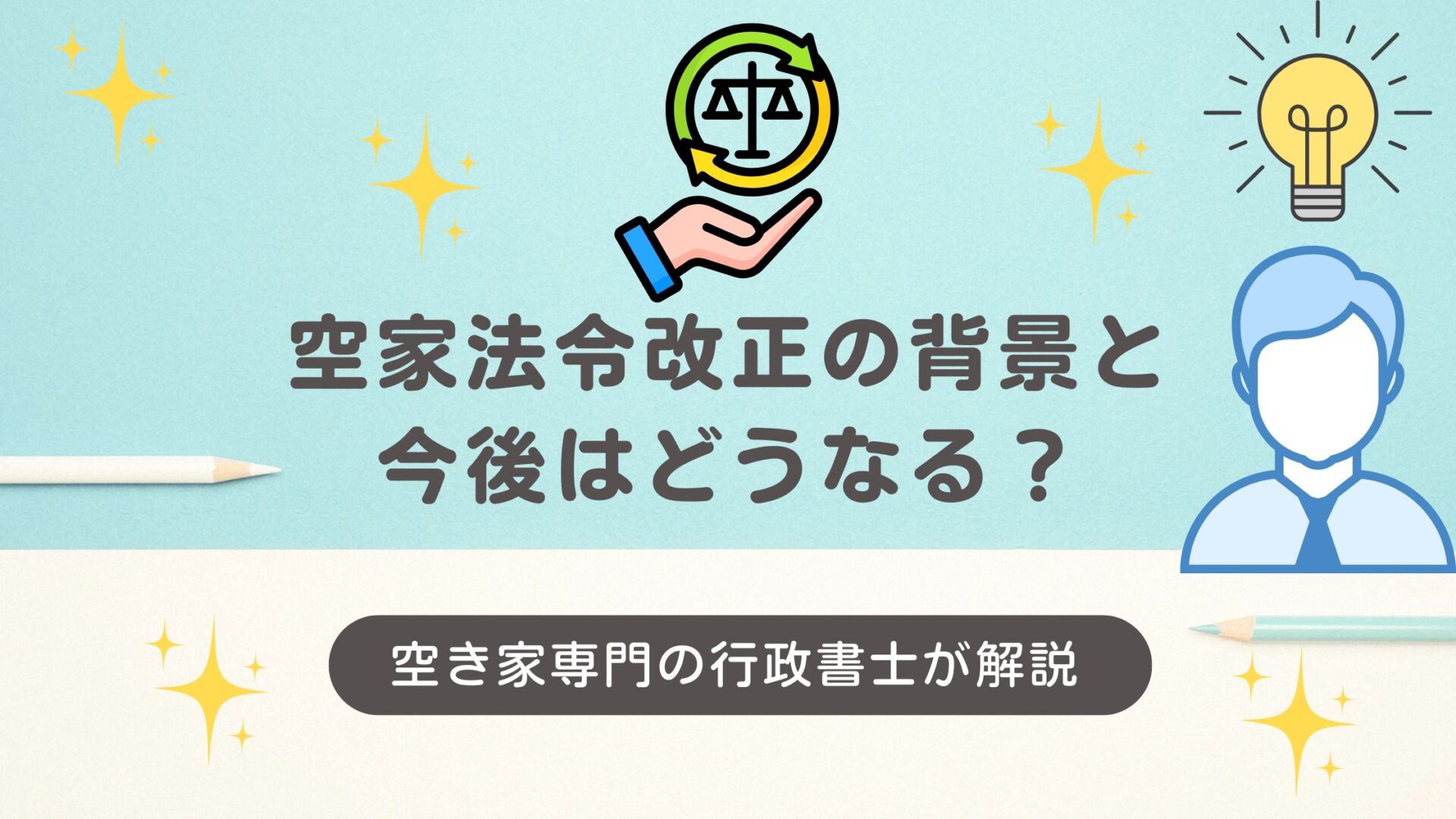
空家法令改正の背景と今後はどうなる?なぜ今、規制が強化されたのか
近年、テレビやニュースで「空き家問題」という言葉を耳にする機会が増えました。特に愛媛県松山市でも、少子高齢化や人口減少により空き家が増加し、地域の課題となっています。そんな中、約1年半前の2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家特措法)が改正され、空き家所有者の皆さまにとってより身近な問題となりました。
この記事では、松山市で空き家専門の行政書士として、また空き家再生診断士として活動する私が、空家特措法改正の概要から、空き家所有者の方々が今すぐ知っておくべきポイント、そして具体的な対応策までを分かりやすく解説します。
空家特措法(空き家対策特別措置法)改正の概要と背景
空家等対策の推進に関する特別措置法とは|制定の目的と内容をわかりやすく解説
「空家等対策の推進に関する特別措置法」、通称空家特措法は、適切な管理が行われていない空き家が全国的に増加し、その結果として地域住民の生活環境の悪化、防犯・防災上の問題、景観の阻害といった様々な問題が顕在化したことを受け、これらの課題を解決するために2014年に施行されました。
この法律の目的は、空き家がもたらす負の側面を解消し、地域の活性化を図ること。具体的には、市町村が空き家対策計画を策定し、特定空家等に対する助言、指導、勧告、命令、代執行といった措置を講じる権限を与えることで、問題のある空き家の発生を抑制し、管理を促進するものでした。
なぜ今「空家特措法」が改正されたのか|社会的背景と課題の深掘り
2014年の施行から約8年が経過し、空き家対策は一定の成果を上げてきました。しかし、それでもなお、空き家は増え続けています。総務省の住宅・土地統計調査によると、2018年には全国で約846万戸の空き家が存在し、今後も増加が見込まれています。
改正の背景には、以下のような社会的な課題の深掘りがあります。これらの課題に対応するため、より早期の段階から空き家対策を講じられるよう、今回の法改正に至りました。
- 空き家問題の深刻化: 特定空家等に指定される前の「管理不全な空き家」が潜在的に多数存在し、放置され続けることで「特定空家等」へと移行するケースが後を絶たない現状があります。
- 地域の生活環境への影響: 放置された空き家は、ごみの不法投棄、不審者のたまり場、倒壊の危険、雑草の繁茂による害虫発生など、近隣住民の生活環境に多大な影響を与えています。
- 所有者への早期対応の必要性: 問題が深刻化する前に、所有者へ適切な管理を促すための新たな枠組みが必要とされていました。
特定空家等になる前の段階で介入することで、問題の深刻化を防ぎ、より多くの空き家を早期に健全な状態に戻すため、規制が強化されました。
空き家問題の現状と増加の理由|放置・危険・管理不全の実態
空き家が増加している主な理由は、以下の通りです。
- 少子高齢化と人口減少: 高齢の親が亡くなり、実家が空き家になるケースが増加しています。しかし、相続人が遠方に住んでいたり、住む予定がなかったりする場合、管理が手薄になりがちです。
- 核家族化とライフスタイルの変化: 若い世代が都市部へ流出し、親元を離れて生活することが増えました。
- 相続時の問題: 複数の相続人がいる場合、空き家の処分や活用について意見がまとまらず、放置されてしまうことがあります。また、相続したくない、管理したくないという理由から、相続放棄を選択するケースも少なくありません。
- 経済的な負担: 空き家を維持・管理するには、固定資産税や修繕費などの費用がかかります。特に老朽化した空き家の場合、多額の費用がかかるため、所有者が対応をためらうことがあります。
- 情報不足: 空き家の所有者が、適切な管理方法や活用方法、行政の支援制度について知らないケースも多く見受けられます。
これらの理由により、管理が行き届かない空き家が「放置空き家」となり、やがて「危険な空き家」や「管理不全な空き家」へと進行してしまう実態があります。
改正法はいつから適用される?主要スケジュールと段階対応
空家特措法の改正は、段階的に施行されています。所有者の方々は、今後のスケジュールを把握し、適切な対応を検討する必要があります。
今回の空家特措法改正は、2023年12月13日に全面施行されました。ただし、一部の規定は施行前から準備が進められており、段階的に適用が開始されています。
主なポイントとしては、後述する「管理不全空き家」に対する新たな措置が加わったことです。これにより、特定空家等に指定される前の段階から、市町村による指導・勧告・命令の対象となる空き家が増えました。
空き家法改正が不動産・相続・所有者に与える影響
今回の法改正は、空き家を取り巻く状況を大きく変え、特に所有者の方々にとって見過ごせない変化をもたらしています。
空き家所有者が直面する変化と具体的対応策
空き家所有者が直面する最も大きな変化は、「管理不全空き家」に対する行政の関与が強化されたことです。これまで「特定空家等」に指定されて初めて厳しい措置が取られていましたが、今後は、適切な管理が行われていないと判断された空き家に対しても、早期に行政指導や勧告、そして命令が入る可能性が出てきます。特に注意したいのが、固定資産税の特例解除リスクです。『管理不全空き家』に指定されると、これまで土地の固定資産税が最大で6分の1に軽減されていた特例が解除され、税負担が跳ね上がってしまう可能性があります。
具体的な対応策としては、以下の点が挙げられます。
- 定期的な状況確認と適切な管理: 空き家を所有している場合は、定期的に現地を訪れて、建物の状態、庭の手入れ、郵便物の確認などを行いましょう。遠方に住んでいる場合は、信頼できる管理会社や専門家に依頼することも検討してください。
- 「特定空家等」や「管理不全空き家」への指定リスクの把握: ご自身の空き家が、どのような状態であれば指定対象となるのかを把握しておくことが重要です。自治体のホームページなどで確認できるガイドラインや判断基準を見ておきましょう。「(例:外壁のひび割れ、屋根の破損、雑草の著しい繁茂、不法投棄の常態化など)」
- 専門家への相談: 不安な点があれば、空き家問題に詳しい行政書士や不動産会社、建築士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。特に、相続の予定がある、売却を検討しているといった場合は、税金や法律に関する専門知識が必要です。
不動産会社・管理会社の役割と経営への影響
空家特措法の改正は、不動産会社や管理会社にとっても、その役割とビジネスチャンスを拡大させる可能性があります。
- 管理業務の需要増加: 空き家所有者からの管理依頼が増えることが予想されます。特に、遠隔地からの管理や、老朽化が進んだ空き家の管理には専門知識が求められるため、新たなサービス展開の機会となります。
- 流通・活用促進の役割: 固定資産税の特例解除リスクが高まることで、空き家の売却や賃貸を検討する所有者が増えるでしょう。不動産会社は、そうした空き家の適切な査定、マッチング、有効活用(リノベーションなど)の提案を通じて、地域経済の活性化に貢献できます。
- 空き家情報の活用: 自治体との連携を深め、空き家に関する情報を共有することで、より効率的な流通や活用促進に繋がる可能性があります。
空き家の相続・売却・解体時の法的注意点と支援制度
空き家を相続する、売却する、あるいは解体するといった場合には、いくつかの法的注意点があります。
- 相続時の注意点:
- 相続人全員の合意: 空き家を相続する場合、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要です。もし合意が難しい場合は、相続放棄という選択肢もありますが、その場合は他の相続財産も放棄することになるため、慎重な検討が必要です。こちらの記事もご参考ください。→相続放棄で固定新税はどうなる?
- 相続登記の義務化: 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続した不動産は、原則として3年以内に登記を完了させる必要があります。
- 相続税・固定資産税: 空き家を相続すると、相続税や固定資産税が発生します。税金対策や特例制度についても確認しておきましょう。
- 売却時の注意点:
- 物件の状態の正確な把握: 売却する際は、空き家の状態(劣化状況、アスベストの有無など)を正確に把握し、買主へ説明責任を果たす必要があります。
- 売却益課税の特例: 一定の要件を満たす空き家を売却する場合、「空き家の3000万円特別控除」などの特例が適用される可能性があります。
- 解体時の注意点:
- 費用と補助金: 空き家の解体には多額の費用がかかります。自治体によっては、解体費用の補助金制度を設けている場合がありますので、事前に確認しましょう。
- 滅失登記: 建物を解体した場合、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。一般的には土地家屋調査士に依頼することになります。
- 近隣住民への配慮: 解体工事は、騒音や粉じんなど、近隣住民に影響を与える可能性があります。事前に説明を行い、理解を得ることが大切です。
松山市でも、空き家の有効活用や除却に関する補助金制度が用意されている場合があります。具体的な手続きや支援制度については、お気軽に当事務所までご相談ください。

空家法令改正への対応方法と今後の対策
自治体・行政による支援・相談体制と今後の対応策
愛媛県松山市をはじめ、多くの自治体では空き家問題に対応するため、様々な支援や相談体制を整えています。
- 空き家バンク制度: 空き家を売りたい、貸したい所有者と、空き家を利活用したい希望者をマッチングする制度です。
- 空き家相談窓口: 空き家に関する様々な悩みに対し、専門家と連携して情報提供やアドバイスを行う窓口です。
- 補助金制度: 耐震改修、リフォーム、解体など、空き家の状態に応じた補助金が用意されている場合があります。
これらの支援制度を積極的に活用することで、空き家問題の解決に繋がる可能性があります。まずは、松山市の空き家関連部署や当事務所にお問合せください。

空き家所有者が今取るべき管理・処分・活用方法
空き家を所有している方々が今取るべき具体的な行動は、以下の3つの選択肢を軸に考えることができます。
- 適切な管理を継続する:
- 定期的な通風、清掃、庭の手入れ、郵便物の整理など、ご自身でできる範囲での管理を徹底します。
- 遠方にお住まいの場合や、ご自身での管理が難しい場合は、信頼できる空き家管理サービスを利用することも有効です。
- 売却を検討する:
- 空き家の活用予定がなく、管理の負担が大きい場合は、売却も有力な選択肢です。
- ただし、築年数が古い、立地が悪いといった物件は、買い手が見つかりにくいこともあります。不動産会社に相談し、適切な査定と売却戦略を立ててもらいましょう。
- 相続登記の義務化など、売却前にクリアすべき法的手続きもありますので、専門家への相談が不可欠です。当事務所では提携司法書士がおりますので、ワンストップで解決することができます。
- 有効活用を検討する:
- 賃貸物件として貸し出す、民泊として利用する、リノベーションして再販するなど、様々な活用方法があります。
- 地域のニーズや建物の状態に合わせて、どのような活用が最適か、専門家と共に検討することをおすすめします。当事務所では、空き家再生診断士として、物件の潜在能力を引き出すご提案も可能です。
今後予想される規制・法改正の動向と対策ポイント
今回の改正で、「管理不全空き家」への対応が強化されたことは、空き家対策がより一層厳しくなっていくことを示唆しています。今後も、空き家問題の深刻化に伴い、さらなる規制強化や新たな法改正が行われる可能性は十分にあります。
今後の対策ポイントとしては、
- 常に最新の情報をキャッチアップする: 自治体や国土交通省のウェブサイトなどを定期的に確認し、空き家に関する最新情報を把握しましょう。
- 早めに行動する: 空き家問題は、時間が経てば経つほど解決が難しくなり、費用もかさむ傾向にあります。問題が深刻化する前に、専門家へ相談し、適切な対策を講じることが重要です。
- 専門家との連携を強化する: 行政書士、不動産会社、司法書士、税理士など、空き家問題に関わる様々な専門家と連携することで、多角的な視点から最適な解決策を見つけることができます。
まとめ|空き家法改正の要点と今後の動向をわかりやすく解説
空家特措法の改正は、単なる法律の変更ではありません。これは、空き家問題に対する社会全体の意識の高まりと、放置された空き家をこれ以上増やさないという国の強い意志の表れです。
今回の改正の要点は以下の通りです。
- 「管理不全空き家」への新たな措置: 特定空家等になる前の段階から、行政の指導・勧告・命令の対象となる空き家が拡大されました。
- 固定資産税の特例解除リスク: 管理不全空き家と指定されると、住宅用地の特例による固定資産税の軽減措置が解除される可能性があります。
- 空き家活用促進への支援強化: 空き家の有効活用や地域貢献を促すための支援制度も拡充されました。
松山市で空き家を専門に取り扱う行政書士として、また空き家再生診断士として、私は空き家所有者の皆様が抱える不安や疑問に寄り添い、最適な解決策をご提案することを使命としています。
ご自身の空き家について少しでも不安や疑問を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。早期の対応が、将来の負担を軽減し、空き家が持つ新たな価値を見出す第一歩となります。



