
注意!0円物件のデメリットとは?失敗談とともに紹介
近年、「物件を無料で譲ります」という魅力的な言葉を耳にすることが増えました。インターネットの空き家バンクやマッチングサイトには、「0円」と書かれた古民家や別荘が並び、夢のような田舎暮らしやセカンドライフが手に入るように見えます。
しかし、その「0円」の裏には、後から数百万円、場合によっては数千万円もの出費を招く、大きな落とし穴が潜んでいることをご存知でしょうか?
この「0円物件」は、単なる掘り出し物ではありません。その実態を知らずに安易に手を出すと、想像もしなかったトラブルや莫大な費用に直面し、「タダでもらったはずなのに、なぜか多額のお金が…」といった後悔に繋がるかもしれません。
この記事では、松山市で空き家に関する専門家として活動する村上行政書士事務所が、0円物件に潜むリスクを解説します。
よくある失敗談や、見落としがちなコスト、法的リスクを分かりやすくご紹介し、あなたの「0円の夢」を「0円の悪夢」にしないために、この記事がお役に立てれば幸いです。
0円物件とは?仕組みと人気の理由を解説

なぜ物件が無料?0円物件の仕組みと背景
0円物件とは、主に所有者が売却を諦め、買い手が見つからないために、無償(0円)で譲渡される不動産のことです。特に地方の空き家がこの形式で流通することが増えています。
なぜ所有者はタダで手放すのでしょうか?その理由は、建物や土地を所有しているだけで発生する「固定資産税」と「管理コスト」にあります。
使われなくなった実家や別荘でも、税金や維持費はかかり続けます。加えて、管理を怠ると建物の老朽化が進み、倒壊の危険性などから「特定空き家」に指定され、さらに重い罰則や税金が課されるリスクもあります。
こうした負担から解放されるため、所有者は「無料でもいいから、誰かに引き取ってもらいたい」と考えるのです。
0円物件が増える理由~空き家・人口減少・地域の過疎化
日本の空き家問題は、深刻な社会課題となっています。少子高齢化と人口の都市部集中により、地方では住む人がいなくなった家が急増しています。
総務省の調査によると、日本の空き家率は年々上昇しており、特に地方では20%を超える地域も珍しくありません。
こうした状況で、所有者と譲り受けたい人のニーズをマッチングするサービスとして、空き家バンクや「みんなの0円物件」のようなサイトが登場しました。
これらのプラットフォームは、地方移住やDIYを夢見る人々にとって、初期費用を抑えて物件を手に入れる魅力的な手段として注目されています。
0円物件の主な取得方法~空き家バンク・みんなの0円物件・自治体譲渡事例
0円物件を手に入れる主な方法は、以下の3つです。
- 自治体の空き家バンク: 自治体が運営する空き家情報サイトです。登録された物件は、地域の移住希望者に向けた情報として公開されています。
- 民間マッチングサイト: 「みんなの0円物件」など、個人間で物件の譲渡を仲介するサイトです。全国の物件が掲載されており、気軽に検索できます。
- 自治体による譲渡事例: 地域によっては、人口減少対策として、特定の条件を満たす移住者に対して、無償で物件や土地を提供する事業を行っている場合があります。
0円物件の真実:デメリットや罠を徹底解説

「無料」という言葉に隠された、本当のコストとリスクについて見ていきましょう。ここからは、村上行政書士事務所が専門家として特に注意を喚起したいポイントです。
0円物件で発生しやすいトラブル・後悔パターン
0円物件の取引では、不動産業者を介さない個人間のやり取りが多いため、専門知識がないまま進めると、後々大きなトラブルに発展するリスクが高まります。
特に多いのが、以下の後悔パターンです。
- 修繕費用が想像以上にかかった: 「少し手直しすれば住めるだろう」と思っていたら、シロアリ被害や雨漏り、基礎の腐食など、素人には判断できない致命的な欠陥が見つかった。
- 解体するしか選択肢がなかった: 建物の老朽化がひどく、リフォーム費用が新築を建てるのと変わらないほど高額になり、結局、解体せざるを得なくなった。
- 引き渡しに関するトラブル: 登記や名義変更に必要な書類が揃っていなかったり、元の所有者が「無料で譲る」と言ったものの、後から金銭を要求されたりするケース。
- 近隣住民とのトラブル: ゴミの不法投棄や庭木の剪定など、物件の管理責任を巡って近隣住民と揉めることがある。
修繕・リフォーム・解体など見落としがちなコストと管理費負担
物件が無料でも、取得後のコストは決して「0円」ではありません。
- 修繕・リフォーム費用:
- 部分的な修繕: 100万〜500万円
- 古民家の全面リフォーム: 30坪で1,350万〜1,800万円が相場です。建物の状態によっては、さらに高額になることもあります。
- インフラ整備費用: 電気・水道・ガスが通っていない物件の場合、引き込み工事だけで数百万円かかるケースも珍しくありません。
- 解体費用:
- 木造家屋の場合、1坪あたり3万〜5万円が相場です。建物が老朽化して重機が入りにくい場合やアスベストが出た場合はさらに、高額になります。
- 年間維持管理費:
- 固定資産税・都市計画税: 市町村によって異なりますが、年額数万円〜数十万円かかります。
- 水道・電気・ガス料金: 使用しなくても基本料金が発生します。
- 管理費: 草刈りや清掃など、維持管理には年間10万〜35万円程度の費用がかかるのが一般的です。
契約・譲渡・所有に関わる手続きと注意点
0円物件の譲渡は、「贈与」という形で行われることが多く、不動産売買とは異なる法的なリスクを伴います。
- 「瑕疵担保責任」がない: 贈与契約の場合、元の所有者は物件の欠陥(シロアリ被害、雨漏りなど)について責任を負いません。引き渡し後に欠陥が見つかっても、修繕費用はすべて譲り受けた側の負担となります。
- 税金のリスク: 「無料」でも、贈与税、不動産取得税、登録免許税などの税金が発生します。特に贈与税は、物件の評価額によっては多額になるため、専門家に相談してシミュレーションしておくことが不可欠です。
- 所有権移転登記のトラブル: 名義変更に必要な書類が揃わない、元所有者の相続人全員の同意が得られないなど、登記手続きでつまずくケースも少なくありません。
事故物件・訳あり物件のリスクとは
0円物件の中には、「事故物件(心理的瑕疵物件)」が含まれている可能性があります。物件内で過去に事件や事故、自殺などがあった場合、それが原因で買い手が見つからず、0円で手放されることがあります。参考記事→心理的瑕疵物件の空き家とは?売却の告知義務と対処法
また、近隣との関係がこじれている、ゴミ屋敷化しているなど、「訳あり物件」である可能性も考慮しなければなりません。これらの事実は、インターネット上の情報だけでは判断が難しく、現地での綿密な調査が必要です。
体験談・失敗談から学ぶ!0円物件買ってみた実例

「実際に0円物件を手に入れた人はどうなったの?」という疑問に答えるべく、よくある失敗談をご紹介します。
よくある後悔・トラブル事例とその原因
「DIYで安く直せると思っていたが、壁を剥がしたら構造部分に腐食が見つかり、業者に依頼すると見積もりは500万円に。予算を大きくオーバーしてしまい、泣く泣く手放すことに…。」
「ゲストハウスとして活用する予定でリノベーションしたが、集客がうまくいかず、リフォーム費用を回収できないまま赤字が膨らんだ。結局、売却しようとしても買い手が見つからない。」
「元所有者の口約束だけで引き渡されたが、後から相続人が現れ、『なぜ勝手に住んでいるんだ』と揉めた。登記もできず、居住権も認められないまま、最終的に退去せざるを得なくなった。」
温泉付き・山林・別荘など特徴ある物件の現実
魅力的な特徴を持つ物件にも、特有のリスクがあります。
- 温泉付き物件: 温泉の権利は物件と一体ではなく、別途権利を購入しなければならなかったり、配管の維持管理に莫大な費用がかかることがあります。
- 山林・僻地の物件: ライフライン(電気・ガス・水道)が未整備で、インフラの引き込み費用が高額になります。また、舗装されていない道路や急な坂道など、アクセスが悪く、生活に不便を感じることも。
口コミ・レビューに見るリアルな声
インターネット上の口コミでは、以下のようなリアルな声が見られます。
- 「タダどころか、むしろ負債だった。修繕費と固定資産税だけで毎月赤字です。」
- 「夢のセカンドライフを期待して購入したが、冬はとにかく寒くて住めず、結局週末の荷物置き場になっています。」
- 「ご近所付き合いが大変。住む前から『ゴミは出すな』『草刈りをしろ』と頻繁に連絡が来て、精神的に参ってしまった。」
0円物件の維持管理・活用で必要な知識
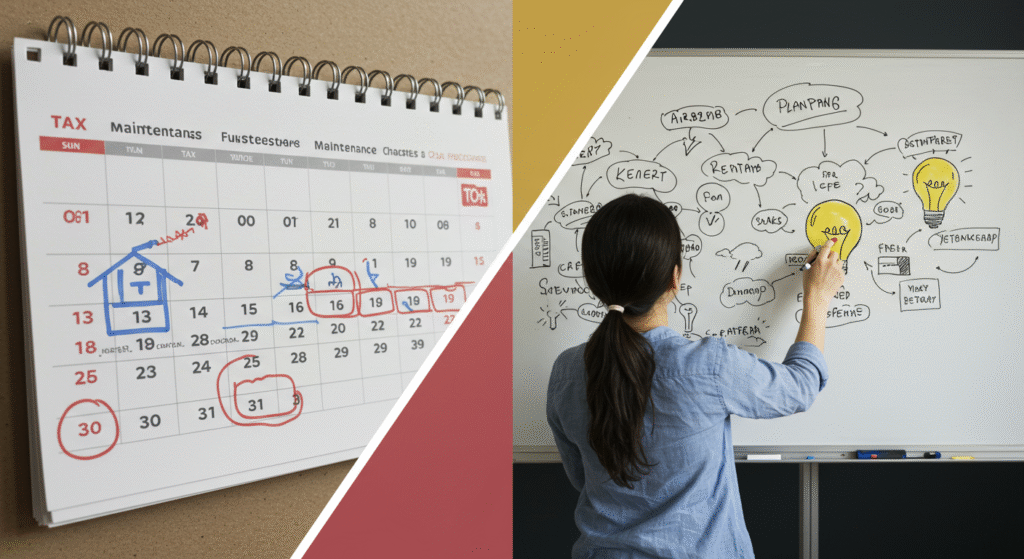
所有後すぐに必要な維持・管理のポイントとコスト
0円物件を所有したら、すぐに以下の維持管理が必要です。
- 最低限の清掃と管理: 庭の草木を刈り、外観を清潔に保つことで、近隣トラブルや特定空き家への指定を防ぎます。
- ライフラインの確保: 水道管の破裂や電気系統のショートを防ぐため、冬季は水抜きをしたり、最低限の管理費を払い続ける必要があります。
活用プラン・リノベーション・DIY・投資活用の選択肢
活用プランを明確にすることで、後悔するリスクを減らすことができます。
- 自分で住む: リフォームやDIYで理想の住まいをゼロから作り上げる。
- 賃貸運用: リノベーションして貸し出し、収益化を目指す。
- コミュニティスペース: 地域住民が交流する拠点として活用する。
固定資産税・税金・補助金など制度と手続き
物件が無料であっても、税金は発生します。
- 固定資産税・都市計画税: 毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
- 各種補助金・助成金: 地方自治体によっては、空き家の改修や解体に対して補助金を支給しています。
- 松山市の補助金制度(一例):
- 老朽危険空家除却事業: 一定の基準を満たす危険な空き家を解体する場合、最大80万円の補助金が受けられます。
- 移住者住宅改修支援事業: 移住者が空き家を改修する場合、工事費の2/3の補助金が受けられます。 これらの制度は、適用要件や申請期間が細かく定められており、専門家のサポートが不可欠です。
- 松山市の補助金制度(一例):
後悔しないための0円物件チェックリストと対策

契約・書類・不動産会社・専門家依頼のポイント
0円物件を検討する際は、以下のチェックリストを必ず確認してください。
- 譲渡契約書は作成するか? 口約束ではなく、贈与契約書を必ず作成しましょう。
- 物件の権利関係は明確か? 登記簿謄本を確認し、所有権が誰にあるのか、抵当権などの権利が設定されていないかを調べましょう。
- 専門家の力を借りるか? 契約・登記手続きは、専門知識がないとトラブルの元です。行政書士や司法書士、不動産コンサルタントに相談しましょう。
物件状態・修繕費用・立地・地域性の調査項目
物件自体のチェックも徹底的に行いましょう。
- 建物の状況:
- 構造的な欠陥: 柱や梁の腐食、傾き、雨漏り、シロアリ被害がないか。
- 断熱・気密性: 冬季の寒さ対策は必要か、結露やカビはないか。
- 立地・環境:
- インフラ: 電気・ガス・水道の状況、公共下水道は整備されているか。
- アクセス: 最寄りのスーパーや病院、駅までのアクセスは良いか。
- 近隣トラブル: 過去に近隣とのトラブルがなかったか、ゴミ出しルールは厳しくないか。
将来的な運用プランと出口戦略(売却や処分など)
万が一、手放したくなった場合の出口戦略も考えておきましょう。
- 売却の難易度: 僻地や老朽化した物件は、売却が非常に困難です。
- 解体費用の準備: 売却できず、解体するしかなくなった場合に備え、解体費用を確保しておく必要があります。
まとめ:0円物件のデメリットと賢い選択のために
0円物件は、一見すると夢のような話に聞こえますが、その裏には多大なコストとリスクが潜んでいます。
- 「無料」は初期費用だけ: 取得後には、修繕費、税金、維持管理費など、数百万円単位の出費が待ち構えています。
- 法的リスクが高い: 贈与契約には瑕疵担保責任がなく、トラブルが発生しやすいのが現実です。
- 専門家のサポートが不可欠: 現地調査から契約、登記、補助金の申請まで、専門知識が必要な場面が多くあります。
村上行政書士事務所は、松山市で行政書士、宅地建物取引士、そして認定空き家再生診断士として、空き家に関するトータルサポートを提供しています。
0円物件の取得を検討されている方は、契約前にぜひ一度ご相談ください。
物件の法的リスクから活用方法、さらには松山市の補助金制度まで、多角的な視点からアドバイスを提供し、あなたの「0円物件」の夢を現実のものにするお手伝いをします。



