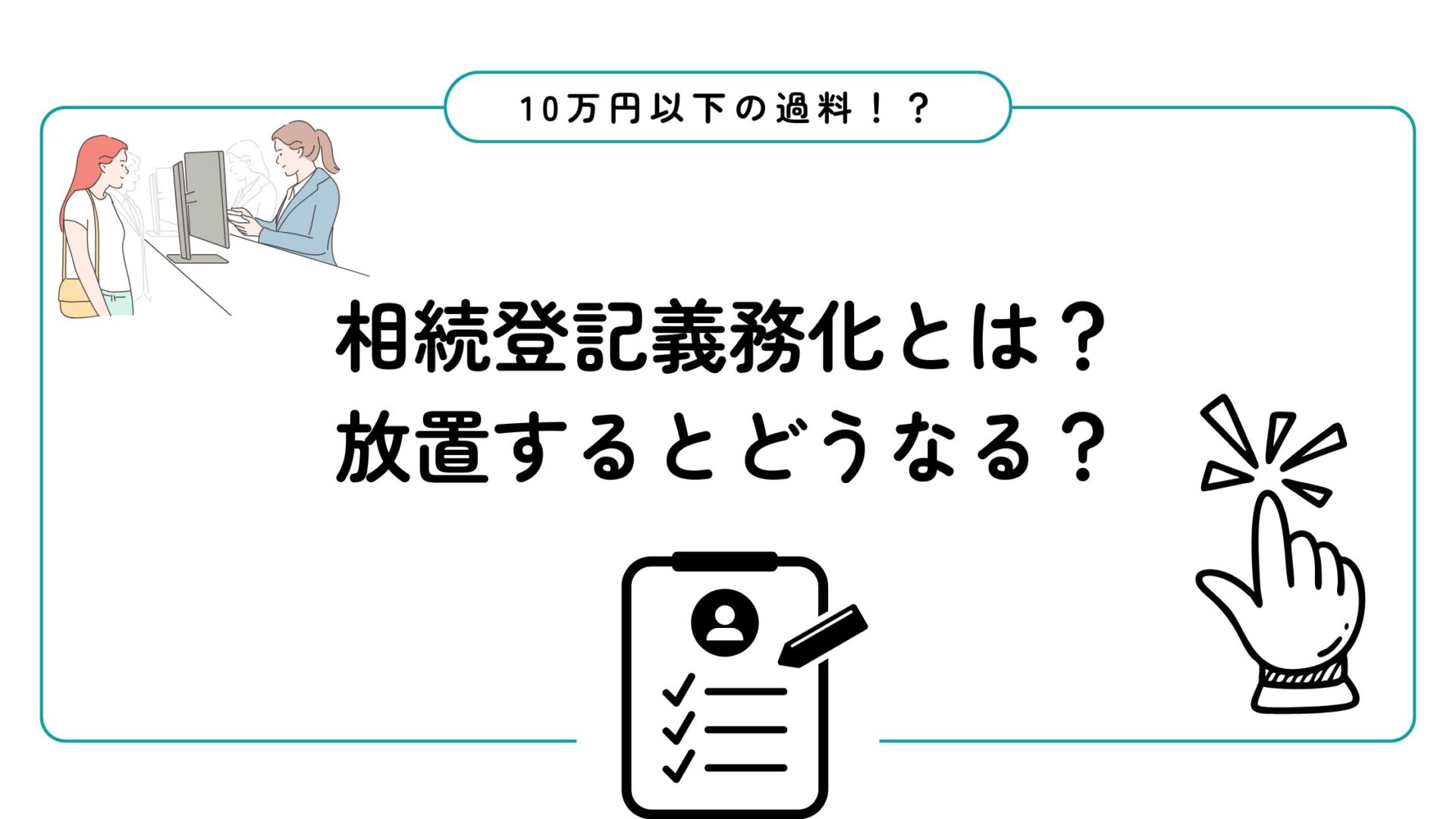
相続登記義務化とは?放置するとどうなる?問題点と対策を解説
「相続登記の義務化」という言葉をニュースなどで耳にして、不安に感じていませんか?
「いつから始まるの?」「過去に相続した実家も対象になる?」「手続きをしないと罰則があるの?」といった疑問をお持ちの方も多いかもしれません。
2024年4月1日からスタートした相続登記の義務化は、あなたの資産を守る上で非常に重要な制度です。もし、相続した不動産の名義変更をせずに放置していると、思わぬトラブルや罰則に発展するリスクがあります。
この記事では、松山市の空き家問題に特化した村上行政書士事務所が、相続登記義務化の「問題点」に焦点を当て、その具体的な「対策」をわかりやすく解説します。
相続登記義務化とは何か?

新制度の概要と目的
相続登記義務化とは、不動産を相続した人が、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を申請することを義務付ける制度です。
これまでは相続登記は任意とされていましたが、法務省が2024年4月1日からこの新制度を開始しました。目的は、所有者不明の土地問題を解消することにあります。
相続登記が行われないことで所有者が特定できなくなり、公共事業や災害復興の妨げとなるケースが増加していました。この問題を解決するために、相続登記の義務化が法制化されたのです。
相続登記義務化の法改正背景
今回の法改正は、2021年に成立した「民法等の一部を改正する法律」によって行われました。
改正の背景には、以下のような問題がありました。
- 所有者不明土地の増加: 相続登記がされないまま放置された不動産が増え、所有者が誰かわからなくなり、社会的な問題となっていました。
- 災害復旧の遅延: 東日本大震災など大規模災害の際、所有者不明の土地が原因で復旧事業が遅れる事例がありました。
- 不動産取引の停滞: 不動産売買や開発の際に、所有者不明の土地がネックとなり、取引が進まないケースがありました。
これらの問題を解決し、不動産が円滑に利用・管理される社会を目指すために、相続登記が義務化されました。
法務省の役割と制度の重要性
法務省は、今回の法改正を主導し、不動産の登記情報が正確に保たれるよう、この制度を運用しています。
相続登記は、あなたの不動産の所有権を明確にするための重要な手続きです。登記がなされていなければ、法的にはあなたが所有者であっても、第三者に対してその権利を主張することが困難になります。
相続登記義務化の対象と期限
義務化の対象となる相続人について
相続登記義務化の対象となるのは、不動産(土地・建物)を相続によって取得したすべての相続人です。
これは、遺言によって不動産を取得した場合や、遺産分割協議によって特定の相続人が不動産を取得した場合も含まれます。
共有名義で不動産を相続した場合も、全員が各自の持分について登記の義務を負います。
過去分の相続登記はいつまで?
「義務化は知っているけど、だいぶ前に相続した分は対象になるの?」と不安に感じている方もいるでしょう。
過去に相続した不動産も、今回の義務化の対象となります。
- 2024年4月1日より前に相続が発生した場合
- 相続登記が済んでいない不動産は、2027年3月31日までに登記申請が必要です。
- この期限を過ぎると、罰則の対象となる可能性があります。
- 2024年4月1日以降に相続が発生した場合
- 不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
令和6年4月1日以降の手続きについて
2024年4月1日以降に相続が開始した場合は、以下の流れで手続きを進めることになります。
- 相続が発生し、不動産の取得を知る
- 3年以内に相続登記を申請する
- 期限内に登記が完了しない場合は、理由を添えて申請が必要
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で登記を申請する「相続人申告登記」という新たな制度も設けられました。
これは、登記の義務を果たすための簡便な手続きで、一旦この登記をしておけば、後日正式な遺産分割協議がまとまってから登記を変更することができます。
相続登記をしないとどうなる?
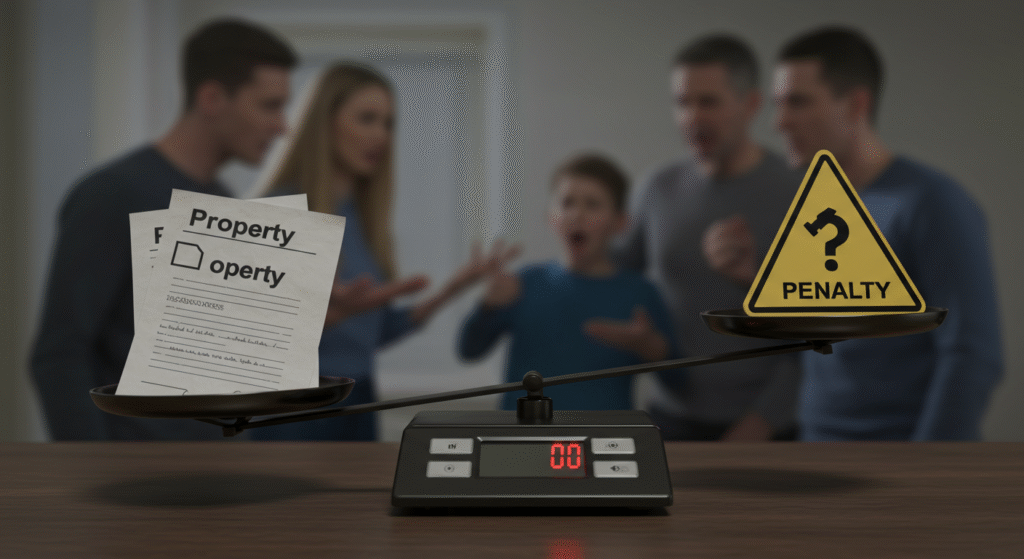
放置した場合のリスクとデメリット
相続登記を怠ることは、単に法律違反となるだけでなく、多くのリスクを伴います。
- 不動産の売却や担保設定ができない: 名義が亡くなった方のままだと、その不動産を売却したり、ローンを組む際の担保にしたりすることができません。
- 共有者の増加とトラブル: さらなる相続が発生すると、共有者がねずみ算式に増えていきます。いざ売却や活用をしようとした際に、親戚の連絡先が分からなかったり、意思決定が難しくなったりして、大きなトラブルに発展する可能性があります。
- 固定資産税の負担: 登記がされていなくても、固定資産税の納税義務は生じます。しかし、所有者が不明確な場合、誰が支払うかでもめることもあります。
義務違反に伴う罰則と過料
相続登記の義務を怠り、正当な理由なく3年以内に申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は、罰金とは異なり刑事罰ではありませんが、法律違反として金銭的なペナルティを受けることになります。
トラブルが発生する可能性
特に深刻なのは、以下の2つのトラブルです。
- 親族間でのトラブル: 誰が不動産を相続するかで、親族間の対立が深まることがあります。
- 第三者への権利主張ができない: 亡くなった方の名義のままにしておくと、その不動産を他人が勝手に売却しようとしたり、抵当権を設定されたりするリスクがあります。この時、あなたが真正な所有者であると主張することが難しくなります。
相続登記義務化における必要書類
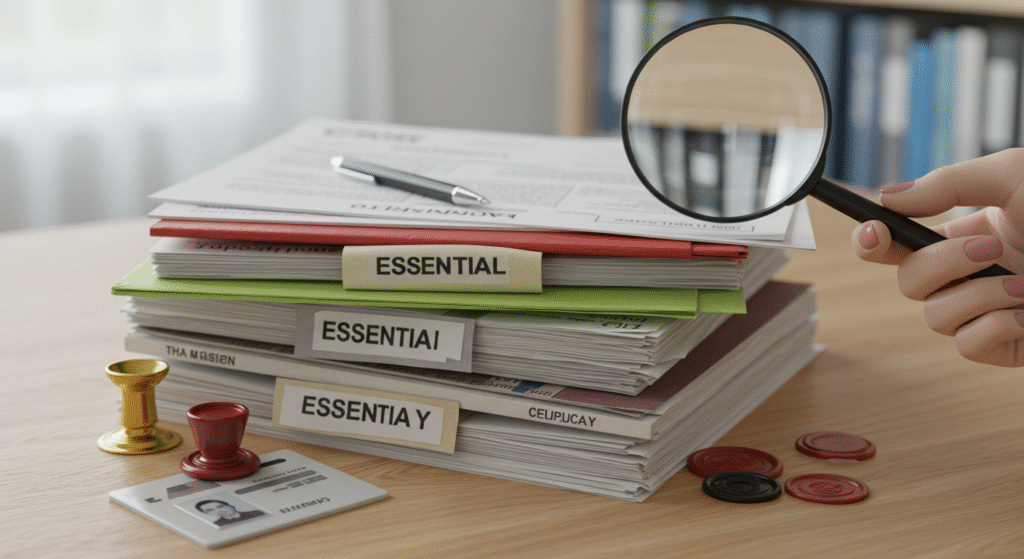
相続登記をするために準備する書類
相続登記の申請には、多くの書類が必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の書類
- 出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の書類
- 現在の戸籍謄本
- 住民票の写し
- 印鑑証明書
- 相続不動産の書類
- 固定資産税評価証明書
- 登記済権利証または登記識別情報通知書
- その他
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
- 遺言書(遺言がある場合)
戸籍謄本や遺産分割協議書の重要性
これらの書類の中でも、戸籍謄本と遺産分割協議書は特に重要です。
戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの連続した記録であり、誰が相続人であるかを証明するために必要です。
また、遺産分割協議書は、相続人全員で不動産の所有権をどのように分けるか合意したことを証明する書類です。署名・実印が必須であり、これがないと相続登記を進めることができません。
相続登記の簡素化と手続きの流れ
簡素化のメリットと手続きの見直し
今回の法改正に伴い、手続きの簡素化も図られました。
- 相続人申告登記: 先述の通り、遺産分割協議がまとまらない場合に、法定相続分でとりあえず登記を行うことが可能になりました。
- 法定相続情報証明制度: 法務局に申請することで、戸籍謄本等の束を一つにまとめた「法定相続情報一覧図」を発行してもらえます。これを添付すれば、複数の金融機関や役所での手続きで戸籍謄本を何度も提出する手間が省けます。
手続きの流れと専門家への依頼
相続登記の手続きは、一般的に以下の流れで進めます。
- 必要書類の収集: 戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書などを集めます。
- 登記申請書の作成: 法務局に提出する書類を作成します。
- 法務局への申請: 管轄の法務局に書類を提出します。
このうち、登記申請書の作成や法務局への申請代理は、司法書士の独占業務です。
行政書士は行うことができません。
ただし、相続登記に必要な戸籍謄本などの収集や、遺産分割協議書の作成サポートなどは、行政書士が業務として行うことが可能です。
戸籍謄本の収集は、被相続人の本籍地が転々としている場合、非常に手間がかかります。また、専門的な知識が必要なため、ご自身で行うことが難しいと感じる方も多いでしょう。
そんな時は、行政書士や司法書士といった専門家への依頼を検討しましょう。
相続登記の費用と負担

登録免許税や司法書士の報酬
相続登記にかかる費用は、主に以下の2つです。
- 登録免許税: 不動産の固定資産税評価額の0.4%が原則としてかかります。
- 専門家への報酬: 司法書士に登記申請を依頼する場合の報酬です。事務所によって異なりますが、一般的には5万円から15万円程度が相場です。
相続登記にかかる費用の具体例
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産を相続する場合、登録免許税は4万円(1,000万円 × 0.4%)となります。
これに司法書士の報酬や、戸籍謄本等の取得費用が加わります。
相続登記義務化の問題点と対策
潜在的な問題点とは?
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決に貢献する一方で、いくつかの潜在的な問題も指摘されています。
- 手続きの複雑さ: 多くの書類を揃える必要があり、手続きが煩雑で一般の方にはハードルが高い。
- 費用負担: 登録免許税や専門家への報酬など、経済的な負担が発生する。
- 罰則の認知度: 罰則があることを知らないまま放置してしまう人が多い可能性がある。
対策として考えられる方法
これらの問題に対する対策は、早めの準備と専門家への相談に尽きます。
- 早めの書類収集: 義務化の期限が迫る前に、戸籍謄本など必要書類を少しずつ集めておきましょう。
- 専門家への相談: 自分で全てを行うのが不安な場合は、司法書士といった専門家に相談することで、手続きをスムーズに進められます。
当事務所では、信頼できる司法書士をご紹介することができますので、お気軽にご相談ください。
過去の相続の取り扱いと今後の展望
過去の相続に関する取り扱いについて
2024年4月1日以前に相続が発生した不動産は、2027年3月31日が登記の期限です。
この期限を過ぎると過料の対象となるため、早めの対応が求められます。
特に、数十年前に相続が発生し、名義が亡くなったままになっているような不動産は、共有者が増えている可能性が高く、早急な対応が必要です。
将来的な影響と法改正の可能性
今回の義務化は、所有者不明土地問題を根本から解決するための第一歩です。
今後は、相続登記がより円滑に行われるよう、さらなる手続きの簡素化や、オンライン申請の普及が進む可能性があります。
不動産を所有するすべての人にとって、「登記は権利ではなく義務」という意識を持つことが、これからますます重要になってくるでしょう。
まとめ:相続登記義務化に備えるために
相続登記の重要性の再確認
相続登記は、義務だからやるのではなく、あなたの不動産という大切な資産を守るために必要な手続きです。
放置すると、過料の罰則だけでなく、将来的な不動産の活用や売却ができなくなり、子や孫の代にまでトラブルの種を残すことになります。
具体的なアクションプランの提案
今、あなたが相続登記を放置している不動産があるなら、まずは以下の3つのアクションを検討してください。
- 所有不動産の確認: 相続した不動産の登記状況を確認しましょう。
- 専門家への相談: 不安な点や不明な点があれば、相続に詳しい専門家(行政書士や司法書士)に相談しましょう。
- 早めの手続き開始: 義務化の期限に間に合うよう、早めに手続きを開始しましょう。
松山市で空き家問題に特化した村上行政書士事務所は、行政書士だけでなく、宅地建物取引士や認定空き家再生診断士の資格も保有しています。相続登記をスムーズに進めるための必要書類の収集サポートや、その後の司法書士への引き継ぎ、不動産の活用、売却、空き家対策まで、ワンストップでサポートすることが可能です。
なお、登記申請手続きそのものは、司法書士の独占業務です。当事務所では、司法書士と連携して、お客様の相続登記を円滑に進めるお手伝いをいたします。
相続した不動産のことでお困りでしたら、まずは一度ご相談ください。
「松山市で相続した実家をどうしたらいいか分からない」「相続登記の手続きが複雑で進まない」といったお悩みにも、専門家が丁寧に対応させていただきます。
まずは、無料相談からご活用ください。



