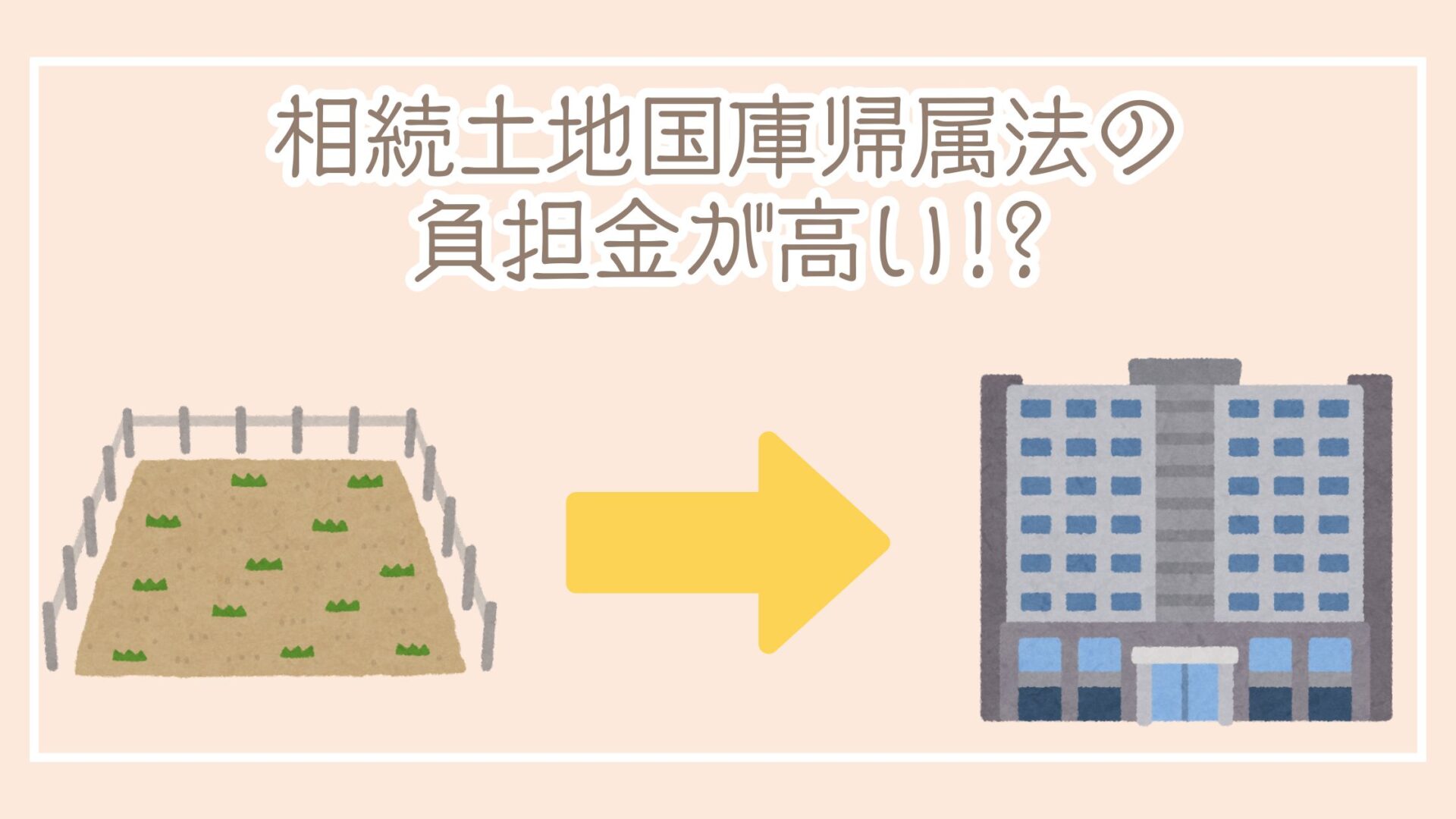
相続土地国庫帰属法の負担金が高い!?知って得する制度の裏側
相続した土地の処分に困っていませんか?「使わない土地、どうしたらいいんだろう…」「売るにも買い手がつかないし、固定資産税だけ払い続けるのは嫌だ…」
もし、あなたがそうした悩みを抱えているなら、「相続土地国庫帰属制度」が解決策になるかもしれません。
この制度は、相続した土地を国に引き渡せるという画期的なものです。
しかし、その利用には「負担金」という費用がかかります。この負担金が「高い」という声も聞かれますが、本当にそうなのでしょうか?
この記事では、制度の概要から負担金の詳細、そして損をしないための活用法まで、専門家として分かりやすく解説します。
相続土地国庫帰属法とは?制度の概要と背景をわかりやすく解説
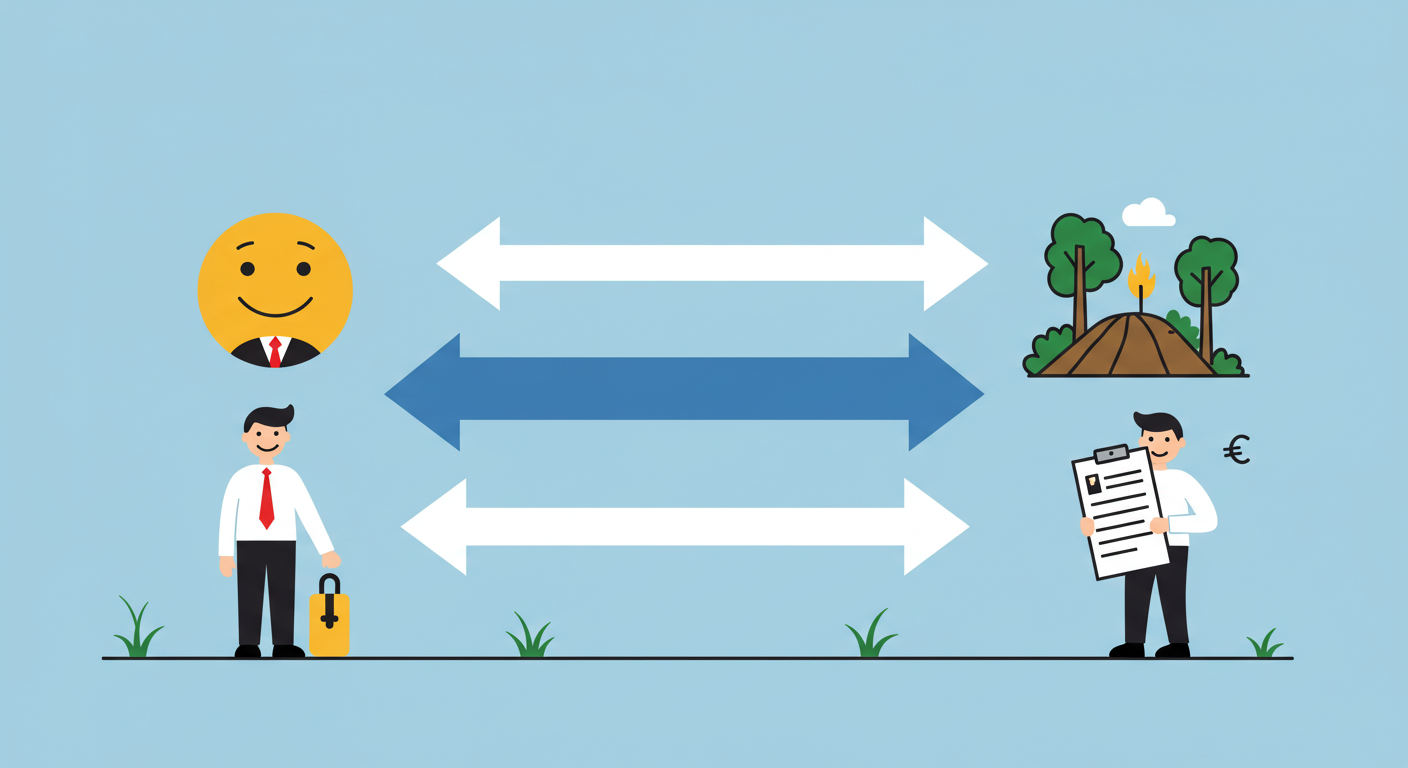
相続土地国庫帰属制度の目的と制定の経緯
長年、日本では所有者不明の土地が社会問題となっていました。登記簿上の所有者が不明だったり、所有者が分かっても連絡が取れなかったりする土地が増え、公共事業や災害復旧の妨げになることもありました。
その背景には、少子高齢化や都市部への人口集中により、地方の土地が利用されなくなり、相続されても誰も管理したがらないという事情があります。
こうした問題に対応するため、2023年4月27日に施行されたのが「相続土地国庫帰属法」です。
この法律は、土地の所有権を手放したいというニーズと、所有者不明土地問題の解決という二つの課題を同時に解決するために生まれた制度です。
土地を国が引き取ることで、個人の負担軽減と公共の利益を両立させることを目指しています。
相続土地国庫帰属法による帰属の仕組みと対象となる土地
この制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人が、その土地を国の所有とするために、法務大臣に承認を求めることができるというものです。
帰属の仕組みは以下の通りです。
- 申請:相続した土地の所有者が法務局へ申請します。
- 審査:国が土地の状況を審査し、承認・不承認を判断します。
- 負担金の納付:承認された場合、申請者が負担金を国に納めます。
- 土地の帰属:負担金が納付されると、土地の所有権が国に移ります。
対象となる土地は、相続または遺贈で取得した土地で、境界が明らかで所有権の所在がはっきりしている土地に限られます。
相続土地国庫帰属法の負担金とは?金額が高いと言われる理由
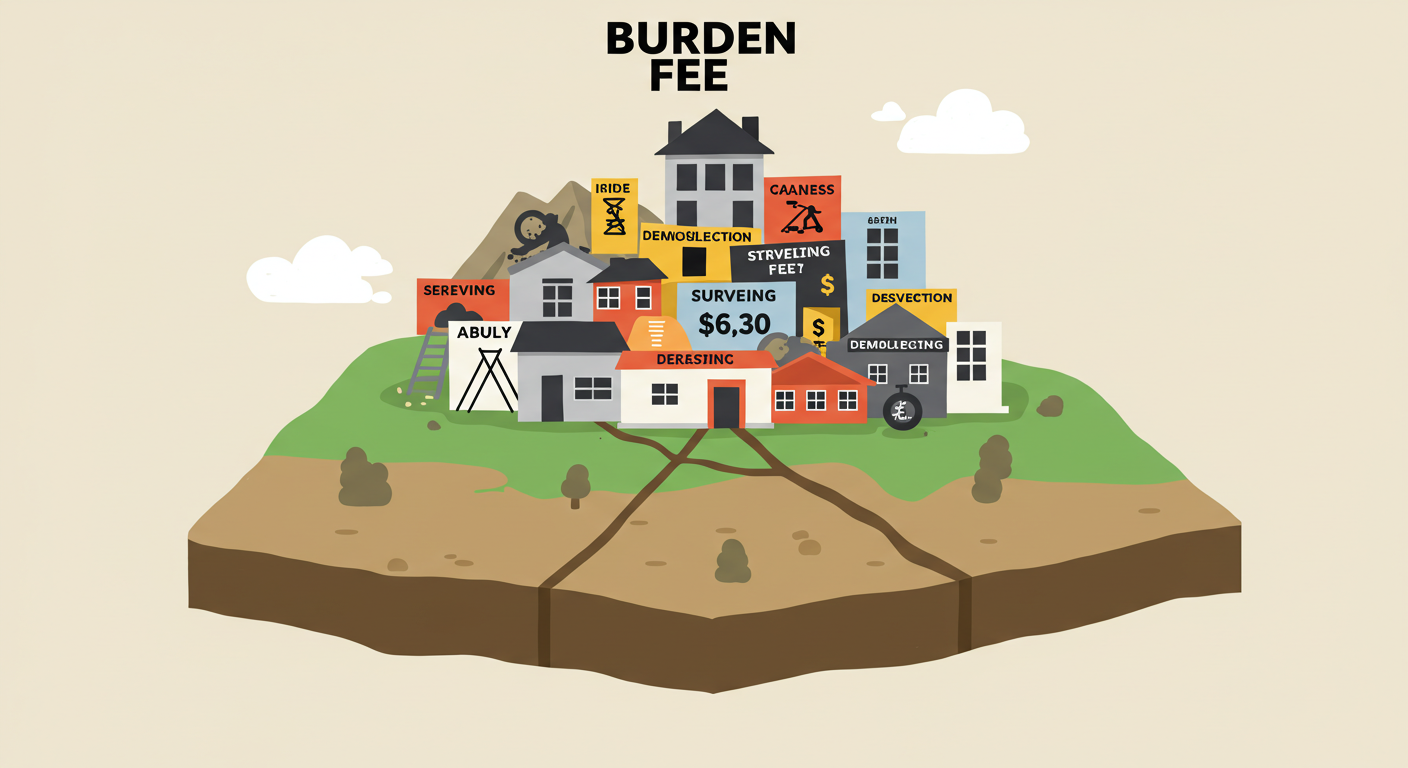
負担金の基礎知識と必要な費用の内訳
負担金とは、国が土地を管理するために必要な費用を、申請者が事前に支払うものです。この負担金の額が「高い」と感じる人が多いのが現状です。
負担金の額は、土地の種別や面積によって定められており、主な費用は以下の通りです。
- 10年分の土地管理費相当額
- その他、特別な管理費用(例:土壌汚染対策費など)
負担金は一律ではなく、個別の土地の状況に応じて計算されます。
負担金が高いと感じる主な要因
なぜ負担金が高いと感じるのでしょうか?主な理由は以下の3つです。
- 一括払い:負担金は、申請時に一括で支払う必要があります。数十万円から数百万円になることもあり、まとまった金額の支払いが負担に感じられます。
- 相場の把握が難しい:土地の状況によって金額が大きく変動するため、事前に正確な負担金の額を把握するのが難しいことも、不安につながります。
- 売却益との比較:売却できれば利益が出ますが、この制度では負担金を支払うばかりで、金銭的なメリットがないと感じる人もいます。
負担金の算定式と計算方法を具体例で解説
負担金は、原則として土地1筆あたり20万円です。これに加えて、宅地、田、畑、森林など、土地の種別や面積に応じて、さらに負担金が加算されます。
<具体的な負担金の例>
| 土地の種別 | 負担金(例) |
| 宅地 | 20万円+1㎡あたりの管理費 |
| 田んぼ・畑 | 20万円+1㎡あたりの管理費 |
| 森林 | 20万円+1㎡あたりの管理費 |
※上記の金額はあくまで目安です。具体的な金額は土地の状況により変動します。
例えば、松山市内の100㎡の宅地の場合、基本負担金20万円に加えて、面積に応じた管理費が加算されます。
納付のタイミングと手数料の違い
負担金は、法務局から承認通知書が届いた後に納付します。通知書には、納付期限が記載されており、期日までに支払う必要があります。
申請手数料とは、申請時に法務局に支払う審査費用のことです。土地1筆あたり14,000円の収入印紙で納めます。負担金とは別のもので、申請時に必ず支払う必要があります。
帰属申請の要件・手続き完全ガイド
申請できる土地の条件・対象外のケース
申請できる土地には、いくつかの条件があります。国が引き取った後に管理する上で、問題となり得る土地は引き取ってもらえません。
<申請できない土地の代表的な例>
- 建物や工作物がある土地:国が管理する前提として、更地であることが求められます。
- 担保権や使用権など、第三者の権利が設定されている土地:所有権以外の複雑な権利関係がある土地は対象外です。
- 通路や墓地など、他人の利用が予定されている土地:国が管理を引き受けることで、他人の利用に支障をきたす可能性があるためです。
- 土壌汚染や埋設物がある土地:管理・対策に多大な費用がかかるため、引き取ってもらえません。
- 境界が不明確な土地:隣地所有者とのトラブルが起こる可能性があるため、明確な境界が確認できない場合は対象外です。
- 通常の管理や処分に過大な費用や労力がかかる土地:崖地、急傾斜地、危険な木が繁茂する森林などがこれにあたります。
農地や山林、宅地の場合の注意点
- 農地:農地法の許可が必要な場合があります。
- 山林:管理状況が悪い場合、特別な管理費用が追加される可能性があります。
- 宅地:建物が建っている場合は申請できません。建物を解体して更地にする必要があります。
法務局への申請手順と必要書類一覧
- 相談:まずは法務局に相談し、申請の可否を確認します。
- 事前調査:土地の状況を調査し、必要書類を準備します。
- 申請:法務局に申請書と必要書類を提出します。
- 審査:国が現地調査を行い、審査します。
- 承認・負担金納付:承認されたら負担金を納付します。
<主な必要書類>
- 申請書
- 土地の登記事項証明書
- 土地の測量図や境界確認書
- 土地の管理状況を証明する写真など
承認・不承認の判断基準と却下事例
承認・不承認は、法務大臣が総合的に判断します。特に重視されるのは、土地の管理状況です。
<却下事例の例>
- 放置されたゴミや廃材が大量にある土地
- 崖崩れの危険がある土地
- 境界が不明確で、隣地所有者とのトラブルが予想される土地
これらのケースでは、国が管理することが難しいため、不承認となる可能性が高いです。
相続土地国庫帰属法で損しないためのポイントと裏側
制度のメリットと意外なデメリット
<メリット>
- 管理の負担から解放される:固定資産税や管理の手間から解放されます。
- 売却が困難な土地の処分が可能:買い手がつかない土地でも手放せます。
<デメリット>
- 負担金:まとまった金額の支払いが求められます。
- 却下の可能性:申請しても必ず承認されるわけではありません。
10年後・将来的な影響と経営・管理上の注意
この制度は、10年分の管理費を負担金として支払うことで、その後は国が管理するというものです。
しかし、将来的に制度内容が変更される可能性もあります。
特に、土地の価格変動や国の財政状況によっては、負担金の額が見直されたり、新たな条件が追加されたりすることも考えられます。制度活用後も国の動向に注目しておくことが大切です。
制度活用時の比較シミュレーション(相続放棄・売却との違い)
| 相続土地国庫帰属制度 | 相続放棄 | 売却 | |
| 費用 | 負担金(数十万円〜) | 費用なし(手続き費用は発生) | 仲介手数料、税金など |
| 手軽さ | やや複雑 | 手軽だが期限あり | 買い手探しが困難 |
| 土地の状況 | 建物や問題がない土地 | 土地自体は引き継がない | 買い手がつくか不明 |
| その他 | 申請から承認まで時間がかかる | 相続財産すべてを放棄する必要あり | 利益が出る可能性がある |
共有名義や遺産分割が未了の場合の対応法
共有名義の土地の場合、共有者全員で申請する必要があります。
一人でも反対すれば申請できません。
遺産分割が未了の場合でも、相続人全員の同意があれば、相続人全員で申請することは可能です。
困った時は?相談・問合せ窓口と専門家の選び方

法務局・相談窓口の案内と初回無料相談の活用法
この制度に関する相談は、最寄りの法務局で受け付けています。制度の概要や手続きについて、まずは法務局に直接問い合わせてみましょう。
また、行政書士や司法書士事務所の中には、初回無料相談を実施しているところもあります。専門家の意見を聞くことで、自分のケースに最適な解決策を見つけられます。
弁護士・司法書士・行政書士等の役割と費用感
- 弁護士:相続トラブルや隣地との境界問題など、法的な紛争解決が必要な場合に依頼します。
- 司法書士:土地の相続登記や名義変更など、不動産登記手続きを専門としています。
- 行政書士:相続土地国庫帰属制度の申請書類の作成や、法務局への手続きの代理を専門としています。
この制度に精通した専門家や状況に応じた適切な専門家を選ぶことが、手続きをスムーズに進める鍵となります。
村上行政書士事務所は、行政書士のほか、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格も持っています。相続した不動産の総合的なコンサルティングが可能です。
相続した土地の処分にお困りなら、ぜひ一度ご相談ください。
申請・手続きでよくあるQ&Aと注意事項
Q:申請から承認までどれくらいかかりますか?
A:申請内容や土地の状況によりますが、数ヶ月から半年程度かかるのが一般的です。
Q:審査中に売却はできますか?
A:できません。審査期間中は、土地の売買や権利設定などが制限されます。
Q:不承認になったら、申請手数料は戻ってきますか?
A:戻ってきません。
相続土地国庫帰属法の負担金を賢く抑えて後悔しない制度活用へ

相続土地国庫帰属制度は、一見すると「負担金が高い」と感じるかもしれません。
しかし、その負担金は、将来にわたる土地の管理費用を国が肩代わりしてくれるためのものです。
相続した土地を放置し続ければ、固定資産税や管理費はかかり続けます。また、将来的に土地の価格が下落したり、法改正によってさらに処分が難しくなる可能性も否定できません。
負担金を支払ってでも、国に引き渡すことで、将来の不確実なリスクから解放されるという大きなメリットがあります。
賢くこの制度を活用するコツは、事前に専門家に相談し、自分のケースでどれくらいの負担金がかかるのか、他にどのような選択肢があるのかを正確に把握することです。
将来、あなたの土地が社会問題となる前に、この制度を上手に活用して、心と経済の負担を軽くしませんか?
相続した土地や空き家の処分について、もしお困りでしたら、いつでもお気軽に当事務所までご相談ください。



