
松山市の法定外公共物占用許可|申請手順と注意点を解説
松山市内において、土地の購入、宅地の開発、または既存の不動産のリノベーションや空き家再生を計画する際、多くの事業者が直面する行政手続きの一つに「法定外公共物占用許可」があります。
これは、敷地と公道とを隔てる水路や里道(旧法上の公共用地)を跨いで橋を架けたり、排水管を埋設したりする場合に必須となる手続きです。
この許可なくして、建築確認申請の前提となる接道義務を法的に満たすことはできず、事業計画全体が頓挫するリスクを抱えます。
法定外公共物に関する手続きは、一般的な不動産取引や建築許可とは異なり、行政法的な厳密さに加え、地域特有の水利慣行や歴史的経緯が複雑に絡み合います。
そのため、単なる書類作成能力だけでなく、不動産の市場価値と建築基準法の要求を理解し、さらに地域コミュニティとの調整能力が不可欠となります。
松山市で不動産活用や空き家再生を円滑に進めるためには、行政書士資格に加え、宅地建物取引士として不動産の評価基準を理解し、認定空き家再生診断士として古い物件の再生を見据えた最適な占用計画を提案できる多角的な知見が、計画の初期段階から求められます。
この記事では、松山市における法定外公共物占用許可の定義から、複雑な申請窓口の分掌、必要とされる高度な技術書類までを網羅的に解説し、円滑な許可取得の道筋を提示します。
松山市の法定外公共物占用許可とは?基本と重要ポイント
法定外公共物の定義と対象(里道・水路・河川など)
法定外公共物とは、道路法や河川法などの個別法に定められた公共物(法定公共物)ではないものの、公共の用に供されている土地や水面を指します。
具体的には、かつての法務局備え付けの地図に公図上で「赤線」や「青線」として記載されていた土地が多く、それぞれ「旧里道」(あぜ道や農道)、「旧水路」(水利に使われていた側溝や河川)に該当します。
これらは歴史的には国が所有していましたが、地方分権一括法(平成12年施行)に基づき、現在は松山市などの地方自治体に管理権限が移譲されています。
松山市は、これらの法定外公共物を適切に管理するため、「法定外公共物財産管理事務取扱要領」 などのローカルルールを定めています。法定外公共物の占用許可は、里道や水路といった公共の財産を、特定の個人や事業者が排他的・継続的に利用することを松山市長が認める行為です。
この許可を得ずに無断で工作物を設置したり、水路を暗渠化したりする行為は違法行為と見なされます。
この「占用」という概念は、公共物の目的外の利用であり、その独占性、排他性、継続性の三点から判断されることになります。
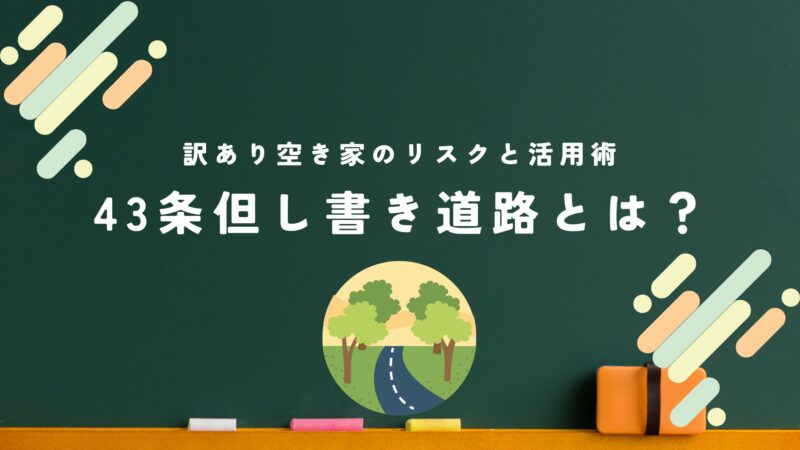
松山市における管理部署と条例の役割
松山市における法定外公共物の管理体制は複雑であり、その性質や手続きの種類によって担当部署が明確に分かれているため、申請者は注意が必要です。この部署の分掌を正しく理解することが、手続きの第一歩となります。
新規で法定外公共物を使用する許可申請、現場の境界確認協議事務、および一般的な里道・水路の管理は、主に松山市役所 都市整備部 道路河川管理課が管轄しています。
申請者はまずこの窓口に相談し、申請の可否や技術的な要件について確認する必要があります。
一方で、既に有効な許可を持つ者が、許可期限を超えて使用を継続する場合の「継続使用許可申請」は、電子申請システム(e-tumo)を通じて行うことが推奨されており 、その受付・管理は農林水産部 農林水産施設整備課が担当しています。
特に農業水利に関わる水路の継続利用はこの部署の管轄となることが多く、申請者は自身の申請が「新規」か「継続」か、また「水利」に関わるか否かによって、問い合わせ先を正確に特定しなければなりません。
松山市が定める「管理要領」は、全国的な原則に加え、松山市独自の技術基準や図面要件を規定しており、全ての申請はこのローカルルールに厳密に従う必要があります。
法定外公共物占用許可が必要なケースと対象物例
どんな工作物・施設・工事が占用許可対象になるか
占用許可が必要となるのは、法定外公共物上に何らかの工作物や施設を設置し、特定の個人や団体がその公共物を独占的、排他的、あるいは継続的に利用する場合です。
最も一般的に許可が必要とされる事例は、土地と公道を隔てる水路を跨ぎ、車や人が通行するための通路用の橋(コンクリート床板橋など)を設置する場合です。
これは、不動産開発における建築基準法上の「接道義務」を確保するために不可欠な行為となります。その他の占用対象には、敷地から公共水路へ排水するための排水管の埋設、上水道管、ガス管、電線、電柱の設置、あるいは水路の暗渠化などが含まれます。
また、大規模な建築工事の際に、一時的に資材置場や仮設通路として公共物を利用する場合も、一時占用として許可が必要です。
松山市の代表的な占用対象(道路・里道・水路・河川)
松山市における法定外公共物占用許可の申請動機として最も重要性が高いのは、個人宅の建設や不動産開発に伴う「接道の確保」です。
例えば、住宅を建設する予定の土地の南側地先が水路によって分断されている場合、申請者はコンクリート床板橋を設置し、これを道路橋として利用することで、敷地の接道を確保する必要が生じます。この行為は、単に行政許可を得るだけでなく、その土地が宅地として適法な価値を持つか、あるいは融資対象となるかを決定づける重要な要素となります。
古い空き家や古民家を再生する場合、認定空き家再生診断士の視点から見ると、敷地と道路をつなぐ既存の構造物(木製の橋など)が法定外公共物上に違法に設置されていたり、老朽化により危険な状態にあるケースがあります。
こうした状況で、既存の構造物を撤去し、現代の技術基準と行政の許可基準を満たした適法なコンクリート製の構造物に置き換える再構築工事も、占用許可申請の重要な対象となります。これにより、不動産の法的安定性と資産価値の向上が図られます。
許可が不要な場合との違い
許可が必要な「占用」とは、その公共物に対する排他的または継続的な利用を伴う行為ですが、一般の公衆が利用する範囲内での使用や、一時的・公共的な目的の使用であれば許可が不要となる場合があります。
例えば、法定外公共物の上を単に通行すること、あるいは公共的な調査や測量のために一時的に立ち入る行為は、原則として許可を要しません。
許可が必要となるか否かの判断基準は、「他の公衆の利用を妨げないか」「公共物の管理に支障をきたさないか」「その利用が特定の者による独占的な利用に当たるか」という点にあります。
法定外公共物占用許可申請の流れと手続き
申請前の準備と必要な情報の確認
法定外公共物使用許可申請は、正式な書類提出よりも前の「事前調整」が許可取得の成否を分けます。申請者はまず、使用目的、場所、期間、設置する工作物の構造や工事実施の方法といった基本情報を明確にする必要があります。
特に水路の占用においては、「利害関係者からの同意」が手続きの最重要課題となります。水路が農業用水路や灌漑施設として利用されている場合、申請地の周囲の土地改良区理事長、水利組合長、または総代(区長)からの承諾書が必須の添付書類となります。
行政の審査は、技術的な図面が揃っているかだけでなく、地域の水利慣行や権利関係が適切に調整されているかを厳しく確認します。この承諾を取り付けるプロセスは、行政の審査期間外で行われるため、早期に着手し、調整にかかる時間を見積もることが極めて重要です。
承諾書には、申請地、水路及び農道の現況幅、工作物の名称や詳細な寸法など、技術的な情報を記載する必要があります。
占用許可申請〜許可取得までの流れ
- 事前相談と現地確認: 申請者は、必要な添付書類や技術基準について、松山市 道路河川管理課(新規申請の場合)に事前に相談します。
- 承諾書の取得: 利害関係者(水利組合、土地改良区等)と協議し、正式な承諾書を取得します。
- 申請書の作成・提出: 「法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)」 および必要な添付書類一式を整え、原則として窓口に提出します。
- 行政審査と補正対応: 松山市は提出された書類に基づき、技術的妥当性、水利上の支障の有無、公共の利益への影響などを審査し、必要に応じて現地確認を行います。図面や書類に不備があった場合は、行政の意図を正確に把握した迅速な補正要求への対応が求められます。
- 許可と使用料納付: 許可が下りた場合、申請者には許可書が交付されます。松山市の条例に基づき、面積や用途に応じた法定外公共物使用料を納付します。
- 継続申請: 許可された使用期間が満了し、引き続き使用を希望する場合は、期限が切れる前に「継続使用許可申請」を、農林水産施設整備課 に電子申請(e-tumo)にて行う必要があります。
着手時期・工事前後の注意点
申請者は、許可書が交付されるまで、工事に着手することはできません。許可を得た後、工事開始前に松山市に対して「工事着手届」を提出する必要があります。
工事が完了した際には、速やかに「工事完了届」を提出し、松山市による完了検査を受けなければなりません。この完了検査に合格することで、設置された工作物や施設が、許可された設計図および技術基準に適合していることが確認され、正式に占用が認められることになります。
検査に合格しなければ、占用は適法と認められず、追加工事や手直しを求められる可能性があるため、設計通りの施工と行政への報告が不可欠です。
必要書類・様式と書き方ガイド
法定外公共物使用許可申請では、申請書本体よりも、添付書類に高い技術的正確性が求められます。不備の多くは技術的な図面や権利関係の書類に集中するため、準備には細心の注意が必要です。
法定外公共物使用許可申請書(記入例付)
法定外公共物使用許可申請書は、松山市の公式ウェブサイト内から様式(様式第1号)を入手可能です。→ダウンロードページ
申請書には、申請者の情報、使用場所、使用目的、使用数量(面積など)、施設または工作物の構造、工事実施の方法、使用期間、工事の期間などを詳細に記載します。
使用目的の記載は、単なる事実の羅列ではなく、申請の必要性を明確に示す必要があります。例えば、典型的な水路上橋の設置事例では、「〇〇町〇〇番地の住宅建設予定地において、南側水路にて分断された接道を確保するため、コンクリート床板橋を設置する」といった具体的な記述が求められます。
使用する場合は必ず松山市役所のホームページから最新版をダウンロードしてください。
添付書類(図面・計画書・その他)の具体例
松山市が要求する添付書類は多岐にわたり、その要求水準は非常に厳密です。単なる略図ではなく、測量に基づく正確な資料の作成が求められます。
| 添付書類 | 技術的要件と目的 |
| 事業計画書 | 簡易な工作物を除く。事業全体の概要と、占用が必要な理由を説明する。 |
| 位置図・平面図 | 許可を受けようとする区域及びその周囲約100メートル以内の地形、地目等を表示する。都市計画や周囲の状況を把握するために不可欠 。 |
| 測量図・求積表 | 許可を受けようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの。正確な占用面積を算出し、使用料算定の基礎とする 。 |
| 断面図・構造図・設計書 | 工作物を設置する場合、その詳細な設計書及び構造図。技術的基準(強度、水利への影響)適合性を証明する。 |
| 利害関係者の同意書 | 土地改良区理事長、水利組合長、総代又は区長など、水利上の利害関係者からの承諾書。 |
| 現況写真 | 申請地の現況を示す写真。工事前後の状況を比較する基礎資料となる。 |
| 法務局公図の写し | 申請地と法定外公共物の法的な境界関係を証明する。地籍図等の写しでも可。 |
これらの図面に関する技術的な要求水準の高さが、申請手続きにおける難易度を上げています。特に、占用面積の算定方法を示す求積表は、面積の正確性を証明するために必須であり、不正確な図面は行政から補正要求を受ける主要因となります。
PDF様式の入手・Adobe Readerでの利用方法
法定外公共物使用許可申請書の様式は、松山市公式ホームページ内の「法定外公共物使用許可申請書」のページからダウンロードできます 。様式はPDF形式で提供されていることが多いため、申請者はAdobe Readerなどのソフトウェアを利用して必要事項を正確に記入し、印刷して提出することが一般的です。新規申請に関しては、電子申請ではなく窓口への提出が基本となります。
よくある疑問・つまずきポイントQ&A
申請内容や提出先に関するよくある質問
Q: 占有料の目安は?
A: 法定外公共物の使用料は、松山市の使用料条例に基づき、占用する面積、期間、および利用目的によって算定されます。具体的な単価は用途や面積によって異なりますが、八幡浜市の例のように、地方自治体は公共物使用料を定めています。正確な使用料について知るには、申請者は申請前に占用の詳細を伝えた上で、担当課に確認することが推奨されます。
Q: 担当課がわからない場合は?
A: 法定外公共物の担当課は、新規使用許可は都市整備部 道路河川管理課 、継続使用許可は農林水産施設整備課と分かれています。申請者が判断に迷う場合は、まず松山市コールセンターに問い合わせるか、都市整備部 道路河川管理課に、使用を希望する里道や水路の所在地を伝えて、新規申請の担当を確認すべきです。
公共物使用許可と岡山市など他市との違い
法定外公共物に関する手続きの法的枠組みは、岡山市の例のように、全国の自治体で共通しており、申請書類の類型も類似しています。
しかし、松山市特有の難しさは、そのローカルルールと、部署間の複雑な分掌にあります。松山市は独自の「財産管理事務取扱要領」を持ち、技術的な添付書類の要件が詳細に定められています。
さらに、新規と継続、水路の性質によって窓口が厳密に分かれている体制は、初めて申請を行う者にとって大きな混乱の原因となり得ます。
そのため、地域に根差した専門家の知見に基づき、行政側の慣習を理解した上で申請を進めることが重要です。
不備時・追加資料の対応方法
行政審査の過程で最も多く発生する不備は、図面に関する技術的な要件の不適合、および利害関係者からの同意書が不十分であるケースです。特に測量図や構造図の不備は、工事の安全管理や公共物への影響評価に直結するため、行政は厳格な補正を要求します。
補正要求を受けた場合、行政書士は行政の意図を正確に把握し、技術者や利害関係者との連携を迅速に行い、手戻りを最小限に抑えるコンサルティング機能を提供します。
例えば、図面の補正が必要であれば、技術的な知識を用いて行政が求める精度に修正し、同意書が不十分であれば、再度水利関係者との交渉を代行し、行政が納得する形式での承諾書を迅速に取り付けることで、許可取得までの期間短縮に貢献します。
松山市の占用許可申請窓口・問い合わせ先一覧
法定外公共物に関する申請において、適切な窓口に問い合わせることは、手続きを円滑に進める上で不可欠です。以下に、松山市の主要な担当部署の連絡先をまとめています。
松山市 法定外公共物関連 主要担当部署連絡先
| 担当部署 | 主な業務内容 | 電話番号 | 備考 |
| 都市整備部 道路河川管理課 | 新規の法定外公共物使用許可申請に関する相談、境界確認協議事務、現地調査の管轄 | 089-948-6907 | 松山市役所(二番町)に所在。新規・境界確認の窓口。 |
| 農林水産部 農林水産施設整備課 | 法定外公共物継続使用許可申請の受付、電子申請システム管理(e-tumo) | 089-948-6577 | 主に継続使用や農業水利に関する水路の管轄。受付時期に注意。 |
| 松山市コールセンター | 手続きの一般的な案内、担当課不明時の案内 | 089-946-4894 |
受付時間・開庁日・提出時の注意事項
松山市役所の受付時間は、一般的な自治体と同様に平日(開庁日)の8時30分から17時00分までです。新規の法定外公共物使用許可申請は、その重要性から、原則として窓口での提出と事前相談が求められ、郵送での提出は受け付けていないことが多いです。
申請書類は正本・副本など複数部数を求められる場合があるため、提出前に必要部数を担当課に確認する必要があります。
まとめ|松山市で法定外公共物占用許可を円滑に取得するコツ
松山市における法定外公共物占用許可の取得は、不動産活用、特に接道確保を目的とする建築計画の根幹を担う重要な手続きです。この許可を円滑に取得するための鍵は、「技術的な正確性」と「社会的合意の形成」という二つの主要な障壁を乗り越えることに集約されます。
まず、技術的な側面では、周囲100メートルを含む詳細な図面、厳密な求積表、そして工作物の構造図といった、行政の要求水準を満たす書類を完璧に準備することが不可欠です。
次に、社会的合意の形成においては、特に水路の占用において、土地改良区や水利組合などの利害関係者から、水利上支障がない旨の正式な承諾書を取得することが、行政審査通過の絶対条件となります。この調整に要する時間と労力は、計画全体のスケジュールに大きな影響を及ぼします。
村上行政書士事務所は、行政書士としての煩雑な書類作成と行政交渉の代行に加え、宅地建物取引士として不動産のリスクと接道義務を理解し、認定空き家再生診断士として古い物件の法的再生を見据えた最適な占用計画を提案できる強みを有しています。
松山市内で法定外公共物に関連する複雑な問題に直面した場合、これらのトリプルライセンスを持つ専門家の支援を早期に受けることが、事業計画の円滑な進行と、時間的・費用的コストの最小化に繋がる最善の策となります。
専門家とのパートナーシップを通じて、法定外公共物に関するトラブルを未然に防ぎ、松山市での不動産活用を成功へと導くことが可能となります。
もしあなたが
- 宅地開発や建築計画で、水路や里道の境界確認や占用手続きに直面している
- 古い空き家や中古物件の再生において、接道確保や排水設備の新設が必要な状況にある
- 利害関係者(水利組合等)との協議が難航している、またはどこから手をつけて良いかわからない
のであれば、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
村上行政書士事務所は、行政書士としての申請代行に加え、宅地建物取引士の知見で不動産活用を見据えた最適な占用計画を立案し、認定空き家再生診断士として再生後の未来までを視野に入れた手続きをサポートします。
初回は無料相談実施中です!



