
家族を守る!空き家特例と老人ホームの関係とは?
松山市にお住まいの皆さま、ご両親が老人ホームに入所されたり、亡くなられたりした後に残された実家(空き家)の扱いに悩んでいませんか?
「空き家を売却したいけれど、税金が高いと聞いた」
「親が老人ホームに入っていた場合、『空き家特例(3,000万円控除)』は適用できるのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方へ。この特例は、老人ホームへの入所がきっかけで空き家になった場合でも、厳格な要件を満たせば適用できる可能性があります。
しかし、その適用要件は複雑で、特に老人ホーム等の種類や入所中の家屋の利用状況でミスをすると、せっかくの税制優遇を受けられなくなるリスクがあります。
松山市で空き家業務を専門とする村上行政書士事務所は、行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士のトリプル資格を持つ専門家として、煩雑な手続きを一括でサポートします。
この記事では、「空き家特例と老人ホーム」という、多くの方が直面するテーマについて、国税庁の最新情報に基づき、解説しております。
本記事の内容は、税制に関する一般的な情報提供を目的としており、税理士法に基づく税務相談や税務申告の代行を意図するものではありません。行政書士は税理士の独占業務である税務相談や申告代行を行うことはできません。具体的な税額計算や申告手続きについては、必ず税理士にご相談ください。
空き家特例と老人ホームの基本|制度の全体像とポイントを解説
空き家特例とは?居住用財産・3000万円控除の仕組み
私たちが普段「空き家特例」と呼んでいるのは、「被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除」のことです。
これは、相続によって取得した空き家を売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという画期的な制度です。

【特例の主な要件チェックリスト】
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 家屋の建築時期 | 昭和56年12月31日以前に建築された家屋であること。 |
| 家屋の種別 | 区分所有建物登記がされている建物(マンションなど)でないこと。 |
| 相続開始直前の居住 | 亡くなった方(被相続人)が一人で居住していたこと。(老人ホーム特例利用の場合は後述の要件あり) |
| 譲渡価額 | 譲渡価額が1億円以下であること。 |
| 売却期限 | 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。 |
この特例を活用できれば、多額の譲渡所得税を節税でき、手元に資金を残して今後の生活やご家族を守ることができます。
老人ホーム入所が「空き家特例」に関係する理由
この特例を適用する上で最も重要なのが、「被相続人が相続開始の直前までその家屋を居住用として使用していたこと」という要件です。
通常、亡くなる前に老人ホームに入所し、住民票を施設に移していると、その家屋は「被相続人の居住用財産」ではなくなり、特例の対象外となってしまいます。
しかし、特例には、特定事由(老人ホーム等への入所)を理由に家屋の居住利用がなくなった場合の例外規定があります。
<老人ホーム入所に関する特例の例外規定(国税庁 No.3307より)>
以下の3つの要件すべてを満たす場合、その家屋は特例の対象となります。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 要件1:特定事由による入所 | 介護保険法上の要介護認定等を受けていた被相続人が、国が定める特定の老人ホーム等に入居・入所していたこと。 |
| 要件2:空き家期間中の利用制限 | 入所により居住の用に供されなくなった時から相続開始の直前まで、事業や貸付、被相続人以外の居住の用に供されていなかったこと(物品の保管は可)。 |
| 要件3:主たる居住地 | 入所した時から相続開始の直前まで、被相続人が主として居住の用に供していたと認められる家屋がその老人ホーム等であること。 |
この例外規定があるからこそ、「親が老人ホームに入居した後に売却した実家」でも3,000万円控除の可能性が出てきます。
相続空き家の特別控除とは?国税庁の最新情報(令和6年対応)
空き家特例は、平成28年の創設以降、何度か改正が加えられています。
特に最新の令和6年(2024年)以降の対応として重要なポイントは以下の通りです。
| 改正点 | 内容 |
|---|---|
| 適用期間の延長 | 令和7年12月31日まで適用期間が延長されました。(今後も延長の可能性あり) |
| 売却人数の緩和 | 相続人が3人以上の場合でも、特例を適用できるケースが拡大されました。 |
| 家屋の要件緩和 | 令和6年1月1日以降の譲渡について、売却後に家屋を取り壊した場合、取り壊し後にもその土地を売却できます。(特例適用期間の緩和など細かな規定あり) |
これらの改正により、特例がより利用しやすくなっていますが、手続きの複雑さも増しています。
空き家特例を老人ホーム入所で適用するための要件整理
老人ホームへの入所を理由に空き家特例を適用するためには、通常の特例要件に加えて、国税庁が定める「特定事由」に関する厳格な要件を満たす必要があります。
適用できるケースの具体例|配偶者・入居・自宅がある場合
特例適用可否の判断で最も間違いやすいのが「誰がいつまで住んでいたか」という点です。以下の具体例で確認しましょう。
| 事例 | 状況 | 特例適用の可否 | 重要なポイント |
|---|---|---|---|
| ケース1:単身入所 | 父親が一人暮らし。要介護認定後、老人ホームに入所。家屋は空き家のまま、施設で亡くなった後に子が売却。 | 適用可能 | 被相続人以外に居住者がおらず、入所後の家屋利用制限(貸付等なし)を満たすため。 |
| ケース2:配偶者(母)が同居 | 父親が老人ホームに入所後、母親(配偶者)が亡くなるまで自宅に居住していた。 | 適用不可 | 特例は「被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」が要件。配偶者が居住していた場合は適用外。 |
| ケース3:親族が介護で同居 | 父親が老人ホーム入所直前まで一人暮らしだったが、介護のため親族(子)が数ヶ月同居した後に入所。 | 原則適用不可 | 老人ホーム入所直前に「被相続人以外が居住していた」要件に抵触するリスクが高い。(非常に判断が難しいケースのため専門家への相談が必須) |
どんな施設が対象?要介護認定・入所要件をチェック
特例適用となる「特定事由」は、以下の要介護認定または障害支援区分の認定を受けていた被相続人が、指定された施設に入所・入居していた場合に限ります。
1. 介護保険法に基づく認定と対象施設
被相続人が介護保険法第19条第1項の要介護認定もしくは同条第2項の要支援認定を受けていた場合が対象です。
| 対象施設(特定事由イ) | 概要 |
|---|---|
| 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居 | グループホームなど |
| 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム | 老人福祉法に基づく施設 |
| 有料老人ホーム | 老人福祉法第29条第1項に規定するもの |
| 介護老人保健施設、介護医療院 | 介護保険法に基づく施設 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 有料老人ホームに該当するものを除く |
2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく認定と対象施設
被相続人が障害支援区分の認定を受けていた場合も対象です。
| 対象施設(特定事由ロ) | 概要 |
|---|---|
| 障害者支援施設 | 施設入所支援が行われるものに限る |
| 共同生活援助を行う住居 | グループホームなど |
【重要なチェックポイント】 要介護認定や障害支援区分の認定は、家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人がその認定を受けていたかどうかで判定されます。
取り壊し・耐震基準・家屋要件など細かな注意点
特例を適用して売却する方法は、主に以下の2つです。
| 売却方法 | 要件 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 家屋をそのまま売却 | 家屋が新耐震基準(昭和57年以降の基準)に適合していること。 | 買主を見つけにくいが、取り壊し費用がかからない。売却前に耐震リフォームが必要になる場合がある。 |
| 取り壊して土地として売却 | 譲渡時まで建物を取り壊し、更地にすること。 | 買主を見つけやすいが、取り壊し費用や固定資産税がかかる。多くの場合、この方法が選択される。 |
特に重要なのは、老人ホーム入所後(居住の用に供されなくなった時)から相続開始の直前までの取り扱いです。(国税庁要件2.イ、ロ)
- 被相続人の物品の保管やその他の用に供されていたこと。
- 事業の用、貸付けの用、または被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
空き家期間中、家屋を第三者に賃貸したり、事業に使用したりすると、特例の適用要件を失います。この期間は、文字通り「被相続人のための空き家」として維持することが求められます。
必要書類と実際の手続き|住民票・確認書・チェックシート解説
特例の適用で最も難易度が高いのが、税務署に提出する「被相続人居住用家屋等確認書」の取得と、必要書類の整備です。
必要書類リスト|住民票から登記まで
税務署へ確定申告する際に必要となる主な書類は以下の通りです。
| 分類 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 税務署提出書類 | 確定申告書、譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し | 譲渡所得の計算と申告に必須 |
| 特例適用証明書類 | 被相続人居住用家屋等確認書(松山市役所等発行) | 特例適用の要件を満たす証明書。最も重要。 |
| 被相続人関連書類 | 戸籍の附票の写し、住民票の除票の写し | 亡くなる前の居住実態を確認する。 |
| 物件関連書類 | 家屋の登記事項証明書 | 家屋の建築時期や面積を確認する。 |
| 老人ホーム関連書類 | 老人ホームの入所証明書(写し)、要介護認定等の履歴が確認できる書類 | 特定事由による特例適用であることを証明する。 |
チェックシート活用法と様式・書き方のポイント
「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例の要件を満たしていることを市区町村(松山市役所など)が確認・証明するための書類です。
<老人ホーム入所ケースでの重要ポイント>
- 住民票の除票: 被相続人が老人ホームに住民票を移している場合、この書類で「老人ホームへの転居」を確認できます。
- 確認書様式: 確認書の様式に添付書類として、老人ホームの入所契約書や要介護認定の写し、入所日・退所日を証する書類などを添付し、特定事由による特例適用であることを明記する必要があります。
- 松山市での手続き: 松山市役所の担当窓口(住宅関係や固定資産税関係の部署が多い)で確認書を発行してもらいます。事前に対象施設の種類や認定状況を電話で確認することが重要です。
書類の提出先・受付窓口|国税庁や税務事務所の対応方法
最終的に特例の申請を行うのは、税務署への確定申告時です。
- 確認書の取得: まずは松山市役所等で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得します。
- 確定申告: 売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に、売却した家屋の所在地を管轄する税務署(松山市であれば松山税務署)へ確定申告を行います。
行政書士である村上行政書士事務所は、この複雑な確認書取得までの手続きや、戸籍・住民票の収集を代行し、お客様の負担を大幅に軽減します。
令和6年以降の申告・準備での注意点
令和6年以降の申告では、特に以下の点に注意が必要です。
- 譲渡価額の把握: 1億円を超える譲渡価額の場合は特例が適用できません。売却活動開始前に、適正な価格(時価)を把握しておく必要があります。
- 売却前の相続登記: 特例の適用を受けるためには、相続人への名義変更(相続登記)が済んでいることが大前提です。松山市の空き家の場合、未登記のまま放置されているケースも多いため、まず相続登記を完了させましょう。司法書士の業務になります。
空き家の売却と特例活用|譲渡所得・控除の計算と申請方法
譲渡所得の計算と特別控除との関係
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。特例適用時の計算は以下の通りです。譲渡所得=収入金額(売却代金)−(取得費+譲渡費用)
この計算で出た譲渡所得から、最大3,000万円を差し引けるのが空き家特例です。
【特例適用時の税金計算例】
松山市の空き家を5,000万円で売却(収入金額)し、取得費・譲渡費用が合計1,000万円だった場合。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 譲渡所得 | 5,000万円−1,000万円=4,000万円 |
| 特別控除 | 最大3,000万円 |
| 課税譲渡所得 | 4,000万円−3,000万円=1,000万円 |
| 譲渡所得税 | 1,000万円×税率≈約200万円 |
| (特例なしの場合) | 4,000万円×税率≈約800万円 |
特例を適用することで、この例では約600万円もの大幅な節税効果が生まれることが分かります。(税率は長期保有の場合の概算です)
売却までの流れと実務での注意点
村上行政書士事務所は宅地建物取引士の資格も持つため、特例を前提とした売却活動をワンストップで支援できます。
- 相談・要件チェック(行政書士): 特例適用要件(特に老人ホーム入所の条件)を満たしているか確認。
- 売却査定・媒介契約(宅建士): 市場価格の査定と売却計画の策定。
- 確認書等の取得(行政書士): 市役所等での確認書取得手続きを代行。
- 売却活動支援: 買主との契約、決済。(提携不動産会社へのご紹介)
- 確定申告サポート: 税理士との連携をサポート。
実務上、「更地にして売るか、建物付きで売るか」の判断が非常に重要になります。建物の状態や松山市内の土地需要を見極めた最適な提案を行います。
土地や家屋の取り壊し・改修工事のガイドライン
認定空き家再生診断士の立場から、空き家対策をアドバイスします。
- 取り壊し: 売却を前提とした取り壊し(滅失登記)が必要です。解体業者選定や手続きをサポートします。滅失登記については関連記事で解説しております。
- 改修・再生: 売却ではなく、賃貸や活用を検討する場合、空き家再生診断士として、補助金情報の提供や、活用プランの提案が可能です。松山市の空き家補助金制度を調べ、最適な再生方法をご提案します。
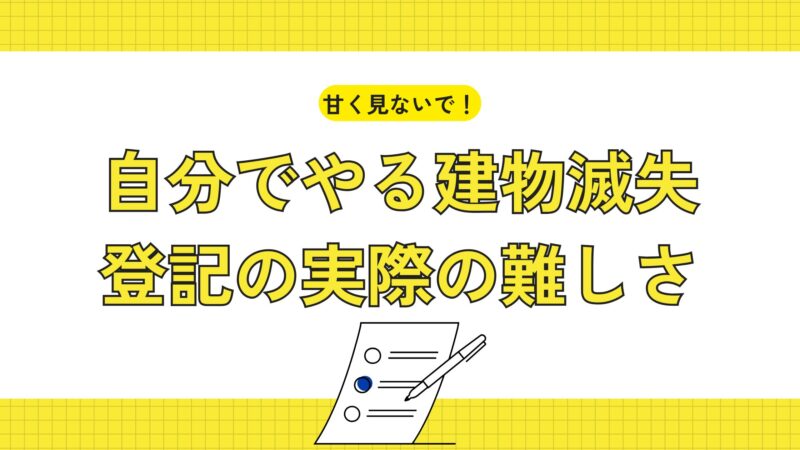
空き家特例と老人ホームの関係によくある疑問Q&A
空き家を相続した後の流れや配偶者の扱いは?
Q: 亡くなった父が老人ホームに入所し、母は既に亡くなっています。特例は使えますか?
A: はい、特例適用が可能です。ただし、特例の要件として、被相続人が老人ホーム等に入所する直前まで、その家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことが必須です。また、老人ホームに入所した時から相続開始の直前まで、老人ホームが主たる居住の場所であることも要件となります。
特例を受けられない場合の主な理由と対策
Q: どんな場合に特例を受けられないことが多いですか?
A: 主な理由は以下の通りです。
- 居住者要件の不備: 老人ホーム入所直前に、被相続人以外(配偶者を除く親族等)が同居していた。
- 施設が要件を満たしていない: 入所した施設が国税庁が定める「特定施設」に該当しない、または要介護/要支援認定を受けていない。
- 空き家期間中の利用制限違反: 空き家となっている間に、家屋を第三者に貸したり、事業に使ったりした期間がある。
- 売却期限切れ: 相続開始から3年10ヶ月以内に売却・申告を完了できなかった。
対策: まずは施設の入所証明書と当時の住民票、要介護認定の記録を確認することが最優先です。適用が難しい場合は、他の税制優遇措置(例:長期譲渡所得の軽減税率など)を検討します。
よくあるトラブル事例と実際の相談対応
Q: 実際に松山市内で多いトラブルは何ですか?
A:実際のトラブル事例
- トラブル事例: 「親が亡くなる数ヶ月前に、介護のため親族が同居したため、特例の要件である『単身居住』が崩れてしまった」というケースや、「有料老人ホームに入所したが、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設だった」というケースです。
- 村上事務所の対応: 居住実態や親族の同居理由を丁寧にヒアリングし、特例適用が難しい場合は、適用範囲内で最大限の対策を提案します。また、相続人同士の売却合意形成に関する行政書士としてのサポートも行います。
まとめ|家族を守る空き家対策と老人ホーム選びのポイント
空き家特例の適用は、ご家族の資産を守り、未来への安心を築く上で非常に重要な手続きです。
特に、老人ホームへの入所というデリケートな背景が絡む場合、行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の複合的な視点が必要不可欠です。
松山市で空き家に関する不安や疑問をお持ちなら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。複雑な手続きをワンストップで解決し、ご家族の安心を守るお手伝いをいたします。



