
2025年建築基準法改正!リフォームプランに必要な確認申請とは
「2025年4月から、建築基準法が改正されるらしい」
「リフォームを考えているけれど、何か影響があるのだろうか?」
「空き家になった実家をどうにかしたいが、法律が変わると何が変わるのか?」
このようなご不安をお持ちではありませんか。2025年に4月に施行された建築基準法改正は、戸建て住宅のリフォームや空き家の活用を検討されている多くの方にとって、見過ごせない大きな変化をもたらします。
特に、これまで確認申請が不要とされてきた小規模な住宅のリフォームにおいても、手続きが必須になるケースが増えるため、計画の費用や工期に大きな影響が予想されます。
この記事では、改正法の背景から、リフォーム計画に不可欠となる確認申請の基礎知識、そして松山市にお住まいの方が知っておくべき具体的なポイントまで、専門家の視点から包括的に解説します。
この記事が、読者の皆様が安心してリフォームや空き家活用を進めるための一助となれば幸いです。
2025年建築基準法改正の概要
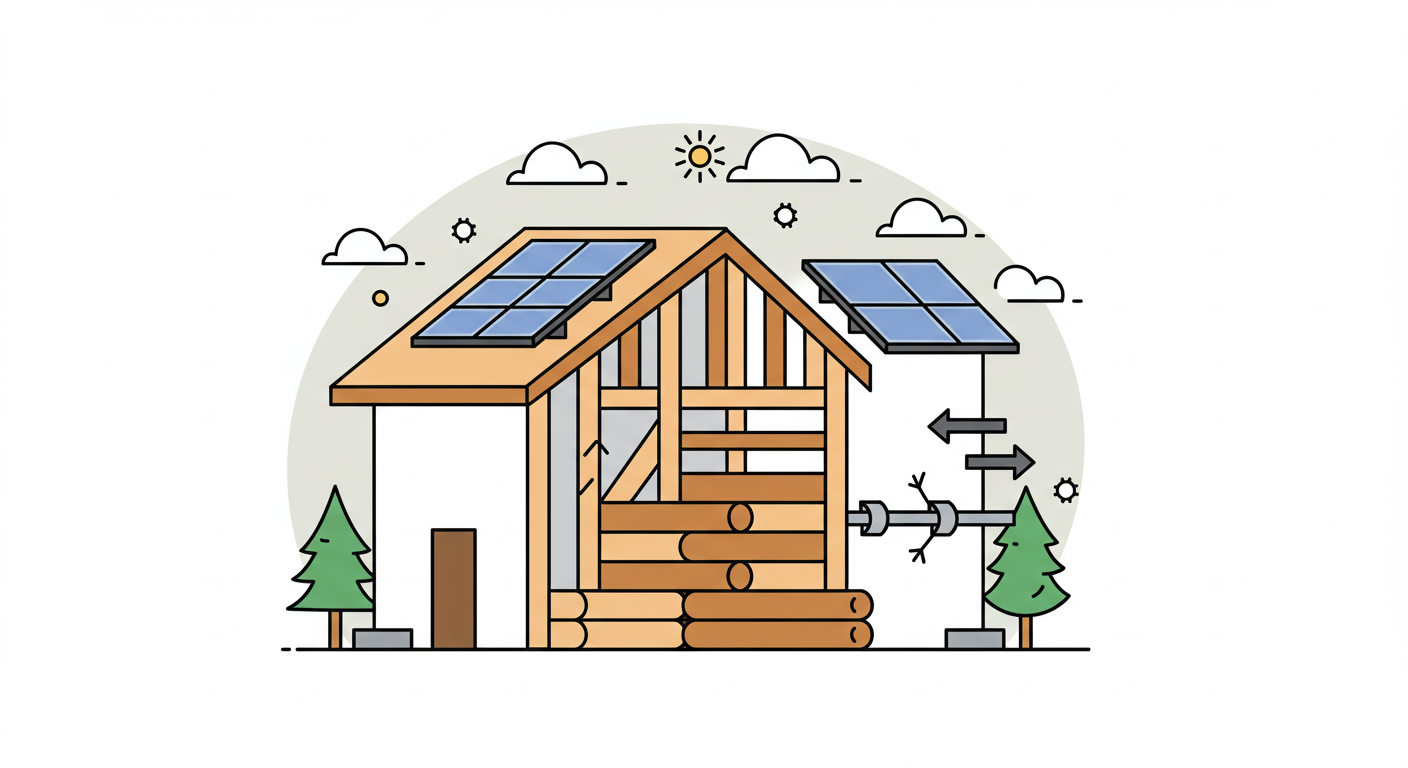
建築基準法改正の背景と目的
2025年4月に施行された建築基準法改正は、単なる規制強化ではなく、日本が直面する複数の社会課題に対応することを目的としています。
国土交通省の資料によると、その主な背景は以下の3つに集約されます。
第一に、省エネ対策の強化です。建物の建設および使用における消費エネルギーは、全産業の約30%を占めており、温室効果ガス削減目標を達成するためには、建築分野での取り組みが不可欠です。
高断熱・高気密な住宅を増やし、冷暖房にかかるエネルギー消費を抑えることが、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた重要な一歩と位置づけられています。
第二に、木材の利用促進です。建築分野は国内木材需要の40%を占めており、木材利用をさらに促進することは、森林の活性化と炭素吸収量の増加に繋がると期待されています。
これまで中・大規模建築における木造建築を妨げていた防火規定や構造計算の要件を見直すことで、木の温かみや魅力を活かした建物の普及を目指しています。
第三に、建築物の安全性向上です。日本は地震の多い国であり、過去の震災で古い建物が倒壊する被害が多数報告されています。
特に、これまでの制度では一部の小規模建築物に対して構造審査が省略されており、設計者や施工業者に安全性の判断が一任されていました。
今回の改正では、これらの審査を厳格化することで、建物の安全性を客観的に担保し、国民が安心して暮らせる住環境を整備することを目指しています。
国土交通省の新しい基準とは
今回の改正で注目すべきは、以下の6つの主要な変更点です 。
- 4号特例の対象範囲が縮小する: これまで建築確認申請の一部審査が省略されていた小規模建築物(4号建築物)の範囲が見直されます。これが戸建て住宅のリフォームに最も大きな影響を与える点です。
- 省エネ基準への適合が必須になる: 新築建築物は原則すべて、2025年4月以降に着工する場合、省エネ基準への適合が義務化されます。
- 構造計算が簡略化される: 3階以下かつ高さ16m以下の木造建築物について、簡易な構造計算で建築できる範囲が拡大されます。
- 大規模木造建築物の防火規定が緩和される: 大規模な木造建築物の構造部材の木材を露出させる仕上げが可能になります。
- 中層木造建築物の耐火性能基準が緩和される: 5〜9階建ての木造建築物の耐火性能基準が、120分から90分に緩和されます。
- 既存不適格建築物における現行基準の一部が免除になる: 既存の建物が現在の法律に適合しない場合でも、増築時などに現行基準の遡及適用が合理化されます。
2025年問題の影響と重要性
2025年の法改正が一般の住宅所有者や空き家所有者に与える最も重要な影響は、「4号特例の縮小」と「省エネ基準の義務化」です。
特に、「4号特例」とは、一般的な木造2階建て住宅(いわゆる4号建築物)に適用されていた構造審査の緩和措置であり、これが縮小されることで、多くのリフォームや増築で建築確認申請が必須になります。
この法改正は、単に手続きが複雑になるという表面的な問題に留まりません。省エネ基準への適合が義務化されると、建物の断熱性能を高めるために高性能な断熱材やサッシを使用することになり、その結果として建物の重量が増加します。
建物の重量が増えれば、地震に対する構造安全性を厳密に検証する必要が生じます。
つまり、今回の改正は、省エネ化による建物の重量増と、それに伴う構造安全性の確保という、二つの課題を同時に解決するために設計されていると言えます。
これまで省略可能だった構造審査を必須とすることで、新たな省エネ技術を導入した住宅の安全性を確実に担保しようとしているのです。
この複雑な法的背景を理解することは、今後のリフォーム計画を立てる上で非常に重要となります。
リフォーム計画における確認申請の基本

確認申請とは?必要な理由
リフォームを考える上で、最初に理解すべきは「建築確認申請」です。
建築確認申請とは、新築・増築・改築や大規模な修繕・模様替えを行う際に、その建築計画が建築基準法や関連法令に適合しているかを、行政や指定確認検査機関に審査してもらう手続きです。
この申請が重要な理由は、第一に建物の安全性と適法性を確保するためです。建築基準法は、人命の安全を守るために建物の構造や材料、防火性能などの基準を定めています。
申請を通じて専門的なチェックを受けることで、リフォーム後の建物が地震や火災などの災害に耐えうる安全性を備えていることが公的に証明されます。
第二に、将来的なトラブルを避けるためです。確認申請を行わずに違法な工事を進めた場合、行政から工事の中止を命じられるだけでなく、その建物は「違法建築物」として扱われ、売却や担保設定が困難になるなど、将来的な資産価値を損なうリスクがあります。
建築確認申請とその流れ
建築確認申請の手続きは、以下のステップで進められます。
- 事前相談: 計画段階で、行政または専門家(建築士や設計事務所)に相談し、法的な要件や手続きの進め方を確認します。この段階での相談が、後のスムーズな進行を左右します。
- 設計図書の作成: 建築士が、法規に適合した詳細な設計図面や書類を作成します。2025年改正後は、多くのケースで構造計算書や省エネ関連の図書が新たに必要となります。
- 確認申請書の提出: 作成した書類一式を、特定行政庁(自治体)または指定確認検査機関に提出します。
- 審査: 提出された書類が建築基準法に適合しているか審査が行われます。書類に不備がある場合は、指摘を受けて修正が必要です。
- 確認済証の交付: 審査に合格すると、「建築確認済証」が交付され、初めて工事に着手することができます。
- 工事着手と中間検査: 工事の途中で、必要に応じて中間検査が行われます。
- 完了検査と検査済証の交付: 工事が完了したら、「完了検査申請」を行い、建物が設計図面どおりに施工されたかを確認してもらいます。合格すれば「検査済証」が交付され、リフォームが完了となります。
確認申請が不要なケースについて
リフォーム内容によっては、建築確認申請が不要となる場合があります 。
- 小規模な増築: 都市計画区域外で、増築部分の床面積が10㎡以内の場合。ただし、防火地域や準防火地域では、1㎡の増築でも申請が必要です。
- 大規模な修繕・模様替えに該当しない工事: 壁紙の張り替え、床材の部分的な交換、外壁や屋根の塗装など、主要構造部(柱、梁、壁、床、屋根など)に影響を与えない軽微な工事。
ここで注意すべきは、リフォームにおける「大規模な修繕」や「模様替え」という言葉の法的な定義です。これは建物の主要構造部(柱、梁、壁、床、屋根、階段など)の過半を修繕・模様替えする工事を指します。
例えば、単なるフローリングの張り替えは通常不要ですが、下地から解体して床面積の半分以上を張り替える場合は申請が必要になる場合があります。
このように、一般的な感覚と法律上の定義には乖離があるため、安易な自己判断は避け、専門家への相談が不可欠となります。
2025年改正によるリフォームの影響

改正内容と建築基準法違反のリスク
2025年4月の法改正は、戸建て住宅のリフォームに大きな影響を与えます。改正後、従来の4号建築物は廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されます。
このうち、一般的な木造2階建て住宅は「新2号建築物」に分類され、これまで省略されていた構造関係規定や防火避難規定の審査が必須となります。
これにより、大規模なリフォーム、特にスケルトンリフォームや増築、主要構造部に手を加える工事では、建築確認申請が義務付けられることになります。
もし申請を怠った場合、工事途中で行政の指導が入り、工事が中断するリスクや、違法建築物となるリスクを抱えることになります。違法建築物は、将来的な売却や建て替えが困難になるだけでなく、万が一の災害時に十分な保険が適用されない可能性も否定できません。
耐震性と省エネ基準の厳格化
改正法では、耐震性と省エネ性能の両方が厳格に審査されます。これまでの4号特例では、建築士の判断に任されていた構造安全性について、行政が直接チェックすることで、より一貫した耐震性の高い住宅が実現しやすくなります。
また、省エネ基準の適合義務化は、リフォーム後の建物の断熱性能を大きく向上させます。これにより、冷暖房効率が大幅に改善し、光熱費の節約に繋がります。
しかし、高性能な断熱材やサッシ、太陽光パネルなどを導入することで建物自体の重量が増加します。この重量増は、建物の構造に負担をかけるため、改正法で必須化された構造計算による厳密な安全性の検証が必要となるのです。
特例の適用と影響を受ける物件
今回の改正は、新築だけでなく、既存の建物にも影響を及ぼします。特に「既存不適格建築物」(建築時には合法だったが、その後の法改正で現在の基準に適合しなくなった建物)や、「再建築不可物件」(現行法規では再建築ができない建物)を所有している方は注意が必要です。


法改正によって、これらの物件に対する一部の現行基準が免除される特例が追加されました。これは、既存建物の有効活用を促すための措置です。
しかし、大規模なリフォームを行う際には、依然として建築確認申請や現行基準への適合が求められるため、計画にはより一層慎重な検討が不可欠となります。
専門家による事前診断と、法令に基づいた適切な計画が、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。
リフォームにおける4号建築物の注意点
4号建築物とは?その特性
「4号建築物」とは、建築基準法上で定義されていた小規模建築物の区分であり、多くの一般的な戸建て住宅がこれに該当します。
具体的には、木造2階建て以下で延べ面積500㎡以下、かつ高さ13m以下、軒高9m以下の建物が該当します。これまでは、建築確認申請の際に構造や防火に関する一部の審査が省略される「4号特例」が適用されていました。
2025年4月の法改正により、この4号建築物という区分は廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されます。
- 新2号建築物: 木造2階建てまたは延べ面積200㎡超の木造平屋建て。
- 新3号建築物: 延べ面積200㎡以下の木造平屋建て。
この変更により、これまで4号特例の恩恵を受けていた「木造2階建て住宅」はすべて「新2号建築物」となり、構造関係の審査省略制度の対象外となります。一方、「新3号建築物」は引き続き審査省略制度が適用されます。
確認申請での特性評価
改正後、新2号建築物のリフォームや増築では、構造や省エネ関連の審査が必須となります。特に重要なのが、構造の安全性を証明する「構造計算書」の提出義務化です。
これまでは、壁量計算など簡易な手法で構造の安全性が確認されていましたが、今回の改正では、より厳密な構造計算(許容応力度計算)が必要となるケースが増えます。
これは、耐震性向上のためだけでなく、省エネ化によって増加する建物の重量に対応するための措置でもあります。
ケーススタディ:4号建築物のリノベーション
典型的な4号建築物である木造2階建て住宅のリノベーションでは、どのような工事が建築確認申請の対象となるのでしょうか。以下に具体的な例を挙げます。
確認申請が必要となるリフォーム工事の具体例
| 建築確認申請が必要となる工事 | 建築確認申請が不要となる工事 |
| 増築工事(防火・準防火地域外で10㎡超、または地域内で1㎡超) | 増築を伴わない内装工事(壁紙・フローリングの部分的な張り替えなど) |
| 構造部分の過半にわたる大規模な修繕・模様替え | 外壁や屋根の塗装・部分的な補修 |
| スケルトンリフォームなど、構造躯体まで手を加える工事 | 既存の窓枠を変えずにサッシやガラスのみを交換する工事 |
| 外壁の全面的な張り替え(下地まで解体する場合) | 間取り変更(主要構造部に影響しない場合) |
| 階段の過半にわたる交換・掛け替え | キッチン、浴室、トイレなどの水回り設備の交換 |
| 耐震補強を目的とした柱・梁の交換や増設 | 電気設備の交換・更新 |
リフォーム計画に必要な書類と手続き
必須の書類一覧
建築確認申請には、多岐にわたる書類が必要です。2025年改正後は、特に新2号建築物において提出書類が増加する見込みです。
- 確認申請書: 正式な申請様式
- 建築計画概要書: 建物の計画概要をまとめた書類
- 配置図、平面図、立面図、断面図: 建物の位置や各部の詳細を示す図面
- 構造計算書: 構造安全性を証明する計算書類。改正後、新2号建築物で新たに提出が求められます。
- 建築工事届: 工事の概要を届け出る書類
- 省エネ関連の図書: 省エネ基準への適合性を示す書類。こちらも改正で提出が必須となります。
- 委任状: 専門家が代理で申請を行う場合に必要
これらの書類を不備なく作成・提出するためには、建築や法律の専門知識が不可欠です。
申請手続きのステップバイステップ
建築確認申請から完了までの流れを以下のフローチャートで示します。
申請にかかる費用の見積もり
確認申請にかかる費用は、主に行政手数料と専門家への依頼費用に分けられます。
- 行政手数料: 申請先の自治体や建物の規模(床面積)によって異なり、一般的な住宅であれば数万円程します。
- 専門家への依頼費用: 建築士による設計や図面作成、行政書士による申請代行にかかる費用です。これは工事内容や建物の規模によって大きく異なりますが、数十万円かかるケースが一般的です。
これらの費用は、リフォーム費用全体のコストアップ要因となりますが、専門家に依頼することで、複雑な手続きの煩雑さから解放され、手続きの遅延や違法建築となるリスクを回避することができます。
行政書士は、建築士が作成した図面を基に行政手続きを代理することが法的に認められています。
リフォーム成功のための業者選び

信頼できる業者の選定基準
今回の法改正後、リフォームを成功させるためには、業者選びがこれまで以上に重要になります。特に以下の点を基準に選定することをお勧めします 。
- 建築確認申請の実績: 改正後の新しい基準に基づいた確認申請の経験が豊富であるか。
- 建築士の在籍: 法律の専門知識だけでなく、建築の専門家である建築士が社内に在籍しているか、または密接に連携しているか。
- ワンストップサービスの提供: 行政手続き、不動産取引、建物診断など、複数の専門家と連携して総合的なサービスを提供できる体制が整っているか。
リフォーム業者に求める技術力
改正法では、耐震性と省エネ性能の向上が求められます。そのため、リフォーム業者には以下の技術力が不可欠です。
- 耐震改修の実績: 特に旧耐震基準(1981年以前)で建てられた建物の耐震診断や耐震補強工事に精通しているか。
- 省エネリフォームの知識: 高性能な断熱材や窓の導入、省エネ設備に関する知識を持ち、補助金制度の活用までサポートしてくれるか。
実績と経験が重要な理由
法改正により手続きが増えることで、リフォーム費用の増加や工期の長期化が避けられないと予想されます。経験豊富な業者は、これらのリスクを事前に予測し、適切なスケジュールと予算を組むことで、予期せぬトラブルを防ぎます。
また、今回の改正基準に適合したリフォームは、建物の安全性向上だけでなく、将来の売却時における資産価値の維持・向上にも繋がります。
宅地建物取引士の資格を持つ専門家と連携することで、リフォーム計画を立てる段階から、不動産としての将来性を見据えたアドバイスを受けることができます。
今後のリフォーム市場への影響
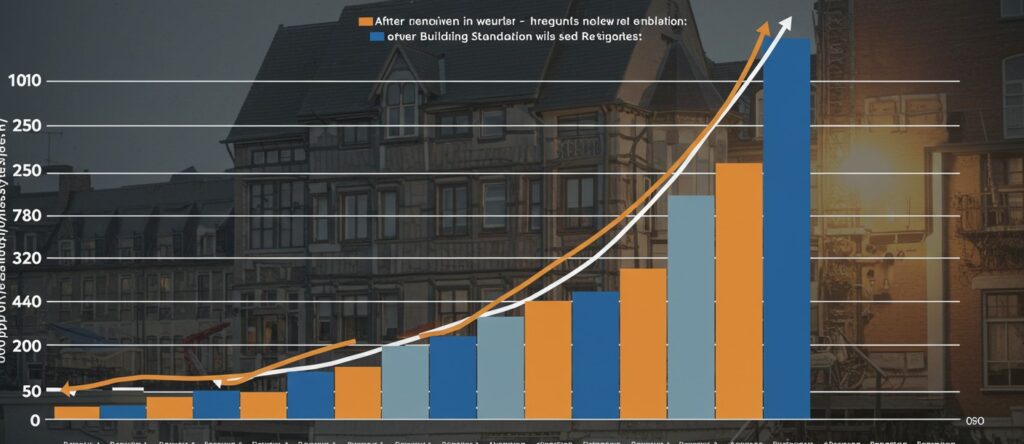
法改正後の市場動向予測
2025年の法改正は、リフォーム市場全体の質的転換を促すと予測されます。確認申請の手続きが必須となることで、低価格で簡素なリフォームの選択肢は減り、その分、建物の安全性や性能を高める高付加価値なリフォームが主流となると考えられます。
また、申請手続きや書類作成のコストは、工事規模が小さくても一定程度発生します。このため、一度の申請で最大限の改修を行う「フルリフォーム」や「スケルトンリフォーム」が、より費用対効果の高い選択肢として注目される可能性があります。
業者に求められる適応力
これまでのリフォーム業者の中には、4号特例を活用して確認申請を避け、低コスト・短工期を売りにしていた業者も少なくありませんでした。しかし、改正後はそのような手法が困難となるため、多くの業者が業務内容や体制の変革を迫られます。
具体的には、社内に建築士を雇用するか、外部の専門家と連携する体制を構築することが必須となります。こうした変化に対応できない業者は、市場から淘汰される可能性もあります。
トレンドとしてのフルリフォームの可能性
今回の法改正は、フルリフォームを検討する良い機会と捉えることができます。確認申請の義務化によって、耐震や省エネの基準をクリアすることが不可欠となるため、どうせコストと手間をかけるなら、建物の性能を飛躍的に向上させるフルリフォームを選択する方が、長期的な視点で見ると賢明な投資と言えるかもしれません。
フルリフォームによって、旧耐震基準の建物を現在の基準に適合させ、光熱費を大幅に削減し、間取りやデザインも自分好みに一新できます。これらの要素は、将来的に建物の資産価値を大きく高めることにも繋がります。
安全で快適な住空間のために
法改正後の住まいの安全性
2025年の建築基準法改正は、住宅所有者にとって一見すると負担増のように感じられるかもしれません。しかし、その根底にあるのは、私たち一人ひとりの暮らしの安全性を高めるという明確な目的です。
手続きの厳格化は、建物の耐震性や防火性、そして省エネ性能を確実に向上させ、災害に強く、家計にも優しい住まいを実現するためのものです。
今回の改正を機に、ご自宅や空き家のリフォームを検討することは、単なる住環境の改善に留まらず、将来の安心と資産価値を守るための積極的な行動と言えます。
改修工事による暮らしの質向上
リフォームは、住まいの性能を向上させるだけでなく、日々の暮らしの質を大きく高めることができます。老朽化した設備を刷新し、断熱性能を高めることで、一年中快適な温度で過ごせるようになります。
また、空き家になっていた実家をリフォームして再活用することは、所有者様の生活の負担を軽減するだけでなく、地域の空き家問題解決にも貢献する、価値ある選択肢です。
2025年改正後のリフォームのポイント
2025年の建築基準法改正は、リフォームを検討する上で重要な転換期となります。特に、木造2階建て住宅のリフォームを計画している場合、これまで不要だった建築確認申請が必須になる可能性が高くなります。
これにより、費用や工期が増加する一方で、建物の安全性や省エネ性能、将来的な資産価値が向上するという大きなメリットが得られます。
この複雑な法律の変更と手続きをスムーズに進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。当事務所は、宅地建物取引士として不動産市場の動向を見据えたリフォームプランを、認定空き家再生診断士として空き家の物理的な状態と活用方法を診断し、そして行政書士として確認申請や補助金申請といった煩雑な手続きを代行いたします。
特に、松山市では老朽化した空き家の解体費用を補助する「松山市老朽危険空家除却事業」や、移住者が空き家を改修する際に利用できる「移住者住宅改修支援事業」など、独自の支援制度が用意されています。
これらの制度は、申請要件や手続きが複雑であり、専門家の助言がなければ見過ごしてしまうことも少なくありません。当事務所は、松山市の空き家問題に深く関わっており、これらの行政手続きについても包括的なサポートが可能です。
複雑な法律と多岐にわたる専門知識が必要となる今だからこそ、法務、不動産、建物の知見を兼ね備えた当事務所の「ワンストップサービス」をぜひご活用ください。リフォームや空き家活用に関するご不安がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。



