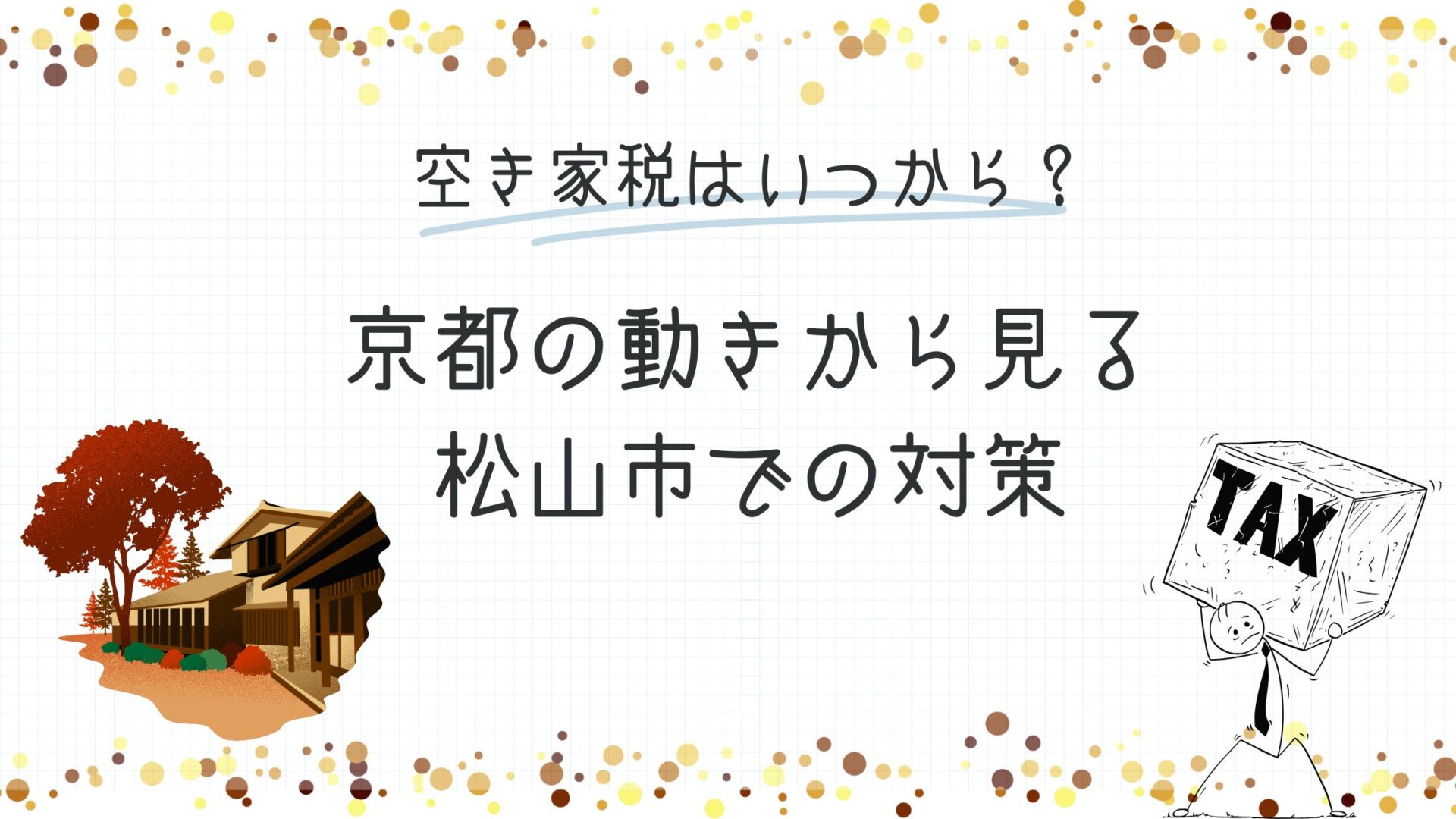
空き家税はいつから?京都の動きから見る松山市での対策
「実家が空き家になって困っている」
「将来、実家をどうしたらいいか不安」
「まさか空き家にも税金がかかるなんて…」
そんなお悩みをお抱えではありませんか?日本全国で深刻化する空き家問題は、もはや他人事ではありません。

空き家が放置されることは、地域の景観を損ねるだけでなく、不法侵入や火災のリスクを高め、防犯上の懸念を引き起こします。さらに、地域全体の不動産価値の低下を招くなど、多岐にわたる悪影響が指摘されています。
こうした状況に対し、京都市は全国に先駆けて「非居住住宅利活用促進税」(通称:空き家税)の導入を進めています。この動きは、単なる地方税制の変更に留まらず、その効果や課題が検証された後、松山市を含む全国の自治体に波及する可能性を秘めています。
京都市が抱える住宅不足や若年層流出といった課題は、形こそ違えど松山市にも通じる点があるからです。
この新しい税制は、単なる増税ではありません。空き家を「負の資産」から「地域に貢献する資産」に変えるための、所有者への強力な問いかけなのです。
本記事では、この京都市の空き家税の全容を詳細に解説します。そして、松山市で空き家専門の行政書士として活動する当事務所が、空き家所有者の皆様に具体的な対策と最適な選択肢を提供することを目指しています。
空き家問題は「個人の問題」から「社会全体の問題」へと認識が変化しており、所有者には「社会的ストック」としての空き家を適切に管理する責任が強く求められています。
京都市初の空き家税とは?その基本を解説
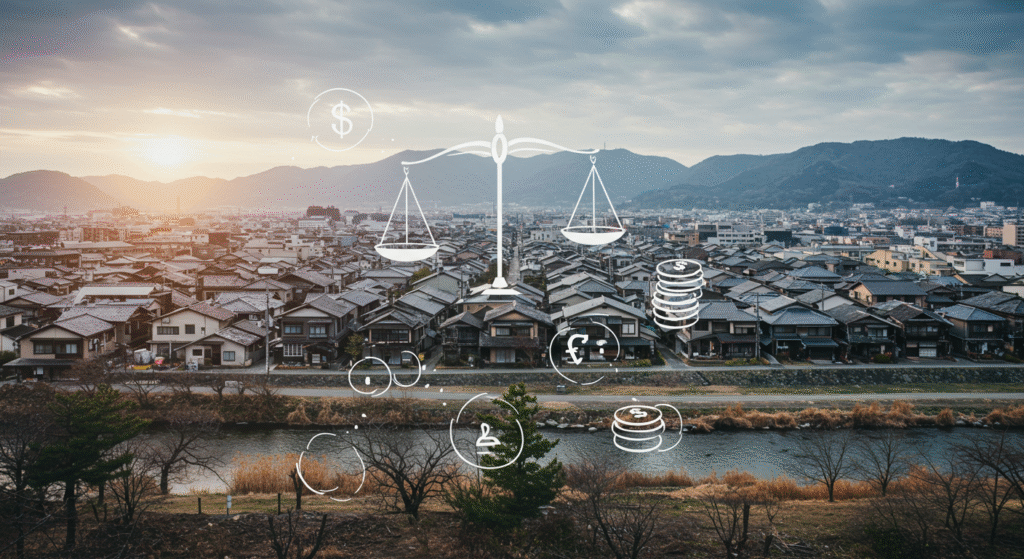
空き家税ってなに?京都市「非居住住宅利活用促進税」の基本
京都市が導入を進める「空き家税」の正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といいます。この税は、一定期間以上使われていない住宅、つまり「非居住住宅」に対して課される新しい税金です。その目的は、空き家が放置されることで生じる景観の悪化、防犯上の問題、火災リスクといった社会課題を解決し、空き家の有効活用や適切な管理を促すことです。
京都市がこの税を導入する背景には、市内の住宅不足を解消し、特に若い世代や子育て世代の転入を増やしたいという明確な意図があります。使われていない空き家を市場に流通させることで、住宅供給を増やし、人口減少に歯止めをかけたいと考えているのです。
この空き家税は、すでにある固定資産税に上乗せされる形で課税されるため、空き家所有者にとっては新たな税負担となる可能性があります。
なぜ今、京都市が空き家税を導入するの?その背景
京都市が空き家税の導入に踏み切った背景には、いくつかの深刻な問題が複合的に絡み合っています。
- 空き家による地域への悪影響: 空き家は、単に見た目が悪いだけでなく、不法侵入や放火などの犯罪リスクを高め、地域の安全を脅かします。また、適切に管理されていない空き家は、周辺の不動産価値を下げる原因にもなります。
- 京都市特有の住宅事情: 近年、京都市では土地や住宅の価格が非常に高騰しています。このため、若い世代や子育て世代が京都市内での居住を諦め、近隣の市町村へ転出してしまうという問題に直面していました。
- 社会的ストックとしての活用: 京都市は、空き家を単なる個人の資産ではなく、「次の居住者に住み継がれるべき社会全体の大切な財産(社会的ストック)」と捉えています。この空き家を流通・活用させることで、若い世代の住宅需要に応えたいと考えています。
この税制は、単に税収を増やすことが目的ではありません。空き家を放置することで地域に悪影響を与えるのを抑え、売却や活用を促すという「政策誘導」の側面が非常に強いのです。
所有者が何となく空き家を放置している状況を変え、具体的な行動を促すための強力なきっかけとなることが期待されています。
空き家税で何が変わる?目的と影響を解説
京都市の空き家税の主な目的は、深刻な空き家問題を食い止め、地域の景観や安全性を守ることです。長期間使われていない空き家に税金をかけることで、所有者に対し、空き家を適切に管理したり、活用したり、売却したりするよう促します。
この税の導入によって期待される具体的な影響は多岐にわたります。
- 住宅不足の解消と不動産価格の抑制: 空き家が市場に流通することで、京都市内の住宅不足が解消され、不動産価格の高騰を抑えることにつながる可能性があります。
- 人口流入と地域活性化: 住宅が手に入りやすくなることで、若い世代や子育て世代が京都市に移住しやすくなり、地域の活性化や人口減少に歯止めがかかる効果が期待されます。
- 税収の使い道: 税収は年間約9.5億円と見込まれていますが、京都市は税収自体が目的ではなく、空き家対策や移住促進対策の財源として活用し、最終的に空き家が減って税収が減っていくことが理想だと表明しています。
しかし、この税制には課題もあります。空き家の所有者には、希望する価格で売却が難しい、解体費用がないなど、様々な個別の事情があるからです。
固定資産評価額が低い家屋や、京町家のような歴史的価値のある建物は非課税とする方針が示されていますが、制度の公平性や透明性をいかに確保するかが重要な課題です。
また、空き家の流通促進だけでは若い世代の呼び込みに直結しないため、移住支援策など、税制と連携した多角的な施策も重要だと指摘されています。
空き家税の具体的な内容と適用
空き家税はいつから?課税開始時期は2029年度以降!
京都市の「非居住住宅利活用促進税」は、2022年3月25日に京都市議会で条例案が可決され、2023年3月24日には国の同意を得て、正式に導入が決まりました。
この税の課税開始時期は、令和11年度(2029年度)以降と予定されています。当初は2026年導入という報道もありましたが、最新情報では令和11年度からの課税開始が京都市から公式に発表されています。
課税対象になると思われる所有者の方には、課税開始前に個別に通知が送られる予定です。
あなたの空き家は対象?課税される空き家の条件と免除ケース
京都市の空き家税を納める義務があるのは、京都市の市街化区域内にある「非居住住宅」の所有者です。ここでいう「非居住住宅」とは、「その場所に住所を持つ人がいない住宅」を指します。
一般的な空き家はもちろん、別荘やセカンドハウス、さらには入居者がいない賃貸物件も含まれます。住民票があるかどうかに関わらず、実際に生活の本拠として使われているかどうかが判断基準となります。
一方で、以下の条件に当てはまる非居住住宅は、課税が免除されたり、税額が減らされたり、徴収が猶予されたりする場合があります。
- 免税点以下の物件: 家屋の固定資産評価額が20万円未満の物件は課税対象外です。さらに、制度導入から最初の5年間は、この免税点が100万円未満に引き上げられます。
- 事業用または事業予定の物件
- 賃貸アパートや店舗など、事業に使われている非居住住宅は課税が免除されます。
- その年の1月1日時点で、1年以内に事業で使うことが具体的に予定されている物件も免除対象です。ただし、親族や知人のみへの貸付や、わざと不利な条件で募集している場合は免除対象外となるので注意が必要です。
- 賃貸または売却の募集を始めてから1年以内の物件: 空き家を賃貸に出す、または売却するために募集を始めてから1年以内の物件は免除されます。
- 歴史的価値のある建造物: 京町家など、景観法に基づき指定された歴史的価値のある建物は課税免除の対象です。
- すでに固定資産税が非課税・免除されている物件: すでに固定資産税の対象外となっている物件も、空き家税の課税対象外です。
- 一時的に住んでいない物件: 転勤、海外赴任(5年間)、入院、介護施設への入所、DV被害による避難、親族の介護、増改築工事などの理由で一時的に不在となっている場合は、申請により税額が減らされる可能性があります。
- 相続物件に対する徴収猶予制度: 空き家の所有者が亡くなった場合や、住んでいた人が亡くなって空き家になった場合など、相続に関連する特定の事情がある場合、所有者の申告により最大3年間、税金の徴収が猶予されます。この猶予期間中に空き家が活用された場合、猶予された税金は支払う必要がありません。
これらの条件を正確に理解し、ご自身の空き家が課税対象になるのか、それとも免除・減免の対象になるのかを確認することがとても重要です。
空き家税はいくら?計算方法と税額シミュレーションの考え方
京都市の空き家税は、「家屋価値割」と「立地床面積割」という2つの要素を合わせて税額が計算されます。どちらの計算にも、固定資産税評価額が基準となります。
家屋価値割
- 計算式:家屋の固定資産税評価額 × 0.7%
これは、建物そのものの価値に基づいて課される税額です。
立地床面積割
- 計算式:敷地の土地に係る1平方メートルあたり固定資産評価額 × その非居住住宅の延べ床面積 × 税率
この税率は、家屋の固定資産評価額によって3段階に分かれます。
| 家屋の固定資産評価額 | 立地床面積割の税率 |
| 700万円未満 | 0.15% |
| 700万円以上900万円未満 | 0.3% |
| 900万円以上 | 0.6% |
立地床面積割は、土地の評価額と建物の床面積を考慮し、空き家の立地条件と規模に応じた負担を求めるものです。
これら二つの税額を合計したものが、1年間で課される空き家税の総額となります。京都市の説明では、平均的にはすでにお支払いになっている固定資産税額(土地+家屋)の約半額が上乗せされるイメージだといわれています。
【シミュレーション例】
例えば、以下のような京都市内の空き家があったとします。
- 家屋の固定資産評価額:800万円
- 土地の1平方メートルあたり固定資産評価額:10万円
- 延べ床面積:100平方メートル
- 家屋価値割: 800万円 × 0.7% = 5万6,000円
- 立地床面積割: 家屋の評価額が700万円以上900万円未満なので税率は0.3% 10万円 × 100平方メートル × 0.3% = 3万円
この場合、年間の空き家税額は、5万6,000円 + 3万円 = 8万6,000円となります。
ご自身の空き家が課税対象になるか、また税額がどれくらいになるかについては、京都市のホームページで提供されている税額シミュレーションツール(XLSX形式のファイル)を利用して試算できます。
ただし、このシミュレーションはあくまで参考値であり、確定額ではない点にご注意ください。より正確な情報や個別の相談には、専門家への相談が不可欠です。
空き家税と固定資産税の関係
空き家税と固定資産税はどう関係する?知らないと損する「最大6倍」のリスク
京都市の空き家税は、すでにお支払いになっている固定資産税とは別に、追加で課される新しい税金です。したがって、空き家税が導入されても、固定資産税の計算方法や税額が直接的に変わるわけではありません。
しかし、空き家を放置し続けると、結果的に固定資産税の負担が大幅に増える可能性があります。
これは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正と深く関わっています。2023年3月に閣議決定され、同年12月に施行されたこの法改正により、新たに「管理不全空き家」という区分が追加されました。空家法令改正についてはこちらの記事で詳しく書いてます。
これまでは、倒壊の危険があるなどの「特定空き家」だけが行政から注意される対象でしたが、今後は「そこまでひどくはないけれど、放置されている空き家」も正式に行政が介入できる対象となるのです。
もし、あなたの空き家が「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定され、行政からの指導や勧告に従わずに改善が見られない場合、土地に対する「住宅用地の軽減措置」という固定資産税の特例が解除される可能性があります。
この特例が解除されてしまうと、なんと土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。
空き家税に加えてこの固定資産税の増額が重なると、税負担はさらに重くなるため、空き家を放置することは経済的に非常に大きなリスクを伴うことになります。
空き家を賢く管理して固定資産税の増額を回避する!
空き家を適切に管理することは、固定資産税の軽減措置が解除されるリスクを避けるために極めて重要です。
特に、「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されないよう、定期的な手入れや点検が求められます。万が一指定を受けてしまっても、その原因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空き家等の指定を解除し、固定資産税の軽減措置を再び適用させることが可能です。
京都市の空き家税における免除制度は、固定資産税の軽減措置とは異なる、空き家税独自のものです。前述の通り、空き家税には、事業に使われている物件、賃貸や売却の募集を始めてから1年以内の物件、歴史的価値のある建物、評価額が低い物件などが課税免除の対象となります。
また、相続で取得した空き家については、相続開始から3年間、空き家税の徴収猶予が認められる制度があります。この猶予期間中に空き家が活用された場合、猶予された税金は支払う必要がありません。
これは、相続人が空き家の活用や処分を検討するための期間を与える配慮であり、所有者にとっては有効な選択肢をじっくり考える機会となります。空き家税の負担を避けるためには、単に放置するのではなく、これらの免除や猶予の条件に当てはまるよう、積極的に活用したり、売却を検討したりすることが不可欠です。
空き家の利活用と売却の選択肢
空き家バンクの活用方法と知っておきたいメリット
空き家バンクとは、地方自治体などが運営する、空き家情報の登録・紹介システムです。空き家を所有している方と、空き家を利用したい方(移住者、Uターン希望者、事業者など)を結びつけることを目的としています。

空き家バンクを所有者の方が活用するメリットはたくさんあります。
- 幅広い物件を掲載可能: 不動産としての価値が低い、あるいは一般的な不動産会社では仲介や買取を断られるような物件でも、空き家バンクであれば掲載できる可能性があります。
- 費用を抑えられる: 自治体が運営しているため、登録や利用が無料でできる場合が多く、不動産会社を介さずに直接交渉・契約が成立すれば、仲介手数料がかかりません。
- 地域貢献にも: 空き家を「使われていない資産」から「地域活性化に貢献する資産」へと変えることができ、地域貢献にもつながります。
利用希望者側から見ても、空き家バンクは魅力的な選択肢です。通常よりも安く空き家を購入・賃借できる可能性があり、古民家カフェなどの店舗利用や、DIYを前提とした住居としても活用できます。
多くの自治体では、空き家バンクを通じた物件の購入や改修に対して、補助金制度やフラット35の金利優遇措置などを設けており、初期費用を抑えることが可能です。
空き家バンクは、単に物件を紹介するだけでなく、地域課題の解決や移住促進にもつながる取り組みです。自治体によっては、物件の事前調査、リフォーム補助金制度、移住者向けの就農・創業支援制度などを組み合わせ、空き家の「放置→活用」の流れを丁寧に支援しています。
ご自身の空き家の状況を考慮し、売却や賃貸を希望する場合は、まず不動産会社に相談し、それでも買い手が見つからない場合に空き家バンクの利用を検討するという流れがおすすめです。
空き家を売るなら知っておきたい!売却時の注意点と税金
空き家の売却は、空き家税の課税対象から外れる最も直接的な方法の一つです。しかし、売却にはいくつかの注意点と税金がかかります。
売却時にかかる主な税金
空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、以下の税金が課されます。
- 譲渡所得税: 土地や建物を売却して得た利益にかかる税金(所得税、住民税、復興特別所得税の合計)です。
- 計算方法:譲渡所得 = 売却額 - (購入費用 + 売却費用)。購入費用が不明な場合は、売却額の5%として計算できる特例があります。
- 税率:不動産の保有期間によって税率が異なります。
- 短期譲渡所得(保有期間5年以下): 所得税30%、住民税9%、復興特別所得税2.1%
- 長期譲渡所得(保有期間5年超): 所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%
- 保有期間は、親が住んでいた期間も含まれます。
- 印紙税: 不動産売買契約書を作成する際に必要となる税金です。通常、売主と買主がそれぞれ負担します。
売却時の特例と控除
特定の条件を満たす場合、売却益から控除を受けられる特例があります。
- 居住用財産の3,000万円特別控除: 以前に住んでいた家屋を売却する場合、売却益から最大3,000万円が控除されます。適用条件として、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却することなどが挙げられます。
- 相続空き家の3,000万円特別控除: 相続で取得した空き家を売却する場合に適用される特例です。適用条件は多岐にわたりますが、主なものとして、
- 亡くなった方が一人暮らしだったこと。
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること。
- 売却価格が1億円以下であることなどが挙げられます。
- 2024年1月1日以降の譲渡では、家屋を取り壊した場合でも、その翌年の2月15日までに取り壊しが完了していれば特例を受けられるよう要件が緩和されています。
- 10年超所有軽減税率の特例: 長期譲渡所得の税率がさらに低くなる制度で、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に適用されます。
売却時の主な注意点
- 名義変更と相続人全員の同意: 売却できるのは、登記された名義人である所有者だけです。相続した空き家の場合は、相続登記が完了しているかを確認し、複数の相続人がいる場合は相続人全員の同意が必要です。2024年からの相続登記義務化により、この手続きの重要性はさらに増しています。
- 3年以内の売却: 多くの特例制度は、住まなくなった日や相続開始の日から3年以内の売却が条件となっています。節税のためにも、売却を検討するなら早めに動き出すことがおすすめです。
- 解体のタイミング: 空き家を解体して更地として売却する場合、解体費用がかかるだけでなく、建物がなくなると土地に対する固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税金が上がる可能性があります。売却が長引く可能性も考慮し、解体するかどうかは不動産会社と相談しながら慎重に検討すべきです。
- 契約不適合責任: 売却後のトラブルを避けるため、契約不適合責任の期間や措置について契約書で確認することが重要です。買い取り業者への売却であれば、多くの場合、この責任は免除されます。
空き家の売却は、税制優遇をうまく使えば非常に有利に進められますが、複雑な手続きや注意点も多いため、専門家への相談が不可欠です。
参照記事→松山市の空き家を売却する流れを徹底解説!5つの簡単ステップ
空き家税との付き合い方
空き家管理、どうしたらいい?対策のポイント
空き家税の導入や「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正によって、空き家を放置することのリスクはますます高まっています。
税負担の増加や行政からの指導・勧告を避けるためには、適切な空き家管理が欠かせません。管理方法は、所有者自身が行う「自主管理」と、専門業者に頼む「管理サービス」の2つに大きく分けられます。
自主管理のポイント
自主管理を行う場合、定期的に空き家を訪れて作業する必要があります。
- 事前準備
- 貴重品を運び出し、電気・ガス・水道などのライフラインを閉栓しましょう。
- 郵便物の転送手続きを行い、郵便受けは閉じておきます。
- 湿気によるカビを防ぐため、畳を上げたり、凍結防止のため給湯器の水を抜いたりするのも大切です。
- 台風などで飛ばされそうな鉢植えやアンテナなどは撤去しておきましょう。
- 近隣住民へ挨拶を済ませ、「定期的に管理に来る」ことを伝え、不審者と間違われないようにするのもポイントです。
- 定期的な作業
- 換気と通水: 湿気によるカビを防ぐため、タンスや戸棚、窓を開けて換気します。水道が通っている場合は、排水管の悪臭防止のために1分程度水を流しましょう。
- 敷地内外の清掃・確認: 雑草の除去、庭木の剪定、ゴミ拾いは近隣トラブルの防止につながります。外壁や軒裏、塀などにひび割れや腐食がないかも確認しましょう。
- 室内のチェックと清掃: 雨漏りやカビ、害虫の発生がないか、床や天井、壁を点検します。窓や建具の開閉に問題がないかも確認し、建物の傾きなどの異常があれば早めの修繕を検討します。
- 記録: カメラで気になる箇所を撮影し、チェックシートを使って作業の抜けがないか確認することで、時間の経過による変化を把握できます。
- 服装・持ち物: 汚れても良い動きやすい服装を着用し、夏場は長袖・長ズボンで害虫対策を。ゴミ袋、軍手、懐中電灯(電気が止まっている場合)などを用意しましょう。
参照記事→空き家管理の基本!空き家を放置するリスクとチェックリスト
空き家管理サービスの利用
遠方に住んでいる、時間がとれない、体力的に難しいといった理由で自主管理が難しい場合は、専門の管理会社に「空き家管理サービス」を依頼することが有効です。
- サービス内容: 月に1度程度の巡回で、敷地内外の清掃、換気、通水、水漏れチェック、郵便物転送、屋内外の巡回報告書作成などが一般的です。
- メリット: 専門家による適切な管理で物件の老朽化を防ぎ、特定空き家等に指定されるリスクを減らすことができます。
管理を避ける他の方法としては、賃貸物件として貸し出す、リフォームして店舗や事務所として活用する、あるいは相続放棄を検討するといった選択肢もあります。
誰に相談すればいい?専門家への相談窓口と手続き
空き家問題は、不動産、法律、税金、建築など多岐にわたる専門知識が必要なため、適切な専門家への相談が欠かせません。特に、京都市の空き家税のような新しい税制が導入される中では、専門家の助言がより一層重要になります。
松山市の村上行政書士事務所は、行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格を併せ持つため、空き家に関する多角的なサポートが可能です。
- 行政書士の役割: 空き家の管理に関する法的手続きのサポート、管理計画の策定、行政の支援事業を受けるための申請手続き代行を行います。また、地域住民との調整を通じて、空き家を地域資源として活用するためのサポートも提供します。
- 宅地建物取引士の役割: 空き家の売買や賃貸借に関する専門知識を持ち、市場の動向を踏まえた適切な売却・賃貸戦略の提案、契約手続きのサポートを行います。
- 認定空き家再生診断士の役割: 空き家の状況を詳しく診断し、その活用や管理について専門的なアドバイスを行います。具体的には、不動産売却情報の拡散、売却手段の提示、空き家バンクを活用した所有者と利用希望者のマッチング、リフォーム・リノベーションによる再生計画の提案、補助金受給のサポートなど、空き家を地域資源として活性化させるための幅広いアドバイスを提供します。
これらの資格を複合的に持つ専門家は、空き家の購入・活用、相続において生じうる経済的・建築技術的な問題から、法律・行政上の問題まで、複雑に絡み合う様々な要素に対応できる強みがあります。
その他の相談窓口
- 自治体の空き家対策窓口: 多くの自治体で空き家対策の専用窓口が設けられており、補助金制度や特例措置についての情報提供、相談に応じています。
- 税理士: 空き家の売却にかかる譲渡所得税や、相続税など、税金に関する専門的な相談に対応します。
- 司法書士: 相続問題や共有名義の不動産に関するトラブル、登記など、複雑な法律問題の解決をサポートします。
- 不動産コンサルタント: 空き家の活用方法や売却戦略について、専門的な視点からアドバイスを提供します。
- 地域の空き家対策団体・NPO: 無料相談サービスを提供している場合もあり、地域に根ざした実践的なアドバイスが期待できます。
空き家に関する問題は、放置すればするほど税金のリスクや維持費用が増え、解決が難しくなる傾向があります。
そのため、課税通知を受け取った場合や、空き家の管理に困った場合は、できるだけ早めに専門家や相談窓口を利用し、適切な対応策を検討することが重要です。
全国から見る空き家税制度の現状
京都市は全国初!他自治体の空き家対策事例
京都市が導入する「非居住住宅利活用促進税」は、空き家や別荘などの非居住住宅に対して税金をかけるという、全国の自治体で初めての試みです。この点で、京都市の取り組みは非常に先進的であり、その効果や課題は今後、他の自治体における空き家対策のモデルケースとなる可能性があります。
京都市以外の多くの自治体では、空き家問題に対し、税金そのものを課すのではなく、情報提供、補助金、相談体制の強化、連携事業といった多様なアプローチで対策を進めています。
他の自治体における主な空き家対策の事例
- 情報提供と周知: 茨城県桜川市、兵庫県姫路市、福岡県豊前市、大阪府貝塚市、山形県鶴岡市などが、固定資産税の納税通知書に空き家バンクへの登録や適切な管理を促すチラシを同封し、空き家所有者への情報提供を強化しています。
- 連携と専門家活用: 栃木県小山市は工業高等専門学校と連携し、学生による空き家物件の活用調査・提案を行い、空き家バンクサイトの利便性向上につなげています。千葉県香取市は解体支援を目的に、民間企業と協定を結び、解体に関する相談対応を強化。神奈川県湯河原町は地元の団体が空き家バンクの運営を担い、物件登録者と移住希望者の双方に寄り添う対応を行うことで、民間ならではの強みを活かしています。
- 空き家バンクの拡充: 群馬県渋川市は農地と空き家を一緒に売買できる「農地付き空き家バンク」を作り、農業に関心のある移住希望者を呼び込んでいます。
- 管理支援サービス: 埼玉県越谷市、山梨県昭和町では、シルバー人材センターと連携し、空き家の見回りや写真付き報告書作成などの「空き家等見回りサービス」を提供しています。
- 補助金制度: 東京都足立区、墨田区では老朽化した危険な家屋の解体費用に対する助成制度を設けています。岡山市、東京都八王子市、鯖江市では、空き家の改修(リフォーム)費用の一部を補助する制度を実施。東京都奥多摩町では、移住・定住を目的とした住宅の新築、増築、購入に対する補助金や利子補給を行っています。
- 利活用事例: 高山市、中津川市、飛騨市、郡上市(岐阜県)では、空き家を博物館、体験用古民家、宿泊施設、テレワークハウス、コミュニティスペースなど、地域の特性を活かした多様な施設に改修し、地域活性化に貢献しています。
これらの事例は、各自治体が地域の状況やニーズに応じて、空き家問題の解決に向けて様々な工夫を凝らしていることを示しています。京都市の空き家税は、これらの取り組みに加えて、税という強力な手段を用いて政策誘導を行う点で特徴的です。
空き家税の法改正と今後の展望:放置するとリスク大!
空き家問題を取り巻く法制度は、近年大きく変化しています。特に重要なのが、2023年3月に閣議決定され、同年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」です。
主な法改正のポイントと影響
- 「管理不全空き家」の導入: これまでの「特定空き家」(倒壊の危険など、今すぐ危険を及ぼす可能性のある空き家)に加え、新たに「管理不全空き家」という区分が設けられました。これは、「そこまでひどくはないけれど、放置されている空き家」も行政が介入できる対象となることを意味します。
- 固定資産税の優遇解除: 管理不全空き家や特定空き家に指定されたまま改善されない場合、土地に対する「住宅用地の特例」が解除され、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。これは、空き家を放置することに対する経済的なペナルティが大幅に強化されたことを示しています。
- 建築基準法・省エネ法改正(2025年4月施行): 今後、空き家をリフォームして貸したり売ったりする場合でも、建築確認申請や省エネ基準への適合が義務化されます。これにより、小さな住宅の改修や用途変更にも構造計算や設計図面の提出が必要となり、空き家の活用における法的・技術的なハードルが上がります。
今後の展望と課題
これらの法改正は、空き家所有者に対し、より一層の適切な管理や活用、あるいは売却を促す強力なプレッシャーとなります。
- 対策の早期化: 税負担の増加や行政指導のリスクを避けるため、全国的に空き家対策が加速する可能性があります。
- 解体業者不足と費用高騰: 急激な解体需要の増加により、解体業者の不足や解体費用の高騰、さらには悪質な業者による問題が発生する懸念があります。
- 売却市場への影響: 法改正で空き家の売却や流通を直接的に活性化させる方策は盛り込まれていないため、放置された空き家が増加し、売却が難しくなったり、価格が下がったりする可能性も指摘されています。
- 税制優遇の継続: 一方で、空き家を売却する際に活用できる「3,000万円特別控除」は2027年12月31日まで延長されており、売却を検討する所有者にとっては引き続き有利な条件が提供されています。
- 京都市の制度検証: 京都市の空き家税条例は、施行後5年ごとに制度の状況や社会経済情勢の変化を考慮し、見直しを行うこととされています。これは、制度が固定的なものではなく、社会情勢に応じて変わる可能性があることを示唆しています。
総じて、空き家を取り巻く状況は「放置すれば負債になりうる」という段階に急速に変化しています。管理状態が悪いだけで行政からの勧告や税金ペナルティの対象となり、リフォームにも建築法の適合が必要になる一方で、税制優遇をうまく使えば売却は依然として有利な選択肢となり得ます。
空き家税に関するよくある質問(Q&A)
空き家税ってどんな特例があるの?知っておくべきこと
京都市の空き家税には、納税義務者の負担を軽くするための様々な特例や免除規定が設けられています。これらを理解することは、適切な対策を考える上で不可欠です。
主な免除・減免・徴収猶予の特例
- Q. どんな空き家なら税金がかからないの?
- A. 家屋の固定資産評価額が20万円未満の物件は課税対象外です。また、制度導入から最初の5年間は、この免税点が100万円未満に引き上げられます。
- Q. 事業に使っている空き家も対象?
- A. 賃貸アパートや店舗など、事業に使われている非居住住宅は課税が免除されます。また、その年の1月1日時点で、1年以内に事業で使うことが具体的に予定されている場合も免除対象です。
- Q. 売りに出している物件も課税対象?
- A. 空き家を賃貸に出す、または売却するために募集を始めてから1年以内の物件は免税されます。
- Q. 歴史的な建物も課税されるの?
- A. 京町家など、景観法に基づき指定された歴史的価値のある建物は課税免除の対象です。
- Q. 一時的に住んでいないだけなのに?
- A. 転勤、海外赴任(5年間)、入院、介護施設への入所、DV被害による避難、親族の介護、増改築工事などの理由で一時的に不在となっている場合は、申請により税金が減らされる可能性があります。
- Q. 災害で被害を受けた空き家は?
- A. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害または盗難により損失を受けた物件は、減免の対象となります。
- Q. 相続したばかりの空き家はどうなるの?
- A. 空き家の所有者が亡くなった場合や、住んでいた人が亡くなって空き家になった場合、納税義務者の申告により最大3年間、税金の徴収が猶予されます。猶予期間中に活用された場合、猶予された税金は支払う必要がありません。
これらの特例は、空き家所有者の状況に配慮し、適切な対応を促すためのものです。課税通知を受け取った際には、まず内容をしっかり確認し、ご自身の空き家がこれらの特例に当てはまらないかを確認することが重要です。
空き家税を回避する賢い方法
空き家税の課税を回避する最も効果的な方法は、空き家を「非居住住宅」の状態から脱却させ、有効活用することです。具体的な選択肢は以下の通りです。
- 賃貸物件として活用する
- 空き家を賃貸に出すことで、居住者がいる状態となり、空き家税の課税対象外となる可能性があります。
- 賃貸需要を高めるためにリフォームを行うことも有効です。
- 賃貸募集を開始してから1年以内であれば、課税免除の対象となります。
- 自宅または事業所として利用する
- 所有者自身がその空き家を生活の本拠として居住を開始するか、または事業所として利用を開始すれば、空き家税の対象外となります。
- 活用のために改修費用がかかる場合は、自治体の補助金制度を利用できる可能性があります。
- 売却する
- 空き家を売却することで、そもそも税金がかかる対象者から外れます。
- 売却を検討する際は、前述の「相続空き家の3,000万円特別控除」などの税制優遇を最大限に活用できるよう、相続開始から3年以内など、期限を意識した行動が重要です。
- 解体して土地として売却する方法もありますが、解体費用や固定資産税の増額リスクを考慮する必要があります。
- 所有権を放棄・譲渡する
- 一部の自治体では、公共利用を目的とした空き家の寄付を受け付けている場合がありますが、老朽化した建物の受け入れは少ない傾向にあります。
- NPOや地域団体に寄付し、地域活性化のために活用してもらう方法もあります。
- 家族や親族に名義を移すことで課税対象から外れる場合もありますが、贈与税などの追加費用が発生する可能性があるため、専門家への相談が不可欠です。
空き家税の課税通知を受け取った場合や、空き家の管理・活用に困った場合は、早めに自治体の窓口や、不動産コンサルタント、税理士、弁護士、そして松山市の村上行政書士事務所のような専門家へ相談することが重要です。
放置すればするほど問題が複雑化し、解決が難しくなる可能性が高まります。地域の現状を調査し、ご自身の空き家に最適な活用・売却プランを立てることが、賢い空き家対策の第一歩となります。
空き家税導入の影響を考える
地域社会の住宅供給確保と空き家問題の改善に向けて

京都市の空き家税導入は、単に税収を増やすことだけを目的としているわけではありません。その根底には、京都市が直面する喫緊の社会課題、すなわち「住宅供給の確保」と「空き家問題の抜本的改善」があります。
京都市では、若い世代や子育て世代の市外流出が大きな課題となっており、その一因として市内の住宅価格高騰や適切な広さの住宅不足が挙げられます。
この税は、使われていない空き家を市場に流通させることで、新しい住宅供給の受け皿を作り、市民の居住を促すことを目指しています。空き家が適切に活用されることで、地域の景観が改善され、不法侵入や火災などの防犯・防災上のリスクが減ります。
これにより、地域コミュニティの活性化が図られ、安心・安全な生活環境の確保にもつながると考えられています。
この税制は、空き家を「個人の資産」という側面だけでなく、「地域社会の重要なストック」として捉え、その有効活用を促すという、より広範な政策的な意図を含んでいます。空き家が生じさせる様々な問題を解消しつつ、持続可能なまちづくりに貢献することを目的としています。
空き家問題を解決するために、京都市の取り組みから何を学ぶか
京都市の空き家税は、空き家問題への取り組みを促す強力な「政策誘導」のツールとして機能します。税金という直接的なインセンティブを通じて、所有者に対し、空き家の放置ではなく、積極的な活用や売却、あるいは適切な管理を促すものです。
しかし、税制度だけで解決できない課題も存在します。空き家問題の根本的な解決には、税制度と連携した多角的な方策が不可欠です。
- 財政的支援の拡充: 空き家の解体、改修、購入に対する補助金制度は、所有者や利用希望者の経済的な負担を減らし、活用を促す上で重要な役割を果たします。
- 情報提供とマッチングの強化: 空き家バンクのようなプラットフォームの充実や、所有者と利用希望者のニーズを的確に結びつけるマッチング機能の強化は、空き家の流通を活性化させます。
- 専門家によるワンストップ支援: 不動産、法律、税務、建築などの専門家が連携し、空き家に関するあらゆる相談に一元的に対応できる窓口の設置は、所有者の心理的・手続き的な負担を減らし、問題解決へのハードルを下げます。
- 地域コミュニティとの連携: 空き家を地域交流拠点や子育て支援施設として活用するなど、地域資源としての再生を促すことで、コミュニティの活性化にも貢献します。
- 地方公共団体間の連携: 他の自治体の先進事例を参考に、固定資産税納税通知書を活用した情報提供や、シルバー人材センターとの連携による見回りサービスなど、地域の実情に応じた多様な取り組みを推進することが重要です。
これらの多角的な取り組みが連携することで、空き家問題は「負の遺産」から「地域の活性化に貢献する資産」へと転換され、持続可能な地域社会の実現に寄与することが期待されます。
空き家税実施後のトレンドと今後の動向
空き家対策の今後は?課題と期待される法律改正
京都市の空き家税導入は、全国で初めての試みとして大きな注目を集めていますが、実施後にはいくつかの課題が出てくる可能性があります。
- 公平性と透明性の確保: 空き家所有者の個別の事情(売却が難しい、解体費用がないなど)に配慮しながら、税制度の公平性と透明性をどのように保つかが継続的な課題となります。
- 補完的政策の必要性: 空き家税による政策誘導だけでは、若い世代の移住促進や住宅不足の解消に限界がある可能性も指摘されています。そのため、移住支援策や子育て世代向けの住宅補助など、税制と連携した他の政策の充実が求められます。
- 市場への影響: 税負担の増加が、空き家の売却を急がせる一方で、急激な供給増による価格の下落や、買い手が見つかりにくい物件がさらに放置されるといった市場への影響も注意深く見守る必要があります。
- 解体・改修需要の集中: 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正により、管理不全空き家への対応が強化され、解体や改修の需要が急増する可能性があります。これにより、解体業者の不足や費用高騰、悪質な業者による問題が発生しないよう、供給体制の整備や情報提供が課題となります。
- 建築基準法・省エネ法改正(2025年4月施行)への対応: 今後、空き家をリフォームして貸したり売ったりする場合でも、建築確認申請や省エネ基準への適合が義務化されます。これは、空き家の活用を促す上で新たなハードルとなるため、所有者や事業者への情報提供、専門家によるサポート体制の強化が不可欠です。
京都市の空き家税条例は、施行後5年ごとに制度の状況や社会経済情勢の変化を考慮し、見直しを行うこととされています。これは、制度が柔軟に運用され、実情に合わせて改善が期待されることを意味します。
また、全国的に空き家問題が深刻化していることから、今後も国レベルでの法改正や、他の自治体による新しい税制度の導入が検討される可能性は十分に考えられます。
空き家税が地域に与える影響と、松山で今すぐできる対策
京都市の空き家税導入は、地域社会に多岐にわたる影響を及ぼすことが予想されます。最も直接的な影響は、空き家所有者に対し、その物件の管理や活用、売却を促す強いきっかけとなることです。
これにより、放置された空き家が減少し、地域の景観が改善され、防犯・防災上の安全性が向上することが期待されます。
また、空き家が市場に流通することで、住宅供給が増え、特に若い世代や子育て世代の居住促進につながる可能性があります。これは、京都市が抱える人口減少問題への対策としても機能し、地域コミュニティの活性化に貢献するでしょう。
一方で、空き家税は、空き家問題が「個人の負担」から「社会全体の課題」へと認識が変化していることの表れでもあります。所有者には、自身の空き家を「社会的ストック」として適切に管理する責任が強く求められるようになります。
このような状況において、空き家所有者が取るべき対策は、早期かつ計画的な行動です。
- 現状把握と情報収集: まずはご自身の空き家の現状を正確に把握し、京都市の空き家税の具体的な適用条件や免除規定、さらには国や自治体が提供する補助金制度などの情報を積極的に集めることが重要です。
- 専門家への相談: 空き家税の計算や特例の適用、売却や活用、そして最適な管理戦略を立てるには専門的な知識が不可欠です。当事務所は、行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格を併せ持つ専門家として、法務、税務、不動産、建築といった多角的な視点から、所有者の状況に合わせた最適な解決策をご提案し、必要な手続きをサポートすることができます。
- 具体的な計画の策定と実行: 放置することのリスクとコストを理解し、賃貸、売却、自己利用、解体など、具体的な活用・処分計画を早期に策定し、実行に移すことが、将来的な税負担の軽減と資産価値の維持につながります。特に、相続から3年以内など、税制優遇の期限を意識した行動が求められます。
空き家税の導入は、空き家問題を解決するための新たな一歩であり、所有者にとっては行動を促す強力なきっかけとなります。適切な対策を講じることで、空き家を負債ではなく、地域社会に貢献する資産へと転換させることが可能となります。
空き家問題、一人で抱え込まずにご相談ください
松山市の村上行政書士事務所は、空き家に関する豊富な知識と経験を持つ専門家です。相続問題、売却、利活用、解体、適切な管理方法など、あらゆる空き家のお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案します。
あなたの空き家は「負の遺産」ではありません。未来の資産として、賢く活用・管理するためのお手伝いをさせてください。
まずは【初回無料相談】をご利用ください。
どんな些細なことでも構いません。まずはあなたの空き家の状況をお聞かせください。専門家として、客観的な視点からアドバイスさせていただきます。



