
「空き家=住民税不要」は本当?見逃せない誤解と法律改正
空き家所有者の間でよく聞かれる「空き家なら住民税は不要」という話。実はこれ、大きな誤解なんです。2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、空き家に対する行政の姿勢や固定資産税の取り扱いは大きく変わりました。住民税と空き家の関係を正しく理解し、最新の法改正を踏まえた対策で、将来の税負担を最小限に抑えましょう。
空き家と住民税の基礎知識|誤解されやすいポイントを解説
そもそも空き家とは?家屋・土地の定義と対象要件
空き家とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいいます。この定義は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいており、単に「誰も住んでいない家」という一般的な認識とは異なる法的な要件があります。
空き家の判定において重要なのは、「常態として使用されていない」という点です。つまり、一時的に居住者がいない状態ではなく、継続的に使用されていない状態を指します。週末のみ利用するセカンドハウスや、年数回の利用にとどまる別荘なども、条件によっては空き家として扱われる可能性があります。
対象となる家屋は、一戸建て住宅、共同住宅、店舗兼住宅など、居住の用に供する建物全般が含まれます。また、その敷地となる土地も空き家対策の対象となり、税制上の取り扱いに大きく影響します。
住民税・固定資産税の違いと空き家との関係
住民税と固定資産税は、課税の仕組みが根本的に異なります。住民税は「人」に対する税金であり、固定資産税は「物」に対する税金です。この違いを理解することが、空き家に関する税金の誤解を解く鍵となります。
| 税目 | 課税対象 | 課税権者 | 課税標準 |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 個人(住所地) | 住所地の市区町村 | 前年の所得金額 |
| 固定資産税 | 不動産(所在地) | 不動産所在地の市区町村 | 固定資産の評価額 |
住民税は、1月1日時点の住民票所在地で課税されます。空き家を所有していても、所有者が別の場所に住んでいる場合、住民税は実際の居住地で課税されます。一方、固定資産税は不動産の所在地で課税され、空き家の所有者は所在地の市区町村に固定資産税を納付する義務があります。
多い誤解:『空き家なら住民税不要』は本当か?
結論:空き家を所有していても住民税は必要です。
住民税は個人の住所地で課税されるため、空き家の所有とは直接関係ありません。
この誤解が生まれる理由は、固定資産税の住宅用地特例と住民税の仕組みを混同してしまうことにあります。固定資産税では、住宅が建っている土地に対して課税標準を軽減する特例措置がありますが、これは住民税とは全く別の制度です。
住民税の課税要件は以下の通りです
- 1月1日時点で住民票がある市区町村で課税
- 前年の所得が一定額以上の場合に課税
- 不動産の所有状況は住民税の課税要件ではない
つまり、空き家を所有していても、所有者が他の場所に住んでいる場合、住民税は実際の居住地で課税されます。空き家所有による住民税への直接的な影響は、空き家を売却した際の譲渡所得に対する住民税(譲渡所得税の住民税分)程度に限定されます。
最新の法改正|空き家税・固定資産税6倍ルールの全貌と影響
空き家税の導入はいつから?京都市の事例と今後の動向
2023年12月13日に施行された改正空家法により、空き家対策は大幅に強化されました。特に注目すべきは、京都市が全国初となる「空き家税」(正式名称:非居住住宅利活用促進税)の導入を決定したことです。京都市では、2029年度(令和11年度)からの課税開始を目指しています。
京都市の空き家税概要
- 課税開始:2029年度(令和11年度)
- 対象:市街化区域内の非居住住宅
- 税率:家屋価値割0.7%、立地床面積割0.15%〜0.6%
- 免税点:固定資産評価額20万円未満(導入当初5年間は100万円未満)
京都市の空き家税は、空き家や別荘、セカンドハウスなどの非居住住宅の所有者に対して課税される法定外税です。この税制の導入により、非居住住宅の有効活用を促進し、住宅供給の増加を図ることが目的とされています。
課税対象となるのは、生活の本拠として利用されていない住宅です。住民票の有無だけでなく、実際の生活実態によって判断されるため、住民票があっても実際に居住していない場合は課税対象となる可能性があります。
全国で加速する税制改正と新たな課税強化の流れ
京都市の空き家税導入を皮切りに、全国の自治体で空き家対策の強化が検討されています。総務省は京都市の空き家税に同意を与えており、今後他の自治体でも類似の制度導入が予想されます。
空き家対策の強化背景には、以下の社会的課題があります
- 空き家総数の継続的な増加(2023年時点で約849万戸)
- 人口減少と高齢化による空き家の増加加速
- 地域コミュニティの活力低下
- 防災・防犯・衛生上の問題の深刻化
これらの課題を解決するため、国は空き家対策特別措置法を改正し、自治体の権限を強化しました。今後は、空き家の所有者に対してより厳格な管理義務が課せられることになります。
特定空家等とは?指定・要件・管理不全の具体例
改正空家法では、従来の「特定空家等」に加えて、新たに「管理不全空家」という概念が導入されました。これにより、特定空家になる前の段階から行政指導が可能となりました。
| 分類 | 要件 | 行政措置 | 税制上の影響 |
|---|---|---|---|
| 管理不全空家 | 放置すれば特定空家となる恐れがある状態 | 指導・勧告 | 勧告により住宅用地特例除外 |
| 特定空家等 | 倒壊等の危険性、衛生上有害、景観阻害等 | 助言・指導・勧告・命令・代執行 | 勧告により住宅用地特例除外 |
管理不全空家の具体例:
- 屋根や外壁の一部が剥がれかけている
- 庭木が伸び放題で近隣に迷惑をかけている
- 雨樋が壊れて適切に修繕されていない
- 窓ガラスが割れたまま放置されている
特定空家等の具体例:
- 建物が著しく傾斜している
- 屋根や外壁が崩落する危険性がある
- ゴミの散乱や悪臭により衛生上有害
- 景観を著しく損なっている
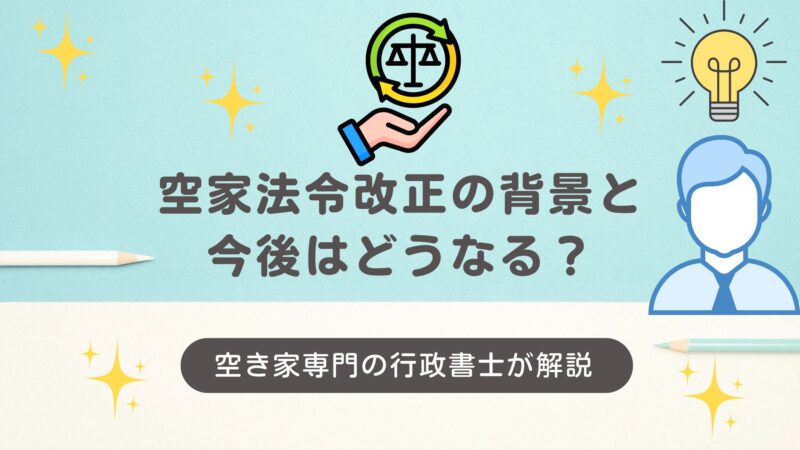
固定資産税『6倍』となるケース|計算方法と税率の仕組み
住宅用地特例が除外されることで、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。この仕組みを正確に理解することが重要です。
住宅用地特例の内容
小規模住宅用地(200㎡以下):固定資産税 1/6、都市計画税 1/3
一般住宅用地(200㎡超):固定資産税 1/3、都市計画税 2/3
例えば、200㎡以下の住宅用地で固定資産税が年額12万円の場合:
- 特例適用時:12万円
- 特例除外時:72万円(6倍)
- 年間負担増:60万円
この特例除外は、管理不全空家または特定空家等に対する勧告を受けた翌年度から適用されます。勧告を受けた年の翌年1月1日時点で判定されるため、早期の対策が重要です。
空き家の住民税・固定資産税はどうなる?課税方法と例外
所有・相続・放置で変わる住民税の発生パターン
空き家の所有形態や取得経緯により、住民税への影響は以下のように変わります。
| ケース | 住民税への影響 | 注意点 |
|---|---|---|
| 購入による所有 | 直接的な影響なし | 維持費は所得から控除不可 |
| 相続による取得 | 相続時は影響なし | 売却時に譲渡所得税が発生 |
| 長期放置 | 直接的な影響なし | 管理費用の増加 |
| 賃貸収入がある場合 | 不動産所得として課税 | 収入に応じた住民税負担 |
住民税に最も大きな影響を与えるのは、空き家を売却した場合の譲渡所得です。特に相続した空き家の場合、取得費が不明確であることが多く、譲渡所得が高額になる可能性があります。
課税対象となる空き家とは?12月31日・1月1日等の判定時点
空き家に関する各種税金の判定時点は以下の通りです:
- 固定資産税・都市計画税:1月1日時点の所有者
- 住民税:1月1日時点の住所地
- 所得税・住民税(譲渡所得):売却した年
- 相続税:相続開始時点
特に固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、1月2日に売却しても、その年の固定資産税は元の所有者に課税されます。売買契約時には、この点を考慮した清算を行うことが一般的です。
無料になる?減額・軽減・特例措置の条件と申請方法
空き家に関する税金の軽減措置は限定的ですが、以下の特例措置があります。
被相続人居住用家屋等の特別控除
相続により取得した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できます。
主な適用要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 相続開始直前まで被相続人が一人で居住
- 相続開始から売却まで使用されていない
- 耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して売却
- 売却価格が1億円以下
- 相続開始から3年経過する年の12月31日まで
- 適用期限:2027年12月31日まで
特に注意が必要なのは、「一人で居住」という要件です。原則として相続開始直前まで被相続人が一人で居住している必要がありますが、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、以下の要件を全て満たせば特例の対象となります。
- 老人ホーム等に入所する直前まで、その家屋に被相続人が一人で居住していたこと。
- 老人ホーム等に入所後も、その家屋を事業の用、貸付けの用又は居住の用に供していなかったこと。
- 相続開始直前まで、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けていたこと。

固定資産税の減免制度
災害や生活困窮などの特別な事情がある場合、市区町村の判断により固定資産税の減免が受けられる場合があります。
個人住民税と空き家所有の関係に注意
個人住民税と空き家所有の関係で注意すべきポイントは以下の通りです。
- 賃貸収入がある場合:空き家を賃貸に出している場合、賃貸収入は不動産所得として住民税の課税対象となります。
- 売却による譲渡所得:空き家を売却した場合、譲渡所得に対して住民税が課税されます。
- 相続時の影響:相続により空き家を取得した場合、直接的な住民税負担はありませんが、将来の売却時に影響があります。
特に重要なのは、空き家の維持管理費用は所得から控除できないという点です。固定資産税、保険料、修繕費などの維持費用は、賃貸収入がない限り所得控除の対象とはなりません。
空き家にまつわる税金対策と実践方法
税金対策の基本|管理・活用・申告のポイント
空き家の税金対策における基本的な考え方は、「予防」「活用」「適正申告」の3つです。
予防的対策
- 定期的な点検・清掃により管理不全空家への指定を防ぐ
- 近隣住民との良好な関係を維持し、苦情を未然に防ぐ
- 必要に応じて専門家による建物診断を実施
活用による対策
- 賃貸住宅としての活用(リノベーション含む)
- 民泊やシェアハウスとしての活用
- 地域交流拠点やコミュニティスペースとしての活用
適正申告のポイント
- 売却時の特別控除の適切な適用
- 取得費の正確な計算と証明書類の保管
- 確定申告の適切な時期と方法
売却・賃貸・解体・活用による税負担の抑え方
空き家の処理方法により、税負担は大きく変わります。各選択肢のメリット・デメリットを比較検討することが重要です。
| 処理方法 | 税務上のメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却 | 特別控除の適用可能 固定資産税負担の終了 | 譲渡所得税の発生 特例要件の確認必要 |
| 賃貸 | 不動産所得による収入 経費の所得控除 | 継続的な管理義務 住民税負担の増加 |
| 解体 | 管理不全指定の回避 更地活用の可能性 | 住宅用地特例の消失 解体費用の負担 |
| 活用 | 収益化の可能性 地域貢献による評価 | 初期投資の必要 事業リスクの存在 |
相談窓口・専門家への依頼と無料査定の活用
空き家の税金対策は複雑であり、専門家の助言を受けることが重要です。相談できる窓口は以下の通りです:
- 市区町村の空き家対策部署:地域の空き家対策情報、支援制度の案内
- 税理士:税務申告、節税対策の専門的アドバイス
- 行政書士:各種申請手続き、法令遵守のサポート
- 不動産業者:売却・賃貸の市場価格査定、仲介業務
- 司法書士:相続登記、所有権移転登記などの法務手続き
無料査定サービスを活用することで、空き家の現在価値を把握し、適切な処理方法を選択することができます。ただし、査定結果は不動産業者により異なるため、複数社での査定を推奨します。村上行政書士事務所では、各専門家と提携しており、ワンストップでの解決が強みです。
空き家の売却・相続時に知っておきたい特例措置・控除
居住用家屋の特別控除と譲渡所得税の仕組み
空き家の売却時に適用される特別控除は、税負担を大幅に軽減できる重要な制度です。特に被相続人居住用家屋等の特別控除は、最大3,000万円の控除が可能です。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用 – 特別控除
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算します(概算取得費)。しかし、これでは譲渡所得が高額になるため、可能な限り実際の取得費を証明する書類を用意することが重要です。
相続税・所得税・登録免許税─発生する税金の種類と計算方法
空き家の相続・売却時に発生する可能性のある税金は以下の通りです。
| 税目 | 課税タイミング | 計算方法 | 軽減措置 |
|---|---|---|---|
| 相続税 | 相続開始時 | 相続財産の評価額から基礎控除を差し引き | 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数 |
| 所得税 | 売却時 | 譲渡所得×税率 | 特別控除3,000万円 |
| 住民税 | 売却翌年 | 譲渡所得×住民税率 | 特別控除3,000万円 |
| 登録免許税 | 登記時 | 固定資産評価額×税率 | 相続登記:0.4% |
適用に必要な証明書・発行・様式と確定申告の流れ
被相続人居住用家屋等の特別控除を適用するために必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村発行)
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 耐震基準適合証明書または建物取壊し証明書
確定申告の流れ
- 必要書類の収集(売却年の12月まで)
- 確定申告書の作成(翌年2月16日〜3月15日)
- 税務署への提出または電子申告
- 納税または還付金の受領
被相続人居住用家屋等の特例と要件・期間をチェック
特例の適用要件は複雑であり、一つでも欠けると適用できません。主な要件を再確認しましょう:
重要な要件
- 家屋:昭和56年5月31日以前の建築
- 居住状況:相続開始直前まで被相続人が一人で居住
- 使用状況:相続開始から売却まで使用されていない
- 震性:耐震基準を満たすか取り壊して売却
- 売却価格:1億円以下
- 売却期限:相続開始から3年経過する年の12月31日まで
- 制度期限:2027年12月31日まで
特に注意が必要なのは、「一人で居住」という要件です。被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、入所直前まで一人で居住していれば要件を満たします。
空き家の管理・放置リスクと行政対応
管理不全・放置によるリスクと費用負担の現実
空き家の放置は、所有者にとって深刻な経済的・法的リスクを生み出します。2023年の法改正により、これらのリスクは一層高まりました。
経済的リスク
- 固定資産税の最大6倍負担(年間60万円以上の増加も)
- 建物価値の継続的な減少
- 管理費用の増加(月額数万円の管理委託料)
- 災害時の損害賠償責任
法的リスク
- 行政による強制執行(代執行)
- 50万円以下の過料
- 近隣住民からの損害賠償請求
- 刑事責任の可能性(重大な事故の場合)
実際の費用負担例
- 固定資産税増加分:年間60万円
- 管理委託料:月額2〜5万円
- 修繕費:年間20〜50万円
- 代執行費用:100〜500万円
市町村からの勧告、指導、強制執行の可能性
改正空家法により、市区町村の権限は大幅に拡大されました。行政対応のフローは以下の通りです
管理不全空家への対応
- 現地調査・所有者確認
- 管理不全空家の認定
- 指導(改善の勧告)
- 勧告(住宅用地特例の除外)
特定空家等への対応
- 特定空家等の認定
- 助言・指導
- 勧告(住宅用地特例の除外)
- 命令(50万円以下の過料)
- 代執行(強制撤去、費用請求)
緊急代執行の新設
改正により、台風等の自然災害で緊急性が高い場合、命令等の手続きを経ずに代執行が可能となりました。
自治体別支援策と相談先・コラム
多くの自治体では、空き家対策のための支援策を用意しています。主な支援策は以下の通りです。
除却(解体)支援
- 解体費用の一部補助(上限50〜100万円)
- 解体業者の紹介
- 手続きの代行サービス
活用支援
- 改修費用の一部補助
- 空き家バンクへの登録
- 利用者とのマッチング
相談窓口
- 市区町村の空き家対策部署
- 空家等管理活用支援法人
- 宅地建物取引業協会
- 司法書士会・行政書士会
これらの支援策を活用することで、空き家の適切な処理を低コストで実現できる可能性があります。まずは所在地の市区町村や当事務所のような専門家に相談することをお勧めします。
【まとめ】空き家の税金・住民税対策は早めの検討・情報確認がカギ
重要なポイントの再確認
住民税の誤解を解消
「空き家=住民税不要」は完全な誤解です。住民税は個人の住所地で課税されるため、空き家の所有とは直接関係ありません。空き家を所有していても、居住地での住民税納付義務は継続します。
法改正による重大な変化
2023年12月の空家法改正により、管理不全空家の概念が新設され、特定空家になる前から行政指導が可能となりました。京都市では2029年度から全国初の空き家税も導入予定です。
固定資産税6倍のリスク
勧告を受けた管理不全空家・特定空家は、住宅用地特例が除外され、固定資産税が最大6倍になります。年間60万円以上の負担増となるケースもあり、経済的な打撃は非常に大きいものです。
特別控除の活用
相続空き家の売却では、被相続人居住用家屋等の特別控除(3,000万円)が適用できます。ただし、2027年12月31日までの期限付きです。
早期対策の重要性
空き家問題は先送りするほど深刻化します。管理不全になる前に、売却・賃貸・活用等の方針を決定し、適切な対策を講じることが重要です。
今後の行動指針
空き家を所有している方は、以下の行動を推奨します。
- 現状把握:建物・土地の状態、市場価値、法的位置づけの確認
- 方針決定:売却・賃貸・活用・解体等の具体的な方針策定
- 専門家相談:税理士・行政書士等による専門的アドバイスの取得
- 支援制度活用:自治体の補助金・支援制度の積極的活用
- 適切な手続き:必要な申請・申告手続きの確実な実施
空き家問題は個人の問題にとどまらず、地域社会全体の課題です。適切な対策により、所有者の経済的負担を軽減し、地域の活性化にも貢献できます。
法改正により空き家を取り巻く環境は大きく変化しました。最新の情報を常に確認し、早期の対策実施により、将来のリスクを最小限に抑えることが重要です。
当事務所は、松山市の空き家問題に特化した行政書士事務所であり、認定空き家再生診断士の資格も保有しております。また、司法書士・不動産業者とも提携しております。そのため、空き家の持ち主調査から、相続、売却、活用方法のご提案まで、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供することができます。
「この空き家、どうにかしたいけど、何から手をつけていいか分からない…」 「所有者調査って、自分でできるの?」 「複雑な空き家問題、誰に相談すればいいの?」
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。 松山市の空き家に関するご相談は、初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。



