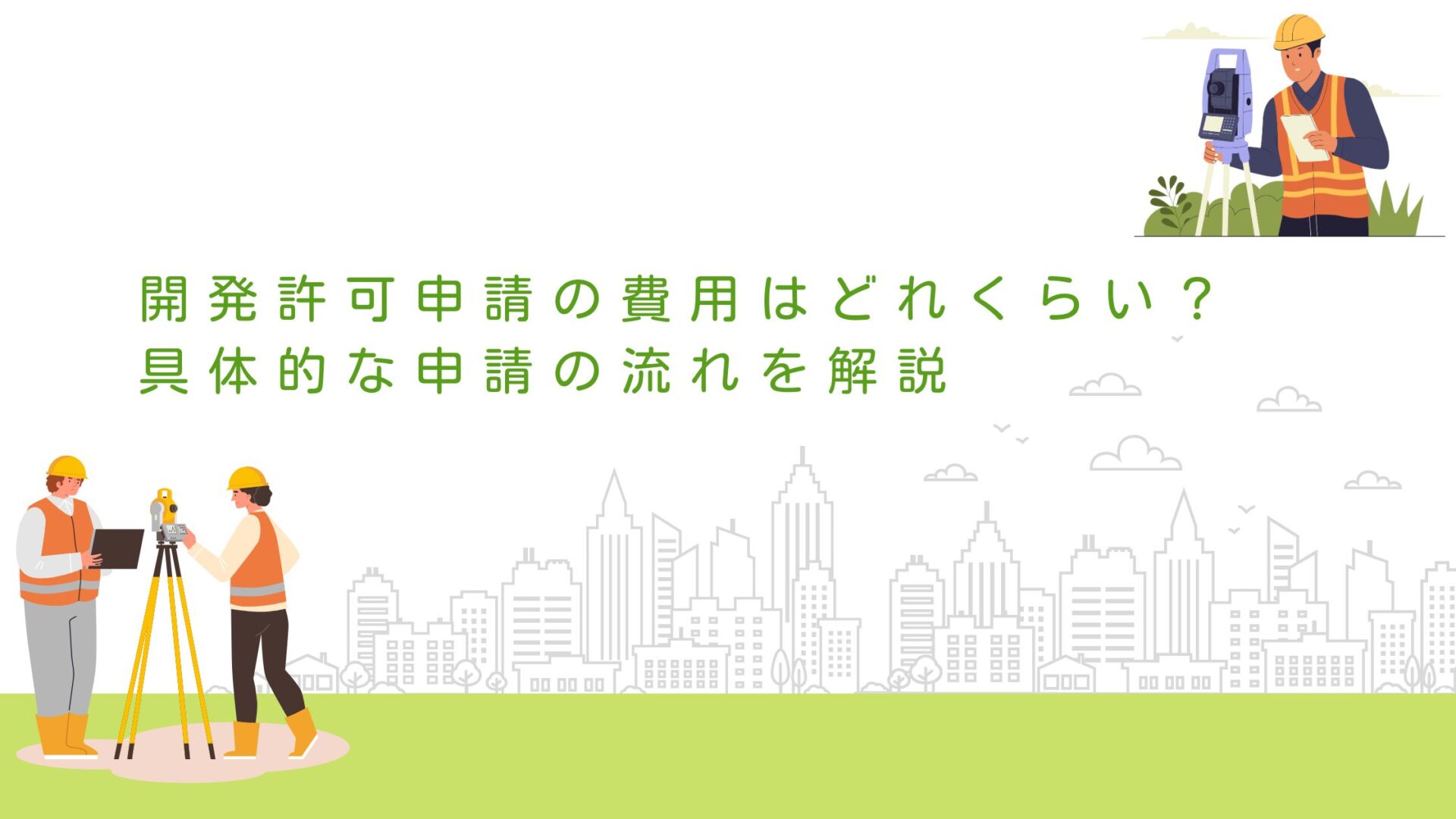
開発許可申請の費用はどれくらい?具体的な申請の流れを解説
都市計画法に基づく開発許可申請は、土地の区画形質の変更を伴う不動産開発を行う上で避けて通れない行政手続きです。特に松山市を含む愛媛県内で大規模な土地活用を検討する事業者や地主にとって、この許可の取得は事業の成否と期間を大きく左右します。
この記事では、開発許可申請の定義、具体的な申請フロー、そして最も関心の高い費用構造について、専門的な視点から詳細に解説します。
村上行政書士事務所は、行政書士資格に加え、不動産取引の専門家である宅地建物取引士、そして地域の資産再生に特化した認定空き家再生診断士の資格を併せ持っています。また、開発許可専門の土地家屋調査士と提携しております。
これにより、単なる許認可の代行に留まらず、開発計画の初期段階から不動産の活用・売却という出口戦略までを見据えたワンストップの専門的なサポートを提供します。
開発許可申請とは?基礎知識と必要なケースを解説
開発許可申請の定義と開発行為の対象範囲
都市計画法における「開発行為」とは、主に建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行われる「土地の区画形質の変更」を指します。この「区画形質の変更」には、以下の要素が含まれます。
- 区画の変更: 主として建築物の建設を目的として行う、道路、公園、下水道などの公共施設の新設や改廃を伴う土地の区画の変更を意味します。
- 形質の変更: 土地の物理的な形状を変える切土や盛土といった造成工事を指します。
開発行為を行う場合、無秩序な市街地の拡大を規制し、計画的な土地利用を促進するために、都市計画法第29条に基づき、あらかじめ都道府県知事(または指定都市等の市長)の許可を得る必要があります。
許可が必要となる開発行為の規模は、土地が所在する都市計画区域の区分によって異なり、以下の基準面積以上で行う場合に許可申請が求められます。
開発許可が必要となる基準面積(都市計画区域別)
| 区域区分 | 許可が必要となる開発行為の基準面積(一般基準) | 根拠法規 |
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 | 都市計画法 第29条 |
| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 | 都市計画法 第29条 |
| 都市計画区域外および準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)以上 | 都市計画法 第29条 |
なお、三大都市圏の特定の区域では、許可が不要な面積の基準が500平方メートル未満とされている例外規定が存在しますが、松山市を含む愛媛県内では、上記の一般基準を適用して判断することが通常です。
都市計画法と開発許可申請の関係性
開発許可制度は、都市計画法上の重要な規制手段として設けられており、その趣旨は、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、および住民の利便性の増進を図ることにあります。
開発行為を規制することで、計画性のない無秩序な開発を防ぎ、社会基盤の整備が追いつかない「スポンジ状の市街化」を抑制する目的があります。
近年の法制度の動向として、気候変動の影響による自然災害の頻発化・激甚化に伴い、開発許可制度の役割が拡大しています。現在では、開発許可制度は、単に土地利用を規制するだけでなく、災害リスクの高い区域における新たな開発行為を抑制する手段としても重要視されています。
これにより、開発申請の審査においては、将来的な防災・減災計画への適合性や、計画地の地盤の安全性に関する技術的な立証が、以前にも増して厳格に求められる傾向にあります。
市街化調整区域や農地転用が関係する場合の注意点
開発計画地が市街化調整区域や農地である場合、手続きの難易度は格段に上昇し、特別な注意が必要となります。
市街化調整区域における厳格な立地基準
市街化調整区域は、都市計画法に基づき「市街化を抑制するための区域」として定められており、原則として住宅や商業施設の建築が厳しく制限されています。
この区域で開発行為を行う場合、都市計画法第34条に定める特定の「立地基準」のいずれかに該当する開発でなければ許可されません。
具体的には、開発行為の目的が「公益性がある」と認められるか、周辺の土地利用に悪影響を及ぼさないか、公共施設(道路・上下水道など)との接続状況が確保されているかなど、非常に厳しい審査基準が課されます。
市街化調整区域での開発は、客観的な技術基準(法第33条)だけでなく、開発審査会への諮問(法第34条第14号)を通じて、個別案件の特例的な必要性や公益性を論理的に立証する必要があり、不許可となるリスクが極めて高い分野です。
農地転用との二重規制
開発行為の対象地が農地である場合、開発行為(都市計画法)の規制に加え、農地の保全を目的とする農地法による規制も同時に受けます。
つまり、事業者は都市計画法上の開発許可と、農地法上の農地転用許可の両方を取得しなければなりません。
特に、農地の中でも農業振興地域内の農用地区域(青地農地)に指定されている土地の場合、農地転用申請を行う前に、まず自治体に対して「農振除外」という手続きを経る必要があります。
この農振除外は、受付期間が年1~2回に限定され、手続きが完了するまでに半年から1年以上かかるケースがあり、開発全体のスケジュールを大幅に長期化させる要因となります。
また、松山市では、法的な許可基準(市街化区域1,000㎡)に満たない0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の開発行為に対しても「松山市開発行為に関する指導要綱」を適用し、市長への事前協議や協定の締結を求める場合があります。
これは、法的な許可基準未満の小規模な開発であっても、松山市が地域の環境保全や公共施設への影響を厳格に管理したいという意図の表れであり、開発検討者は、この指導要綱に基づく行政的な準備と、地域の特性や行政の長期計画(都市マスタープラン)を深く理解したうえで協議に臨む能力が求められます。

開発許可申請の費用相場と内訳
開発許可申請にかかる総費用は、行政に支払う「手数料」は比較的少額である一方、申請に必要な技術的資料を作成するための「専門家報酬」と「実費」が大部分を占めます。
開発許可申請に必要な費用一覧(手数料・報酬等)
開発許可申請に関連する費用は、主に以下の三つに分けられます。
- 行政手数料(公的費用): 愛媛県の条例に基づき、開発区域の面積に応じて定められています。詳しくは松山市ホームページをご参考ください。→建築指導課で取り扱う手数料一覧
- 専門家報酬(代行費用): 行政書士による申請代行報酬、土地家屋調査士による測量や図面作成、設計士による公共施設の設計費用などが含まれます。これが総費用の核となります。
- 実費・雑費: 各種調査費用、印紙代、交通費、通信費などです。
費用の勘定科目・会計処理のポイント
法人として開発事業を行う場合、開発許可申請にかかる費用は、会計処理上、単なる「経費」としてではなく、土地や建築物の「取得原価」として処理されることが一般的です。
これは、開発許可を得なければ、その土地を開発目的で利用することができないため、許可取得費用が土地の価値を高めるために不可欠な支出と見なされるためです。
専門家報酬や行政手数料は、「開発費」や「仕掛資産」といった形で原価に算入され、最終的に販売される不動産のコストとなります。また、開発に伴う造成工事費用や、新設する道路、上下水道等の公共施設整備費用も、同様に土地・建物の取得原価に組み込まれます。
市街化調整区域など区域別の費用の違い
開発許可申請の費用相場は、対象区域の複雑性によって大きく変動します。
難易度による報酬の変動
市街化調整区域(法第34条申請)での開発は、市街化区域での開発と比較して、行政協議の回数、要求される調査の深度、および立地基準適合の立証難易度が格段に上がります。
この複雑性に対応するため、行政書士の報酬相場も高額になる傾向があります。通常の開発許可申請代行報酬(154,000円〜)に対し、市街化調整区域の案件は、さらに詳細な調査費用や交渉費用が加算されることが一般的です 。
農地転用費用の上乗せ
農地転用が同時に必要な場合、農地法に基づく許可申請(農地法5条許可など)の報酬(50,000円〜)が別途上乗せされます。
さらに、農振除外が必要となると、その手続き費用と時間が追加されます。
行政書士や土地家屋調査士への依頼費用・代行費用
開発許可申請は、法的な手続きを行う「行政書士」と、測量および区画形質の変更に関する技術図面を作成する「土地家屋調査士」または「設計士」の連携が不可欠です。
- 行政書士の報酬目安: 開発許可申請(一般)の代行報酬は、154,000円〜(税込)が相場感として示されています。ただし、これは法務・行政手続きに関する報酬であり、技術的な資料作成費用は含まれません。
- 技術資料作成費用の支配: 行政手数料は最大でも約10万円程度で頭打ちとなりますが、開発許可申請の真の費用は、申請に必要な技術的な準備、すなわち測量、高度な設計、計算書(構造計算書、水理計算書、土量計算書など)の作成にかかる専門家報酬が中心となります 。土地の形状や高低差、必要な公共施設の設計の複雑さが増すほど、測量・設計費用は大幅に上昇します。
したがって、総費用を抑え、手続きを円滑に進めるためには、初期段階で行政書士が行政の要求を正確に把握し、技術専門家と密接に連携し、手戻りのない正確な計画図書を作成できる体制を構築しているかどうかが最も重要な判断基準となります。
愛媛県(松山市)における開発許可申請の手数料と報酬相場(目安)
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の手数料
| 費用の種類 | 内訳/対象 | 愛媛県条例等に基づく公的手数料 | 専門家報酬相場(目安) |
| 行政手数料 | 0.1ha未満の申請 | 8,800円 | – |
| 行政手数料 | 1.0ha以上の申請 | 130,000円 | – |
| 行政手数料 | 市街化調整区域内 特例許可申請 | 47,000円 | – |
| 専門家報酬 | 開発許可申請代行(法第29条) | – | 154,000円〜(税込) |
| 専門家報酬 | 農地転用許可申請(5条) | – | 50,000円〜 |
| 専門家報酬 | 測量/設計図面作成 | – | 個別見積もり(土地家屋調査士/設計事務所) |
開発許可申請の具体的な流れと期間
開発許可申請は、現地調査、行政協議、技術資料作成、審査という複数の段階を経て進行し、全体の期間は数ヶ月から年単位に及びます。
申請手続きの全体フローチャート
手続きは、主に以下のステップで進行します。
- 開発計画の策定・法規制調査
- 自治体への事前相談・指導要綱に基づく協議(松山市では0.3ha以上)
- 公共施設管理者との同意取得(法第32条協議)
- 申請書及び添付書類の作成・提出
- 行政による審査(必要に応じて開発審査会へ諮問)
- 許可の交付
- 工事着手・完了検査
- 開発登録簿への登録・公告
開発計画・事前協議・同意・提出までのステップ
申請手続きにおいて最も重要かつ時間を要するのが、行政への「事前協議」と「同意取得」のステップです。
- 事前協議の重要性: 開発行為に着手する前に、計画が都市計画法および自治体の指導要綱(松山市では指導要綱第6条)に適合しているかについて、都市計画課などの担当部署と綿密に協議を行うことが必須です 。この協議の結果に基づき、計画の修正や、松山市においては市長との協定締結(第8条)の必要性が決まります。
- 公共施設管理者との同意(法第32条): 開発によって新設または改廃される道路、下水道、水路などの公共施設について、それらの施設管理者から事前に同意を得る必要があります。この同意取得が遅れると、申請書が受理されないため、全ての関係機関との調整を円滑に進める能力が求められます。
申請書や必要書類の用意・様式・資料取得方法
開発許可申請は、申請書自体よりも、その添付書類として要求される膨大な技術的図書の作成に労力を要します。
- 要求される技術資料の例: 道路計画断面図、縦断図、下水道計画縦断図、防災計画平面図・構造図、工事工程表、仕様書、土質説明書などが挙げられます 。さらに、地盤や水利に関する構造安定計算書、水理計算書、土量計算書といった高度な技術計算書も提出が必要です。
- 作成責任の明確化: これらの図面や計算書には、作成者自身の記名または署名を行うことが求められ、技術的な責任の所在が明確化されています。したがって、行政書士が円滑な行政手続きを担い、土地家屋調査士や設計士が高度な技術資料を正確に作成するという、専門家間の密な連携が不可欠となります。
- 申請の提出方法: 申請書は、単に申請先に行うだけでなく、関係する市町を経由し、市町の意見書を添えて提出することが求められます。
当事務所は土地家屋調査士の先生と提携しておりますので、ワンストップで申請まで進めることができます。
完了検査・交付・公告までの期間目安
申請が受理されてからの行政による標準処理期間は設定されているものの、実質的に許可を得るまでの期間は、事前協議や技術資料作成に要する期間に大きく左右されます。
複雑な開発(特に市街化調整区域や大規模開発)の場合、事前調査、法第32条同意、技術資料作成だけで数ヶ月から1年以上かかることは珍しくありません。
計画の不備、公共施設管理者との意見対立、近隣住民との調整難航などが生じた場合、期間はさらに長期化します。
したがって、専門家に依頼する最大の目的は、これらの準備段階での手戻りをなくし、全体の流れをスムーズに進行させることにあります。
開発許可申請のポイントと注意事項
開発許可申請を確実に進めるためには、地域の特性や法改正の動向を踏まえた戦略的な対応が必要です。
自治体・条例ごとの規定や審査基準
開発許可は、全国共通の都市計画法(法第33条の技術基準、法第34条の立地基準)に基づく一方で、自治体ごとの条例や指導要綱にも大きく影響を受けます。
- ローカルルールの適用: 愛媛県内の特定都市計画区域では、法第29条の基準面積が引き下げられている例があり 、また松山市では0.3ha以上の開発に指導要綱が適用されます。
- 用途地域との整合性: 市街化区域内や非線引き都市計画区域内の開発では、計画する建築物がその区域に指定された用途地域に適合していることが審査基準となります。
自治体ごとのローカルな要求事項、特に松山市の指導要綱に基づく協定締結の可能性は、単に法令を遵守するだけでなく、行政が目指すまちづくり(都市マスタープラン)に沿った開発であるかという、より高度な適合性を試されていると理解すべきです。
不許可となるケースと対応策
開発許可が不許可となる主なケースは、市街化調整区域での立地基準(法第34条)への不適合や、公共施設の整備基準を満たせない技術的な不備です。また、近年では災害リスクの高い区域での開発抑制基準に抵触する場合も不許可の原因となります。
不許可という最悪の事態を避けるためには、申請後の審査を待つのではなく、計画の初期段階での「事前協議」を徹底し、行政の意向を正確に把握し、問題点を事前に修正することが唯一かつ最重要な対応策となります。
特に市街化調整区域の難解な案件では、行政協議を通じて、開発の特例的な必要性について論理的な証拠をもって交渉することが不可欠です。
近隣住民・公共施設・土地利用計画への影響
開発行為が周辺環境に与える影響は大きく、近隣住民とのトラブルや公共施設管理者との調整が、事業全体の遅延の大きな原因となります。
- 近隣住民への配慮: 松山市では、指導要綱に基づき、市長が必要と認めるときは、自然・環境の保全や公害の防止、災害の防止などについて事業者と協定を締結することが規定されています。事業者は、近隣住民への十分な説明責任を果たし、紛争を未然に防ぐための配慮が求められます。
- 公共施設への適合: 開発に伴い新設される道路や上下水道などの公共施設は、法第32条に基づき、施設管理者の技術基準と同意を得たうえで計画されなければなりません。
業務用・居住用・法人申請の留意点
計画する建築物の用途(居住用、業務用、宿泊施設、福祉施設など)によって、市街化調整区域における立地基準の判断や、必要なインフラ整備要件が大きく変わります。
特に、既存の空き家を活用し、ゲストハウスや福祉施設へ用途変更する場合、建物の規模によっては開発許可の対象となることがあります。空き家特例制度を利用することで「投資目的」での活用が可能となるメリットがありますが、この活用計画と開発許可申請(または建築基準法上の用途変更手続き)を整合させるためには、不動産活用戦略と法務手続きの両面に精通した専門家によるアドバイスが不可欠です。
開発許可申請を専門家に依頼するメリット
開発許可申請は、高度な専門知識と、膨大な作業量、そして多岐にわたる関係機関との調整を伴うため、専門家への依頼は事業の効率化、期間短縮、および不許可リスクの低減に不可欠です。
開発許可申請代行の流れと選び方
専門家への依頼は、煩雑な行政手続きや技術的な図面作成、そして行政協議に伴う精神的負担を大幅に軽減します。特に、複雑性の高い市街化調整区域の案件においては、行政書士の専門知識と交渉力が、許可取得の鍵となります。
代行を依頼する場合、一般的な流れは、相談・見積もりから始まり、現地調査、測量・設計、事前協議、申請書提出、許可取得、完了検査へと進みます。
行政書士・土地家屋調査士事務所の選定ポイント
- 実績と連携体制: 開発許可申請代行実績、特に市街化調整区域での実績が豊富であるかを確認すべきです。また、行政書士は法務手続きを、土地家屋調査士は技術的な測量・図面作成を担うため、両者がシームレスに連携できるワンストップサービス体制を持つ事務所を選定することが、手続きの遅延を防ぐ上で重要です。
専門家依頼時の費用相場と見積もりの注意点
専門家への依頼費用は、行政書士報酬の他に、測量費用、設計費用、そして公的手数料(実費)で構成されます。依頼時には、これらの内訳が明確に示されているかを確認し、特に事前協議の回数が増加した場合の追加費用についても、初期見積もりの段階で明確にしておくべきです。
複合資格が実現する戦略的サポート
村上行政書士事務所が保有する行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士のトリプル資格は、松山市での不動産活用を検討する方に対し、以下の統合的な価値を提供します。
- 許認可+取引の専門性: 許認可手続き(行政書士)だけでなく、開発後の土地の売買や賃貸(宅建士)といった不動産の出口戦略までを考慮した、総合的な開発計画のアドバイスが可能です。
- 再生戦略の統合: 認定空き家再生診断士として、空き家を含む既存資産の潜在的な価値を診断し、開発(造成)を伴う、または用途変更のみで済む最適な活用プラン(例:地域資源を活用した宿泊施設や福祉施設)を提案できます。
これは、単なる許可の取得だけでなく、顧客の不動産資産全体の戦略的な価値最大化に貢献できる、松山市地域に特化した強力な付加価値となります。
まとめ|開発許可申請の費用と流れをスムーズに進めるコツ
開発許可申請は、費用(主に専門家報酬)と期間(主に事前協議と技術資料作成)の両面において、その複雑性を正確に理解し、早期に対策を講じることが成功の鍵となります。
開発許可申請をスムーズに進めるためには、次の3点を実行することが不可欠です。
- 徹底した初期調査: 計画地の法規制(区域区分、農地指定、法第34条適合性)を早期に確認し、松山市の指導要綱(0.3ha以上)の適用要件を遵守すること。
- 早期かつ綿密な行政協議: 行政(松山市)との事前協議を早い段階で開始し、地域の要件を満たす計画に修正することで、不許可リスクと手続きの遅延を防ぐこと。
- 専門家チームの一元化: 行政書士と土地家屋調査士や設計士といった技術専門家との連携を円滑に進め、高度な要求水準を満たす技術資料を迅速に作成すること。
複雑な開発許可申請、特に市街化調整区域や農地転用が絡む案件において、行政手続き、不動産取引、そして地域資源の活用戦略までをワンストップでサポートできる村上行政書士事務所は、松山市における不動産活用の最良のパートナーとして、事業のスムーズな進行を強力にサポートします。
お気軽にお問い合わせください。



