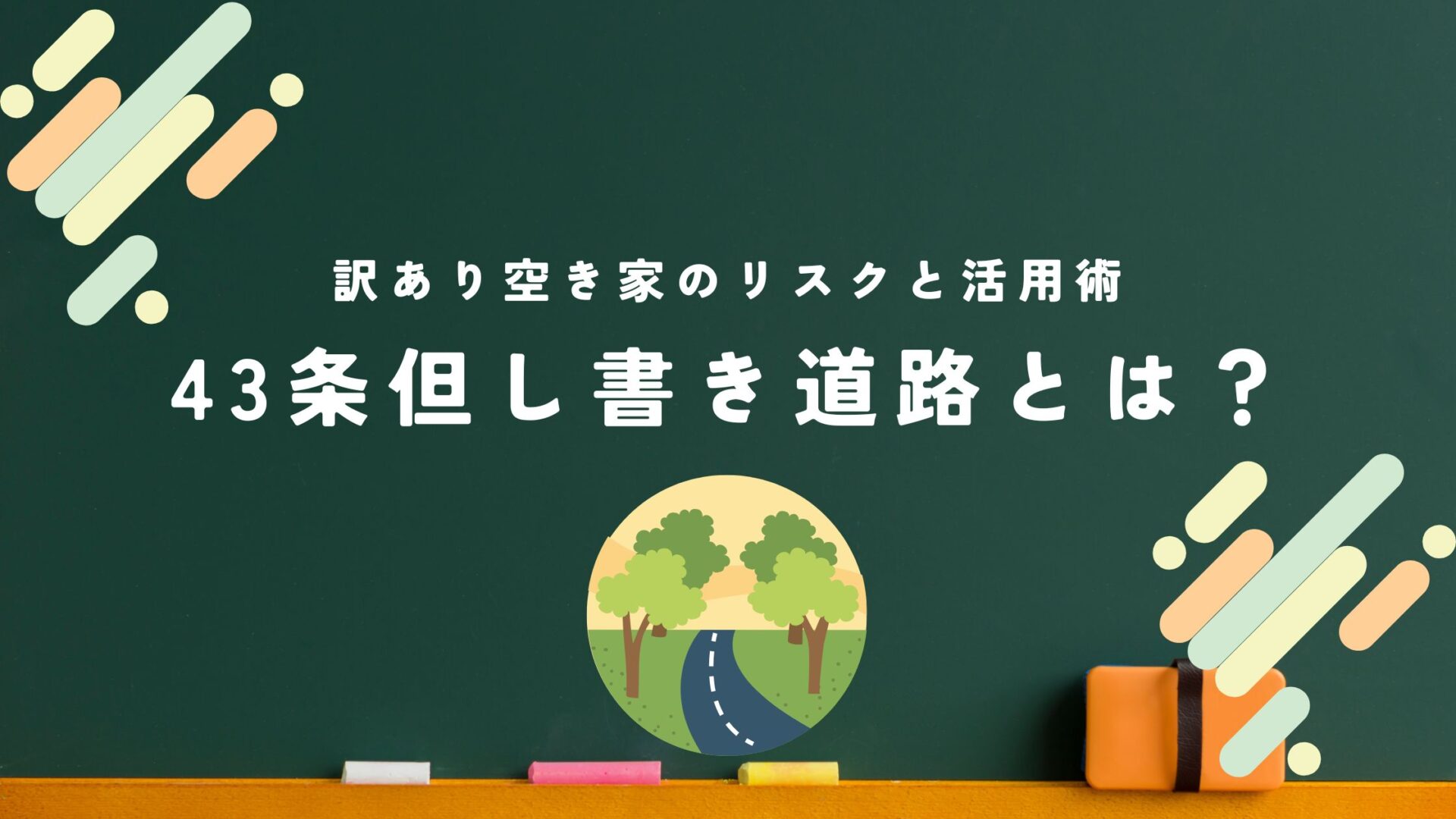
43条但し書き道路とは?訳あり空き家のリスクと活用術を紹介
「43条但し書き道路」と聞いて、その理由が分からず困っていませんか?
特に、先祖から引き継いだ松山市内の空き家が、実は建築基準法上の道路に接していない「訳あり物件」だった…というケースは少なくありません。
この問題の鍵を握るのが、「43条但し書き道路」という特例です。
この記事では、専門家である行政書士の視点から、43条但し書き道路の基本から、そうした物件の具体的なリスク、そして賢く活用・売却する方法まで、網羅的に解説します。
松山市で空き家にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
43条但し書き道路とは|基礎知識と建築基準法の概要を解説

建築基準法43条の内容と但し書きの意味
建築基準法では、災害時の避難や日照・通風を確保するため、「建物を建てる敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」と定めています。これが「接道義務」と呼ばれるものです。
しかし、昔からある集落や密集市街地などでは、この基準を満たせないケースが多く存在します。
そこで、特定行政庁が「交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、例外として建築を許可する規定が設けられました。
これが「建築基準法43条第2項第2号(旧:43条1項但し書き)」であり、この規定によって認められた道路を一般的に「43条但し書き道路」と呼びます。
簡単に言えば、「原則として建築はできないけど、特定の条件を満たせば例外的にOK」とするための救済措置です。
43条但し書き道路に該当する道路の種類と特徴
43条但し書き道路に該当するのは、主に以下のような道路です。
- 農道や里道、赤道など:元々、通行目的ではなかった幅の狭い道路
- 私道:個人の敷地を通過する道路で、建築基準法上の指定を受けていないもの
- 集落内の細い通路:昔から人が通っていた道で、幅員が4m未満のもの
- 行き止まりの道路:一方が行き止まりになっており、避難経路として不十分なもの
これらの道路は、物理的には存在しますが、建築基準法上の「道路」として扱われないため、原則として新たに建物を建てたり、既存建物を建て替えたりすることはできません。
セットバックや位置指定道路との違い
43条但し書き道路は、セットバックや位置指定道路とは明確に異なります。
- セットバック:建築基準法上の「みなし道路(42条2項道路)」に該当する道路で、将来的に幅員を4mにするため、道路の中心線から2m後退(セットバック)して建物を建てる義務があります。
- 位置指定道路:個人が私道を築造し、特定行政庁から道路としての指定を受けたものです。こちらも建築基準法上の「道路」として扱われます。
一方、43条但し書き道路は、これらのように公的に道路と認められているわけではありません。あくまでも、特定の建物の建築を例外的に許可するための制度であり、その効力は限定的です。
43条但し書き道路が敷地・建物・用途に与える影響
43条但し書き道路に接する敷地は、原則として「再建築不可」となります。つまり、既存の建物を解体して更地にした場合、新たに建物を建てることができません。
また、増築や大規模なリフォームにも制限がかかることがあり、将来的な用途変更(例えば、住居から店舗への変更など)も難しくなるケースがあります。これは、再建築不可物件の資産価値を大きく下げる要因となります。
43条但し書き道路の空き家|よくあるトラブルとリスク

再建築不可物件・訳あり空き家の典型的トラブル事例
- 隣地とのトラブル:隣の家も同様の条件で、建て替え時に隣地所有者の同意が必要となり、交渉が難航する。
- 共有持分トラブル:私道の持分を複数の所有者で共有しており、売却や建て替えの際に全員の同意が必要になるが、連絡がつかない、あるいは反対される。
- 相続トラブル:再建築不可物件であることを知らずに相続し、後からその事実が判明。売却できず、固定資産税だけを支払い続ける羽目になる。
資産価値・売却価格への影響とローン・査定の現実
再建築不可物件は、一般的に周辺相場の2割〜5割程度安価になる傾向があります。多くの金融機関は、再建築不可物件に対する融資に消極的で、住宅ローンを組むことが極めて困難です。
そのため、現金で購入できる買主を探す必要があり、売却のハードルが非常に高くなります。
専門業者による査定でも、再建築不可である事実が判明すれば、その評価額は大きく下がります。
所有者・隣地・私道持分の権利関係とトラブルの要因
43条但し書き道路の多くは、私道であり、複数の土地所有者によって共有されているケースが少なくありません。
- 権利関係の不明確さ:登記簿に私道持分が記載されていない、あるいは共有者の所在が不明な場合、同意を得ることができず、建て替えや売却が滞る。
- 私道協定の有無:私道協定が結ばれていれば、ある程度のルールに基づいて利用できますが、協定がない場合は、通行を巡るトラブルに発展することもあります。
43条但し書き道路の空き家が抱える将来的なリスク
- 災害リスク:幅員が狭い道路は、緊急車両の進入が困難なため、災害時に適切な救助活動が行えない可能性があります。
- 建物の老朽化:再建築ができないため、建物の大規模な改修や建て替えができず、老朽化が進んでいく。
- 資産価値の下落:一度「再建築不可」というレッテルが貼られると、その後の資産価値の回復は非常に困難です。
43条但し書き道路の空き家活用・売却術
空き家活用のアイデア|リフォーム・用途変更・賃貸化の可能性

再建築不可でも、リフォームや用途変更、賃貸化は可能です。
- リフォーム:大規模な改修を伴わない範囲であれば、快適に住めるようにリフォームできます。
- 賃貸化:建物の状態が良ければ、賃貸物件として貸し出すことで収益化が可能です。ただし、借主には再建築不可である事実をきちんと説明する必要があります。
- 用途変更:一定の要件を満たせば、住居から事務所などに用途変更できる可能性もあります。ただし、この場合も建築確認申請が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。
スムーズな売却のコツ|不動産業者・買取業者の選び方
- 再建築不可物件に強い業者を選ぶ:一般的な不動産業者は、再建築不可物件の売却を敬遠することがあります。訳あり物件専門の不動産業者や買取業者を選ぶのが賢明です。
- 複数の業者に査定を依頼する:1社だけでなく、複数の業者に査定を依頼することで、適正な価格を見極めることができます。
訳あり物件の買取相場と価格アップの工夫
- 買取相場:一般的に、再建築不可物件は相場より安価になります。
- 価格アップの工夫:
- 測量図や協定書を準備する:権利関係を明確にすることで、買主は安心して購入を検討できます。
- 土地家屋調査士に依頼する:境界を明確にすることで、売却時のトラブルを避けることができます。
- 専門家へ相談:建築士や行政書士に相談し、法的リスクを事前に洗い出しておくことで、買主への説明責任を果たしやすくなります。
業者依頼時の注意点と無料査定の活用法
- 査定価格の根拠を明確に説明してもらう:なぜその価格になるのか、納得ができる説明を求めましょう。
- 仲介手数料・買取手数料を確認する:業者によって手数料が異なるため、事前に確認しておきましょう。
- 無料査定の活用:多くの不動産会社は無料査定を行っています。まずは査定を依頼し、物件の価値を知ることから始めましょう。
43条但し書き道路で建て替え・増改築する方法と許可申請の流れ
再建築や増改築に必要な条件・基準と接道義務の確認
43条但し書きの許可を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないこと:例えば、周辺道路との接続状況や、緊急車両の進入路が確保されているかなどが審査されます。
- 建築審査会の同意:特定行政庁が単独で判断するのではなく、専門家で構成される建築審査会の同意を得る必要があります。
- 隣地所有者の同意:多くの場合、隣地所有者との協定書作成や同意取得が求められます。
許可申請・事前協議の手順と提出すべき書類
- 特定行政庁への事前相談:まずは、松山市の建築主事や建築指導課に相談し、許可の見込みがあるか確認します。
- 申請書類の準備:申請書、配置図、平面図、断面図、立面図、公図、登記簿謄本、隣地所有者の同意書など、多くの書類が必要です。
- 建築審査会への申請:必要書類を揃え、審査会に申請します。
- 現地調査・審査:審査会の委員が現地調査を行い、申請内容を審査します。
協定書作成・同意取得の流れと審査会での審議ポイント
- 協定書作成:専門家(行政書士など)に依頼し、隣地所有者との間で、再建築に関する協定書を作成します。
- 同意取得:協定書の内容を丁寧に説明し、隣地所有者から同意を得ます。
- 審査会の審議ポイント:
- 再建築の必要性
- 周辺環境への影響
- 交通安全や防災上の問題はないか
申請から許可までの期間と費用相場
- 期間:申請から許可までには、数ヶ月から半年、場合によっては1年以上かかることもあります。
- 費用:申請手数料のほか、専門家(建築士、行政書士)への報酬、測量費用などがかかります。報酬は依頼する内容によって大きく異なりますが、数十万円〜が目安となります。
知っておきたい43条但し書き道路空き家のメリット・デメリット
43条但し書き道路物件の救済制度や包括認定制度の概要
一部の自治体では、特定の地域における43条但し書き道路について、包括認定と呼ばれる制度を設けています。
これは、個別の許可申請を不要とし、一定の基準を満たせば再建築を可能にするものです。松山市の状況については、建築指導課に確認が必要です。
資産価値・用途の広がりなどのメリット
再建築不可物件は、デメリットばかりではありません。
- 購入価格の安さ:安価に購入できるため、リフォームして住む、あるいは賃貸物件として収益化するなどの方法で、費用対効果の高い投資になる可能性があります。
- 固定資産税の安さ:評価額が低いため、固定資産税も安価になるケースが多いです。
- 希少性:再建築不可という条件が、逆に独自の価値を生み出すこともあります。
再建築の制限・トラブル等のデメリットと慎重な検討ポイント
- 再建築の制限:最も大きなデメリットであり、将来的な住み替えや建て替えが困難になります。
- トラブルのリスク:隣地や私道の所有者との間で、権利関係を巡るトラブルが発生する可能性があります。
- 売却の難易度:再建築不可であることから、売却先を見つけるのが難しく、希望の価格で売れない可能性があります。
43条但し書き道路空き家の買主・売主が守るべき注意点
購入前の調査ポイントと自治体への事前相談の重要性
- 道路の種類を確認:まずは、接している道路が建築基準法上のどの道路に該当するのか、松山市の建築指導課で確認しましょう。
- 権利関係を調査:登記簿謄本を確認し、私道持分や協定書の有無などを調査します。
- 専門家へ相談:購入前に行政書士や建築士に相談し、物件が抱えるリスクを事前に把握することが重要です。
ローン利用・住宅ローン審査のハードルと対策
- ローン利用の難しさ:多くの金融機関は再建築不可物件への融資に慎重です。
- 対策:
- 現金での購入を検討
- ノンバンクの利用:ノンバンク系のローンは、再建築不可物件でも利用できる場合がありますが、金利が高くなる傾向があります。
- 専門家への相談:不動産業者やファイナンシャルプランナーに相談し、資金計画を立てましょう。
契約書・協定書・権利関係の確認事項
- 契約書:再建築不可である事実を契約書に明記し、売主・買主双方でリスクを理解した上で契約を締結することが重要です。
- 協定書:私道協定がある場合は、その内容を十分に確認しましょう。
- 重要事項説明:不動産業者から重要事項説明を受ける際、再建築不可であること、それに伴うリスクについて、きちんと説明を受けましょう。
将来的なリスク・再建築不可となる可能性の見極め方
将来的なリスクを避けるためには、物件の情報を徹底的に調査することが不可欠です。建築主事への相談はもちろん、専門家(行政書士や建築士)に依頼して、物件の法的リスクを評価してもらいましょう。
まとめ|43条但し書き道路の空き家活用・売却で後悔しないために

43条但し書き道路に接する空き家は、再建築ができないという大きなリスクを抱えています。しかし、その事実を正しく理解し、適切な対策を講じれば、活用・売却の道は開けます。
松山市で空き家にお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、行政書士の資格に加え、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格も保有しており、多角的な視点からあなたの空き家問題をサポートします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。



