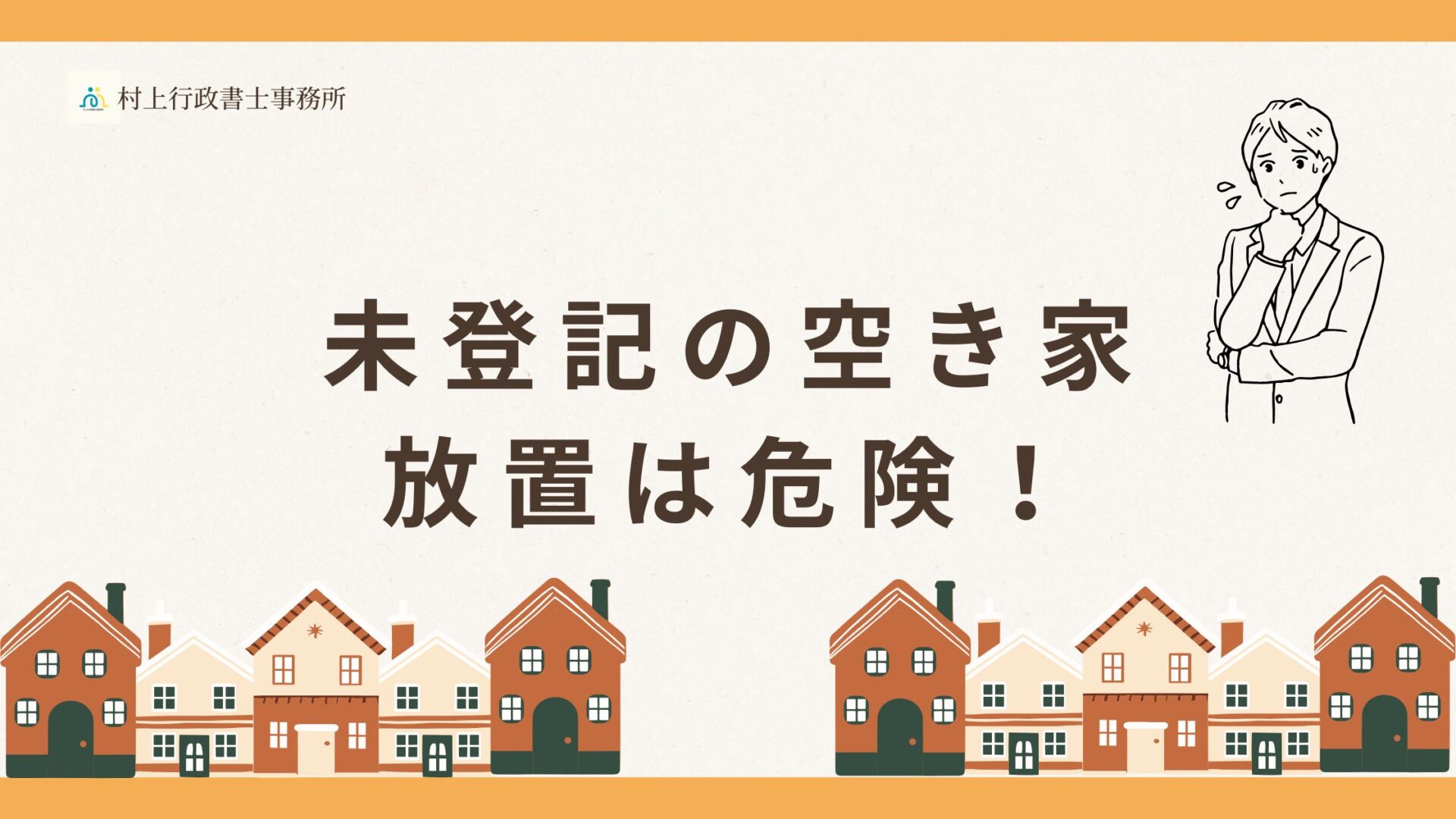
未登記の空き家、放置は危険!売買時のリスク&トラブル回避術
「親から実家を相続したけど、古い建物だし、そもそも登記されていないみたい…どうすればいいの?」
松山市で空き家を所有している方の中には、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
登記されていない「未登記建物」の空き家を放置すると、さまざまなリスクやトラブルに巻き込まれる可能性があります。しかし、正しい知識と手続きを踏めば、安心して売却を進めることができます。
この記事では、未登記建物の空き家が抱えるリスクから、トラブルなく売却するための具体的な方法まで、村上行政書士事務所がわかりやすく解説します。
未登記建物の空き家売買に関する基礎知識
未登記建物とは何か?その定義と特徴

未登記建物とは、建物が新築された際に義務付けられている「建物表題登記」がされていない建物のことを指します。建物表題登記は、建物の物理的な状況(所在、家屋番号、種類、構造、床面積)を明確にし、所有者を公示するためのものです。
登記されていない建物は、法務局に所有者や建物の情報が登録されていないため、公的に所有者が誰であるか証明することができません。
未登記のままになっている主な理由は以下の通りです。
- 建築された時期が古く、登記の制度が普及していなかった。
- 建て替えや増築をした際に、登記の手続きを失念していた。
- 所有者が亡くなり、相続人が手続きを知らずに放置していた。
未登記建物のリスク:放置の危険性
未登記の空き家を放置すると、以下のようなさまざまなリスクが発生します。
- 所有権の証明ができない: 売買や相続の際に、自分がその建物の所有者であることを公的に証明できません。これは、第三者への売却や、抵当権の設定を難しくします。
- 相続手続きが複雑になる: 相続人が複数いる場合、誰が所有者なのかが曖昧になり、遺産分割協議が難航する原因になります。
- 固定資産税の課税ミス: 登記情報が更新されていないため、実際の建物の状況と固定資産税の課税状況が一致しない場合があります。
登記がないことによる所有権トラブルの事例
実際に起こりうる所有権トラブルの事例を紹介します。
- 事例1:相続人同士の対立 相続人が複数いる場合、未登記の建物を売却しようとしても、所有者が明確でないため、売却の合意形成が難しくなります。その結果、遺産分割協議が進まず、兄弟間でトラブルになることがあります。
- 事例2:第三者による不法占拠 未登記の空き家は、所有者が誰かわからないため、不法占拠されても法的に対応するのが困難になる場合があります。
空き家特例と税制の理解
空き家特例とは?その基本的な内容
「空き家の発生を抑制するための特例措置(通称:空き家特例)」とは、相続した空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
この特例を適用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 相続開始から売却まで、被相続人以外が居住していなかったこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 売却価格が1億円以下であること
など、細かい要件が定められています。
居住用財産の3,000万円控除の併用方法
空き家特例は、「居住用財産の3,000万円特別控除」とは別の制度です。
空き家特例は相続した空き家を売却した際に適用されますが、居住用財産の3,000万円特別控除は自分が住んでいた家を売却した際に適用されます。
それぞれの制度を同時に使うことはできませんが、どちらか一方を利用することで税負担を大きく軽減できます。未登記の空き家でも、要件を満たせば空き家特例を適用できる可能性があります。

未登記建物を売却する際の税金の取り扱い
未登記建物を売却する場合も、通常の建物と同様に譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
未登記の建物は、取得費(建物の購入費や建築費)が不明なケースが多く、その場合は売却価格の5%を概算取得費として計算することになります。取得費が不明なままだと税額が高くなる可能性があるため、注意が必要です。
未登記建物の売買に必要な書類と手続き
必要書類一覧:未登記建物売買時に求められるもの

未登記建物を売却する際には、以下のような書類が必要になります。
- 建物に関する書類:
- 固定資産税の納税証明書または評価証明書
- 建築確認済証、検査済証(あれば)
- 売主に関する書類:
- 住民票
- 印鑑証明書
- 身分証明書
- その他:
- 境界確認書(土地家屋調査士による測量が必要)
- 実印
これらの書類を揃えることで、建物の存在や所有権を証明する根拠となります。
所有権保存登記と所有権移転登記の流れ
未登記建物を売却する際は、原則として売却前に登記を完了させる必要があります。
- 建物表題登記: 土地家屋調査士に依頼し、建物の現況を調査・測量してもらい、法務局に登記を申請します。
- 所有権保存登記: 建物表題登記が完了したら、司法書士に依頼し、誰が所有者であるかを登記します。これにより、公的に所有権が証明されます。
- 所有権移転登記: 売買契約後、買主への所有権移転登記を行います。
これらの手続きをすべて完了させることで、安心して売却ができます。
登記事項証明書の取得方法とその意義
登記事項証明書は、建物の登記簿謄本とも呼ばれ、建物の所有者や抵当権などの権利関係が記載されている重要な書類です。
未登記の建物は登記事項証明書が存在しないため、代わりに固定資産税の納税証明書などで建物の存在を証明することになります。
未登記建物の売買時に注意すべきリスクとトラブル
購入者が知っておくべきリスクとは?
購入者にとって、未登記建物の購入は大きなリスクを伴います。
- 所有権の証明ができない: 購入後も所有権が不安定な状態が続きます。
- 住宅ローンが組めない: 金融機関は、登記のない建物を担保として評価できないため、ローンを組むのが困難です。
- 境界トラブル: 隣地との境界が不明確な場合、将来的にトラブルに発展する可能性があります。
売主として気をつけるべき点
売主として、以下の点に注意が必要です。
- 売買価格が低くなる: リスクのある未登記建物は、購入希望者が限られ、通常より売却価格が低くなる傾向があります。
- 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任): 売却後に未登記が原因で問題が発生した場合、売主が責任を問われる可能性があります。
トラブルを避けるための専門家への依頼方法
未登記建物の売買は、手続きが複雑で専門的な知識が不可欠です。トラブルを未然に防ぐためには、不動産業者、行政書士、司法書士、土地家屋調査士といった専門家に依頼することが最も確実な方法です。
司法書士と土地家屋調査士の役割
司法書士の業務内容と必要性
司法書士は、不動産の権利に関する登記(所有権保存登記、所有権移転登記など)の専門家です。未登記建物を売却する際には、所有者を明確にするための所有権保存登記を依頼します。
土地家屋調査士との連携方法
土地家屋調査士は、不動産の物理的な状況に関する登記(建物表題登記など)の専門家です。未登記建物の売却前には、土地家屋調査士に建物の現況を調査・測量してもらい、建物表題登記を依頼します。
村上行政書士事務所では、司法書士、土地家屋調査士と連携しながら、登記手続きをスムーズに進められるようサポートします。
専門家に相談するメリット
- 手続きの迅速化: 複雑な手続きを代行してもらうことで、時間と労力を節約できます。
- リスク回避: 専門家の知識と経験により、法的トラブルを未然に防ぎます。
- 正確な情報提供: 最新の法律や制度に基づいた正確なアドバイスが受けられます。
中間省略登記を活用したケーススタディ
中間省略登記の適用条件と流れ
中間省略登記とは、売主から買主へ直接所有権を移転させる登記のことです。未登記建物の場合は、建物表題登記と所有権保存登記を同時に行い、直接買主への所有権移転登記を行うという流れになります。
成功事例:中間省略登記を利用した売却
売主Aさんは、未登記の空き家を相続しました。村上行政書士事務所に相談したところ、提携先の司法書士を紹介。中間省略登記を活用することで、登記費用や手間を削減し、スムーズに買主Bさんへの売却を完了させることができました。
失敗事例:実施しなかった場合のリスク
売主Cさんは、未登記の空き家を売却する際に、中間省略登記を行いませんでした。その結果、売買契約後に所有権の証明ができず、買主Dさんとの間で契約が白紙に戻るトラブルに発展しました。
空き家の存在を放置することの社会的影響
空き家問題が引き起こす地域の課題

松山市でも空き家が増加し、以下のような地域課題が深刻化しています。
- 景観の悪化: 放置された空き家は地域の美観を損ないます。
- 治安の悪化: 不法投棄や犯罪の温床になる可能性があります。
- 倒壊の危険性: 老朽化した建物は、地震や台風で倒壊する危険があります。
放置された空き家を解決するための制度
松山市では、空き家対策として「松山市空家等対策計画」を策定し、空き家の適正管理や利活用を促進しています。
未登記の空き家を売却する具体的な流れ
売却前の準備と必要な手続き
- 専門家への相談: まずは村上行政書士事務所にご相談ください。現状をヒアリングし、最適な解決プランを提案します。
- 建物表題登記の申請: 土地家屋調査士と連携し、建物表題登記を完了させます。
- 相続登記の手続き: 相続した建物の場合、相続登記の手続きが必要になります。
- 売却価格の査定: 宅地建物取引士の資格を持つ専門家が、適正な価格を査定します。
売却条件の設定と査定方法
未登記建物は、そのままでは売却しにくいため、「現状のまま売却する」、「登記を完了させてから売却する」など、さまざまな方法を検討する必要があります。
契約締結までのステップと注意点
売却条件がまとまったら、買主との間で売買契約を締結します。この際、未登記であることや、それに伴うリスクについて、重要事項説明書に明確に記載することが不可欠です。
関連法制度と今後の展望
空き家対策関連の法律と制度
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、管理不全の空き家に対する所有者への指導・命令が強化されています。
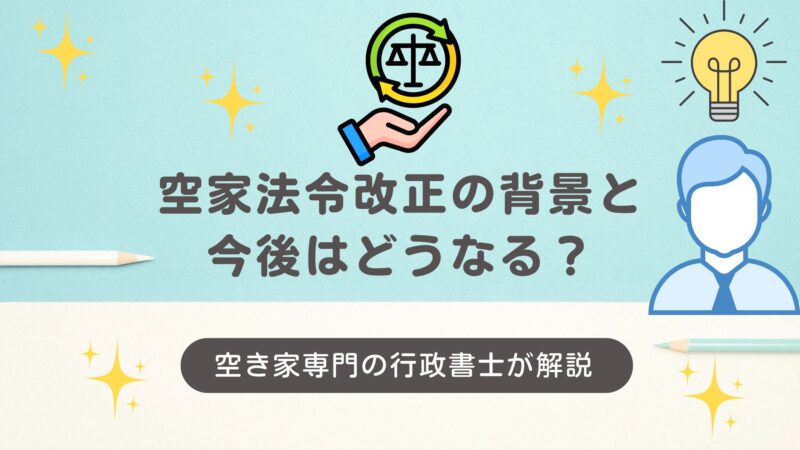
今後の市場の動向と予測
少子高齢化が進む日本では、今後も空き家問題は深刻化していくと予測されています。行政書士や宅地建物取引士といった専門家が連携し、空き家問題の解決に取り組むことが、社会全体の課題解決に繋がります。
未登記の空き家でお困りではありませんか?
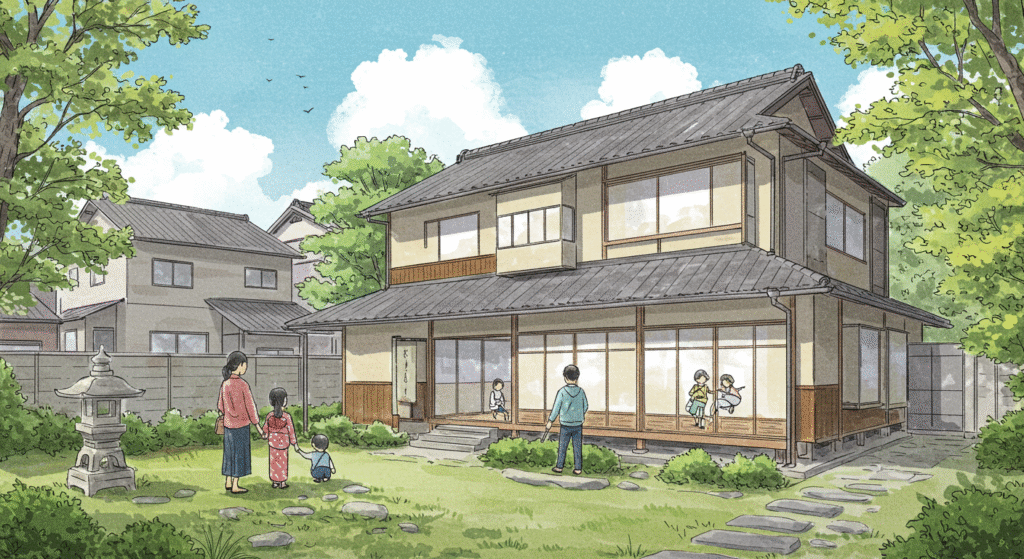
未登記の空き家を所有していると、「どうすればいいのかわからない」と不安に感じるかもしれません。しかし、放置しておくとリスクは増すばかりです。
村上行政書士事務所は、行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格を活かして、あなたの空き家問題をワンストップでサポートします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。



